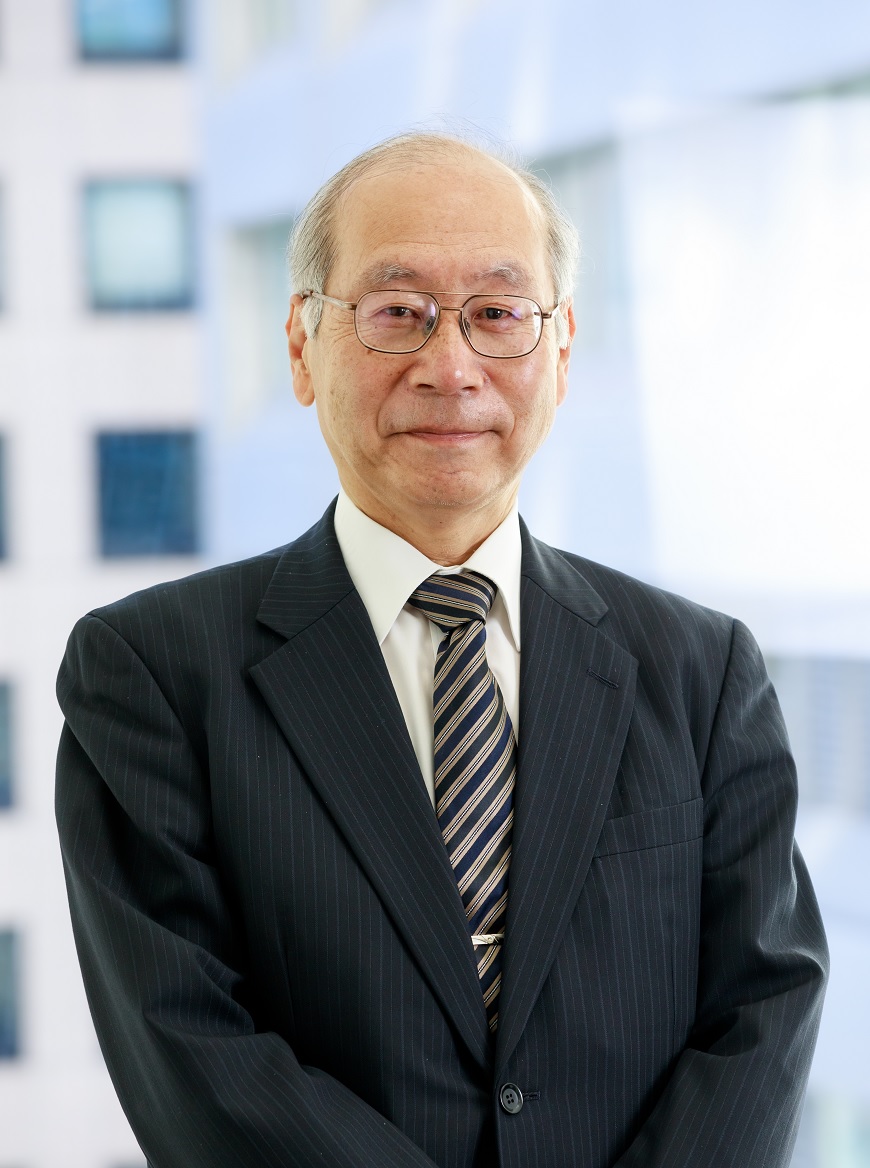[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#18 日本におけるジェンダー平等」:大野恒太郎弁護士(顧問)
日本におけるジェンダー平等
―歩みと課題、法曹界の状況―
私は、本年6月クアラルンプールで開催されたアセアン政府間人権委ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) の会議において、「日本におけるジェンダーの視点から見たビジネスと人権」の題で講演した。これは、現在私が理事長を務めている公益財団法人国際民商事法センター(コラム#5「我が国による法整備支援」参照)が来年創立30周年を迎えるので、その記念行事を前に、アセアン諸国との連携を強化するために行ったものであった。
本稿は、その際の講演内容をベースに、法曹界において見聞きしたことなどを付け加えたものである。
ジェンダーという言葉は、社会的な意味における性別を意味するが、国内法においては「男女共同参画」の語が用いられており、用語をめぐっては政治的な文脈もあって様々な議論がなされている。しかし、ジェンダーも男女共同参画も基本的には同義であると解され、内閣府も男女共同参画の英語表記をGender Equality としているところから、両者の使い分けは結局用語としての分かりやすさに帰するものと理解される。そして、ジェンダーの語は、国際的に広く認知されているにとどまらず、国内的にも次第に馴染みのものとなってきたと思われることから、本稿においては、これを用いる。
1 これまでの経過
1947年に公布された日本国憲法は、両性の平等を規定している。
ところが、日本社会の中には、「男性は外で働き、女性は家庭で家族を支える」という伝統的な役割分担の考え方が根強く残っていた。そうしたこともあり、かつては多くの法律において、男女平等よりも女性の保護に重点を置く規定が置かれていた。女性の深夜労働を禁止し、時間外労働・休日労働を制限する法規制がその典型例である。
仕事始め記念写真(1984年正月、法務省刑事局)
これは、40年余り前、私が当時勤務していた職場の新年仕事始めの時の記念写真である。この写真を見ると、女性職員の数は全体の1割にも満たない少数であったことや、その多くが晴れ着である着物を着用していたことに気付かれると思う。当時、女性職員はしばしば「職場の花」などと形容され、必ずしも実質的な役割を担うことを期待されてはいなかった。そして、「寿退社」の語が示すように、結婚と同時に退職して家庭に入ることがある意味当然であると考えられていたのである。
しかしながら、高等教育を受けた女性の数が増加するにつれ、そのような飾り物的な役割に甘んじるのではなく、社会においてより実質的な活躍をしたいと思う者が増えていった。
そして、日本が1985年女性差別禁止条約を批准したことに伴い、翌86年、男女雇用機会均等法(それまでの勤労婦人福祉法を改正したもの)が施行され、これが女性の社会進出の法的な転機となった。その後、雇用機会、業務内容や昇進に関し、女性に対する差別的な取扱いを除去するために様々な法改正が行われた。これを一言で言うならば、女性を一律に保護することから、男女平等を重視する方向への転換と認めることができるであろう。それにより、女性の社会進出は着実に進んでいった。
現在、法的には男女平等は概ね達成されている。引き続き法改正の必要性が議論されているのは、選択的夫婦別姓制度の導入や、一定の所得があると税法等の関係で被扶養者として有利な取扱いを受けられなくなる制度の改正についてである。これらは、法律上は男女を差別的に規定しているものではないが、実際の運用上女性の社会進出を阻害していると指摘されているものである。
2 ジェンダー・ギャップ指数における低評価とその原因
このように法制上は男女平等がほぼ実現され、女性の社会進出が相当進んできたにもかかわらず、国際的に比較した場合、日本はジェンダー平等においてなおかなり遅れているとされている。
この表は、スイスの民間団体ワールド・エコノミック・フォーラムによって公表された2025年世界ジェンダー・ギャップ指数の順位表の抜粋である。これによれば、日本は順位表に掲げられている148国中118位に位置付けられている。アセアン各国との関係で言えば、10か国のうち、9か国がいずれも日本より上位であるとされ、残る1か国であるミャンマーについて、現在の政治状況にかんがみて評価の対象とはされなかった。
ジェンダー・ギャップ指数は、経済、教育、健康、政治の4分野における客観的なデータを総合して点数を算出している。
日本の順位を世界的に低いものにしているのは、経済面と政治面のスコアである。経済面において、同一労働に対する女性の賃金は男性の60.3%に過ぎず、上級管理職における女性比率は16.1%にとどまる。
また、政治面においては、評価の時点において、衆議院(下院)における女性議員の比率は、15.7%に過ぎず、閣僚19名中女性は僅か2名であった。もっとも、先般高市早苗氏が女性初の内閣総理大臣に就任したことは、政治分野における指標とされている国政トップの在任期間に関わるものであるから、この方面における日本のスコアを向上させることになるものと思われる。
これに対し、教育面や健康面において男女に大きな差はない。むしろ寿命に関しては、女性の平均寿命87.13年は男性の81.09年を6年以上も上回っている。もっとも、ジェンダー・ギャップ指数は専ら女性に対する不利益取扱いを是正する観点から作成されているため、このように女性に有利な数字はスコアに反映されていない。
それならば、日本において法的には男女平等が保証されているにもかかわらず、現実には世界的に見てなおかなり立ち遅れているのはなぜか。
それは、日本の職場文化の中に、女性が勤務を続け、昇進することを妨げる様々な要因が存在しているからである。そうした要因の中には、長時間労働や勤務時間後の頻繁な飲み会のように、男性中心の職場において長年にわたって形成された慣行が含まれている。このような慣行の背後には、1でも触れた伝統的な男女間の役割分担意識がアンコンシャス・バイアスとして存在していると見るべきであろう。そして、定年まで同じ組織で勤務するという生涯雇用制度が依然として支配的であることに照らすと、こうした職場慣行は、女性、取り分け育児期の子を持つ母親にとって、男性と競争し、昇進をしていくことを困難にしているのである。
3 女性の社会進出を一層促進するための方策と新たに浮かび上がってきた問題
日本は近年少子高齢化により労働人口の急速な減少に直面している。そのような中で社会を支える経済活動を維持していくためには、女性の社会進出が不可欠である。そこで、政府はこれを優先的政策課題とし、2015年には女性活躍推進法を成立させるなどしている。
そうした観点からは、男女いずれにも関わる働き方や男女の役割分担に関する考え方を改革することが必要である。
働き方の改革としては、最近10年間、長時間労働の是正や、同一労働・同一賃金の原則により女性の多くを占める非正規労働者の待遇を改善することなどの取組みが行われてきた。そして、在宅勤務もコロナ禍によって急速に普及した。このような柔軟な働き方は、女性に対してはもとより、男性に対しても、個々人の実情に応じた多様な働き方を可能にするものであった。
また、家庭においては、男性も育児や介護を含む家事により積極的に参加することが求められるようになった。かりに男性が従来同様家事を積極的に担わず、育児・介護等も含む家事は女性の責任であるとの古い考え方が維持されるのであれば、社会で働く女性の負担は過重になり、これをこなすためには、スーパーウーマン的な能力や努力が求められることになってしまう。
家事面の役割分担における変化は、近年顕著であり、その好例は男性の育児休暇取得である。男性の育児休暇制度は20年ほど前に導入されたが、当時実際にはほとんど取得されなかった。しかし、2023年には取得率は30%に達し、なお上昇を続けており、しかも取得期間も伸びている。
さらに、両親が社会で働くことができるよう、日中子供を預けることができる保育園の整備も急速に進められた。
企業側としても、人手不足の中で、貴重な女性社員を確保し続けるため、時短制度の採用等様々な方策に力を入れるようになっている。
働く女性が安心して出産し育児を行うことができるようになれば、少子化問題に対しても一定の効果があると期待される。
こうして出産を経た女性社員が働き続けることは今や当たり前のこととなっているが、その一方で、マミートラックと呼ばれる問題が残っていると指摘される。これは、出産を終えて職場に復帰した女性社員に対し、上司や周囲が育児との両立に配慮するあまり、負担の重い重要な業務を割り当てないため、当該女性がいつしか疎外感に陥り、意欲を失っていく現象を指す。
もとより出産を経た女性社員の置かれた状況は、人により千差万別であるので一律な対応にはなじまない。女性社員については、例えば、独身者、既婚者であって子供がいない者、既婚者であって子供を有する者等、その立場によって考え方が大きく異なり、他の女性社員に対する見方が男性社員より厳しいことも少なくない。
したがって、それぞれの個別の事情や考え方を把握できるよう、企業側には女性との丁寧なコミュニケーションが望まれる。
さらに、管理的立場の女性を増加させることも重要である。
生涯雇用制度の下では、企業の役員に就任するためには相当の経験を積んで一定の年齢に達していることが前提とされる。したがって、多くの上場企業においては、女性を役員ポストに就けるためには社内人材の養成が間に合わず、しばしば外部から女性の社外役員を招聘している。私がいくつかの会社において経験したところからすると、女性の社外役員の方は総じて優秀である。特に男女雇用均等法の施行が軌道に乗るまでの時代においては、国内の大手企業による女性の採用が限られていたため、まず外資系企業に就職し、その後転職されたような方も少なくなく、そうした方々は外国語に堪能であるとともに、経験の幅や視野も広いように思う。
現在多くの会社が女性幹部の養成に積極的に取り組んでおり、特別なプログラムやメンター制度等の方策を講じていることから、上級管理職の人数も着実に増加しつつある。しかも、生涯雇用制度もより柔軟なものへと改められつつあることからすれば、有能な女性の登用は、今後ますます増加するであろう。
ジェンダー平等は、ビジネス界においても大きな影響を有するに至っている。先年、我が国の有名企業における取締役選任議案の中に女性が含まれていなかったことから、経済界のリーダーとされてきた同社経営者の取締役選任が危うく否決されそうになったことがあり、企業側に強烈な警鐘を鳴らした。その反面、ジェンダー平等についての先進的な取組みは、今やその企業の製品やサービスのブランド価値を高める重要な要因と認められるようになった。
もっとも、このようにジェンダー平等に関する意識が高まってくると、これまで必ずしも十分な議論が行われて来たとは言い難い問題も注目されるようになる。そうした例の一つが、職場におけるセクハラである。
最近、男性人気タレントが某テレビ局の女性アナウンサーに性暴力を加えた旨が広く報道され、同テレビ会社にはこれまで長く女性アナウンサーを重要な顧客の接待に当たらせる慣行があったと指摘された。しかも、当該アナウンサーが会社に対し暴行を受けた旨を通報したにもかかわらず、会社側は適切に対応しなかったことが明らかになった。こうしたことから、会社は強い社会的非難の対象となり、スポンサーが一斉にそのテレビコマーシャルを引き揚げたため、会社の業績が急速に悪化し、社長らは辞任を余儀なくされることとなった。社長らは、後に会社から役員としての責任を追及する損害賠償請求訴訟を提起されている。
このような事件は、ジェンダーに関わる問題が今や企業の命運を左右する重要性を帯びていることを端的に示すものである。
なお、ジェンダーに関連して、性的少数者の人権の問題も議論されるようになっていることにも注目する要がある。
4 法曹界や検察におけるジェンダー平等
以上我が国におけるジェンダー状況について述べたが、最後に法曹界や検察におけるジェンダー平等についても簡単に触れたい。
法曹界における女性進出の黎明期は、昨(2024)年NHKで放映された連続テレビ小説「虎に翼」に採り上げられた。モデルとされた三淵嘉子判事が退官されたのが1979年であり、私が検事に任官したのは1976年であるが、残念ながら三淵氏本人にお目にかかる機会はなかった。
この表は、司法修習第1期以来の修了者数、検事任官者数とそれぞれの中の女性数を示したものである(コラム#13「検事任官者確保」所収の表の再掲)。私が任官した1976年を例に取れば、修習修了者は537名で女性は24名、検事任官者は74名で女性は3名であり、今日に比べれば女性の数が桁違いに少ない。ある高名な検事総長が会合の席で「自分が人事課長をしていた当時は一人も女性検事を採用しなかった」と自慢気に述べているのを耳にした記憶があるが、そのような発言がなされていたこと自体に隔世の感を覚えずにはいられない。したがって、それよりも30年近くも前に任官した三淵氏ら女性法曹の先駆者のご労苦は並大抵のものではなかったと思われる。
「虎に翼」にも似たようなシーンがあったが、かつては女性検事が女性であることを理由に事件関係者から軽く見られるようなこともあったと聞いている。
また、検察の職場も、一昔前までは御多分に洩れず長時間労働や厳しい上下関係が支配的であったから、そのような中で、女性検事が男性に伍して仕事をしていくことは容易ではなかったはずである。私が駆け出しのころは、男性検事に対抗してことさらにバンカラさを強調するような先輩女性検事も見受けられたが、それは男性優位の職場環境に合わせるため、かなり無理をしていたのではないかと思う。
ここで、私が東京地検特捜部に所属し、東京拘置所に通っていた時のエピソードをお話ししたい。1991年のことと記憶しているが、東京拘置所に初めて女性の特捜部検事が被疑者取調べのために通うようになった時のことである。
当時、身柄を拘束した被疑者に対する特捜部検事の取調べは、東京拘置所の古い建物で行われていた(コラム#1「ある取調べの思い出」参照)。取調べ用の個室は、建物5階の長い廊下に沿って片側に20室ほど並び、その中央に会議室、手前と一番奥にそれぞれ手洗いが配置されていた。このフロアーに来る被疑者、取調べに当たる検事・検察事務官、押送を行う拘置所係官はいずれも専ら男性を想定していたので、女性用の手洗いはなかった。しかも、大便所の扉は、保安上の理由で上部が透明のガラス窓となっており、外側から内部を確認できるような仕様だった。そのままでは女性検事が手洗いを利用することはできない。
そのため、拘置所係官の発案により、女性検事には一番奥の手洗いを利用してもらうこととし、使用中にはその手前の廊下の壁に取り付けられた配電盤の扉を大きく開くことによって、誰も奥の手洗いには行かないようにする目印としたのである。
今振り返って見れば、笑い話のようなことであるが、そうした環境の中で、ただでさえストレスに満ちた被疑者取調べに当たられた女性検事には本当に頭が下がる。そして、そのようなご苦労の積み重ねが今日の女性検事の活躍に通じる道を次第に切り開き踏み固めていったのだと思う。
いずれにせよ、司法試験は男女に等しく開かれた制度であり、法曹は法のプロフェッショナルとして男女平等を定める法制度の運用に関わることをその職務としているのであるから、前の表に記載されている通り、女性法曹や女性検事の数は次第に増加していった。
近年の数字を見ると、2023年の第76期においては、司法修習修了者1391名でそのうち女性は387名、検事任官者は76名で女性は31名であった。
私は10年ほど前フランスの司法官(判検事)養成機関である国立司法学院を訪ねた際、司法官試補の何と8割が女性であることに驚いた記憶があるが、どこの国においても法曹界や司法は他の分野に比して女性の進出は進んでいる。法律家に求められる知力、倫理感、コミュニケーション力、気力等について男女間に差はなく、社会の多様性に応じて法律家の側にも多様性が求められることからすれば、けだし当然のことであると思われる。
しかも、女性法律家は、単に数が増えたというだけではなく、続々と法曹界における指導的な立場に就いている。例えば、現在最高裁判事15名のうち女性が4名を占め、検事総長や日弁連会長はいずれも女性である。
検察においては、女性検事の数が多くなるにつれ、自然体で勤務する人が増え、かつてのようにことさらに「男勝り」であることを強調するような人はいなくなったように思う。そして、今や女性検事が次々に法務検察の重要なポストに就くようになった。このような女性検事の躍進は、決して女性だからという理由で優遇されたことによるものではない。むしろ、実力と実績によってジェンダーに由来する旧来の不利な環境を乗り越え、その進路を切り開いていったものと認められる。
今後女性検事が一層活躍できるようにするためには、女性検事にも働きやすい職場環境を実現していく必要がある。こうした観点も踏まえ、検事の異動等人事制度について改革が望まれることに関しては既に別のところで述べた(詳しくはコラム#13参照)。
現在様々な場面でしばしば「女性初の」というような表現が用いられているのは、それがジェンダー平等の進捗を示す上で大きな意味があると考えられているからであろう。
しかし、将来ジェンダー平等が実現されて、女性の進出や活躍が当然視されるような時代になれば、そのような表現は次第に用いられなくなっていくのではないかと思う。
現に、例えば、検事出身の赤根智子国際刑事裁判所長は、世界にあまねく法の支配を実現するため、国際的には厳しい立場に置かれながらも毅然としてその職務を遂行している。かつて一緒に働いた者として誠に誇らしいが、それは、赤根氏がジェンダーを超えて法律家として尊敬に値するからなのである。
なお、私は弁護士の世界について多くを語るだけの知識を持ち合わせていない。
ちなみに、現在所属している渥美坂井法律事務所は、所属弁護士等(外国法事務弁護士及び外国弁護士を含む)259名のうちその28%に当たる73名が女性で、卓越した女性弁護士に対する国際的な表彰の受賞が毎年のように相次ぐなど、女性が働きやすい法律事務所として評価されている。