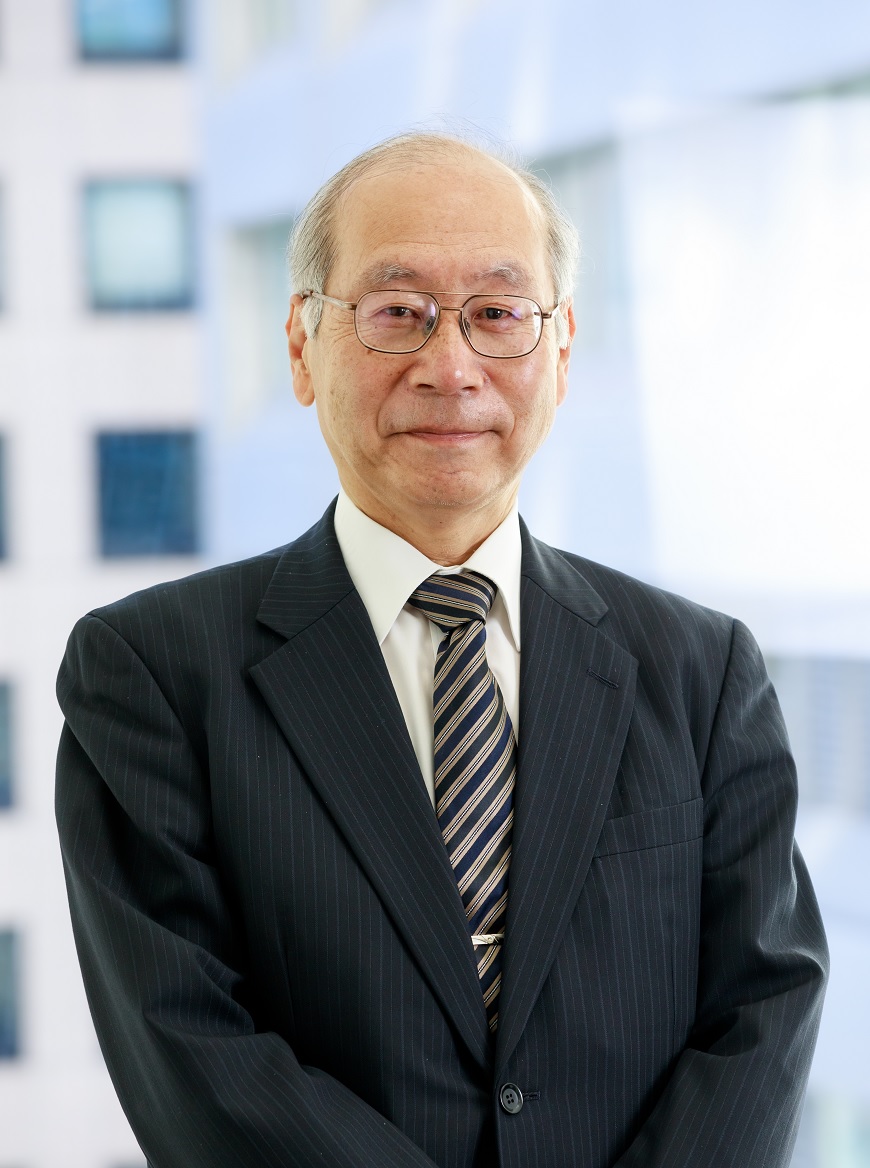[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#15 会計検査院に注目してほしい」:大野恒太郎弁護士(顧問)
会計検査院に注目してほしい
―税金の行方と財政健全化―
私は、2017年7月から2023年3月まで5年余り会計検査院に設けられた会計検査懇話会の委員を務めた。会計検査院は、国の財政等を監視する重要な機関であるにもかかわらず、その活動状況については必ずしも十分に知られているとは言えない、そこで、今回は、私の乏しい経験を通じ、会計検査院が果たしている役割について紹介したい。
会計検査院と会計検査懇話会
会計検査院は、憲法にその設置根拠がある。
国の財政については、財務省が予算の策定や執行の過程全体に関わっているのであるが、同省は政府部内における直接の当事者である上、責任内閣制の下で政治のコントロールに服さなければならない。そこで、予算の策定や執行から切り離され、政治からも独立した中立的客観的な立場で、いわば一般納税者の視点から、財政の在り方を検査する機関として会計検査院が置かれているのである。
もっとも「会計検査院」というネーミング自体にややミスリーディングなところがある。「会計」という語からは、帳簿の記載の仕方などの技術的なイメージを思い浮かべがちであるが、会計検査院の検査はそれにとどまるものではない。
会計検査院は、国の収入支出決算等をその正確性、合規性、経済性(より少ない費用で実施できないか等)、効率性(より大きな成果を得られないか等)、有効性(所期の目的や効果を達成しているか等)等について検査するもので、特に経済性、効率性、有効性の観点からは関係する行政の執行の在り方にも検査が及ぶ。そして、法令に違反しあるいは不当であると認める事項や、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項については、当該省庁等に対し、その旨の意見を表示し、あるいは是正改善の処置等を要求することができるとされている。
また、省庁別の検査結果とは別に、会計検査院が特に必要であると認めた特定のテーマに関する検査の結果については、「特定検査状況」として検査報告中に記載し、そこで会計検査院の「所見」という形でその意見や今後の検査方針が表明されている。したがって、関係する省庁等は、こうした所見を踏まえて適切に対応することが求められ、仮にこれを怠れば、いずれ会計検査院から不当事項等として指摘を受けることになりかねないのである。
なお、会計検査は、私が長く身を置いてきた検察の捜査と一部に共通する点がある。すなわち、いずれも事後的なチェックである点や、証拠に基づく認定が求められている点、外部の勢力に忖度することなく、いわば憎まれ役を買ってでもその役割を果たすべき点等において、両者には相通じるところがある。
もとより、会計検査は、捜査とは異なり関係者の身柄拘束や関係先の捜索、証拠物の差押えのような強制力を伴うものではない。しかし、会計検査院の権能に対応して、検査の対象となる機関は、会計検査院の求めを受けた場合には、資料・報告を提出しあるいは質問に応じるなどの法的義務を負っている。
また、会計検査は、捜査のように個人の刑事責任の有無の認定という点にフォーカスするのではなく、より広く経費執行の適否をチェックし、それによって関係行政機関等に適切な対応を促す役割を有している。
ところで、私が所属した会計検査懇話会は会計検査院幹部と有識者委員7名から成る。私が委員をしていた当時は、牛尾治朗座長(2020.3まで)、三村明夫座長をはじめとする企業経営者、学者、エコノミスト、ジャーナリスト等の錚々たるメンバーによって構成されていた。
そのような中で、財政については全くの門外漢である私が委員を仰せつかったのは、検査される側の省庁出身者であるとともに、検査と一脈通じるところのある検察に所属していたことによるものと推測している。
懇話会は毎年2回、6月と12月に開催され、そこでの意見交換は、会計検査院のその後の業務遂行の参考にされる。6月のセッションは、特定のテーマを取扱い、私の在任中は、公共事業、IT/DX等が採り上げられた。これに対し、12月のセッションは、前月内閣を通じて国会に提出された最新の決算検査報告を中心に意見交換が行われた。
税金の行方のチェック ―コロナ禍対応を中心に―
私が委員をしていた期間の相当部分は、我が国がコロナ禍への対応に追われていた時期と重なった。
その間コロナ禍に対応するために特別な予算が組まれ、執行された。このような緊急事態に対しては、平時とは自ずと異なる対応が求められるのであるが、そうした中で、平時にも増して国費の無駄遣い等が明らかになり、我が国の財政や行政の抱える問題が露呈したように思う。
そこで、本稿では、コロナ禍対応を中心に、私の感想も交えながら、会計検査院の検査によって明らかにされたことついて紹介することとしたい。
まず、コロナ禍に対応する予算措置の枠組みについて述べる。
コロナ禍に対しては、当初予算に加え、累次の補正予算が組まれ、さらに予備費が活用された。それは、2019年度から2021年度までの3年間を見ても合計114兆円を超える膨大な額に達する。
そして、これはコロナ禍に限ったことではないが、当初予算については、財政健全化の観点から個々の予算の要否についてかなり厳格に吟味されるのに対し、補正予算については、緊急に対処する必要があるとの観点から、編成作業においても国会審議においてもこの点の吟味が必ずしも十分には行われず、むしろ時には政治的な配慮から予算額の大きさをアピールする傾向すらあると言われる。
さらに、コロナ禍をめぐる事態は極めて流動的で、これを事前に正確に予測することが困難であったため、予算中にこれまでに例のない巨額の予備費が計上され、その機動的な執行によって対応することとされた。予備費の具体的な使用は行政側に委ねられるので、その適否は、事後的に会計検査院の検査やそれを受けた国会での決算審査においてチェックされることになった。
実際の執行は、当初予算、補正予算に加え、予備費の中から使用決定により配賦された額も合わせて一体的に行われる。会計検査はこれらを一体として見ることによって、そのような予算の策定や執行が適切であったかどうかについて事後的な検討を加えるのである。もっとも、執行段階ではこれらが渾然一体となるため、会計検査において予備費や補正予算のみを切り離してその執行の適否を判断することができないという制約がある。
会計検査の結果、2021年度末においてなお13兆円近い額が翌年度に繰り越され、不用額は3か年を通じて5兆円近い額に達することが明らかになった。繰越は、補正予算の成立時期等からやむを得ないところがあり、また、予算の費消を優先して無駄な支出を行うべきでないことも言うまでもない。
しかし、予算策定やその執行の在り方は、国民負担や財政の健全性にも関わることであるので、会計検査のデータをもとに、こうした予算の在り方について十分な議論がなされることが望ましい。
しかも、必要以上に膨らんだ予算は、放漫で不適切な執行を生む素地ともなりかねない。そして、実際に、会計検査の結果、コロナ関連の予算執行の中には、納税者の目から見て到底許容できないようなものが相当含まれていることが明らかになった。
ここでは、そうした例の一つとして問題性が明らかな雇用調整助成金・休業支援金の不正受給について見てみよう。
雇用調整助成金は、事業主が従業員に対して支払った休業手当を国が補填するものであるのに対し、休業支援金は、休業手当を受け取れない従業員に対して国が直接支払うものであり、これらの総支給額は5兆円を超える。これらは、コロナ禍による休業という緊急事態にかんがみ、制度上支援前の審査を緩くせざるを得なかったため、労働局の事後確認によって必要な是正を図ることとされた。
ところが、会計検査院の検査により、制度上はあり得ない雇用調整助成金と休業支援金の重複支給等の不正受給が横行していることや、それに対する労働局側の事後確認が極めて不十分であることが判明した。そこで、会計検査院は、2020年度の決算検査報告においてこの点について「特定検査状況」中に掲記し、続く2021年度決算検査報告では、厚労省に対して重複支給等の有無や、リスクの所在等に留意して実地調査の対象とする事業主の範囲を設定するなど実効性のある事後確認を行うこと等を「処置要求事項」として指摘した。
これを受け、労働局の側で行った調査や受給者の側からの自主的な申出により、膨大な数の不正受給が判明し、これらについては、基本的に返還の措置が講じられたとのことである。
同じような不正受給ないし過大交付は、会計検査の結果、持続化給付金事業、病床確保事業、Go Toトラベル事業等コロナ対策関係経費の執行においても明らかにされた。そして、これらについては、会計検査院から所管省庁に対してその返還をさせる改善処置をとることが要求された。
なお、個別の不正請求が犯罪に該当するような悪質な場合には、刑事捜査や裁判の対象となり、現に処罰を受けた事例も少なくない。刑事訴訟法には公務員の告発義務が定められており、これは会計検査院職員にも適用されるので、極めて悪質なケースにおいてはその活用も考慮すべきであろう。
我が国のような申告納税制度の下においては、行政や財政に対する信頼感がなければ正しい納税を期待することはできない。こうした不正受給や過大交付のケースのように国費が無駄遣いされている事態は、一般の市民の納税意欲を著しく損なうものである。
また、コロナ禍という緊急事態に対応するという事情があったとはいえ、国費の放漫な支出は、ただでさえ深刻な状況に置かれた我が国の財政を不必要に悪化させ、財政規律の弛緩を招くものと言わなければならない。
さらに、コロナ対応は、端無くも我が国の行政の非効率を明らかにすることとなった。
そうした一例として、私自身の経験について述べることとしたい。それは、コロナ罹患時の保健所からの連絡に関するものである。
私は、コロナがいわゆる2類相当の新型インフルエンザ等感染症とされていた当時、体調不良を覚え、かかりつけ医に診てもらったところ、果たしてコロナに感染していることが判明し、自宅療養に入った。すると程なく地元の保健所から電話があり、かかりつけ医からの報告に基づき、自治体として必要な支援を行いたいとのことであった。そうした電話は、コロナに罹患した患者にとっては心強い行政の対応であった。
ところが、その電話では、まず私の身上を確認する必要があるとのことで、私の氏名の表記について質問されたのである。「大野」はありふれた苗字なので何の問題もなかったが、問題は「恒太郎」の「恒」であった。私が「つねとも読む恒です」と言っても通じないので、「立心偏の恒です。」と答えると、今度は「りっしんべんってどんな偏でしたっけ」と聞かれ、「真ん中に縦棒があり、その両側に点があります」とか、果ては「小と言う字の縦棒を長く伸ばした形です」などというやり取りを繰り返し、ようやく理解を得られたと思われるまでには、かなりの時間を要した。もし私の名が更に複雑な漢字であったとすれば、一層長時間を要したであろうことは想像に難くない。当時保健所の業務がコロナ対応に追われパンク状態であると報道されていたが、氏名の特定にすらこのように手間取っていたのであれば、それも無理のないことと思われた。
しかし、このような非効率は、マイナンバーの活用など行政のデジタル化を進めれば、一挙に片付くはずである。それは、デジタル化の進行した他国の例を見れば、一目瞭然である。
先程述べた不正受給等を行政側が事前に防止できず、事後的にも有効なチェックができなかったことの理由としてしばしば人手不足が挙げられていた。しかしながら、マイナンバー等を活用し、関係するデータを自動的に突合できていれば、さして人手をかけずに問題を解決できたはずである。
このようにコロナ禍対応で露呈した我が国行政の非効率は、税金を効率的に使用し、行政サービスの質とスピードを上げるためにはデジタル化の推進が不可欠であることを端的に示すことになった。もとより、そのことはコロナ対応に限られるものではない。
しかも、最近はAIも実用化されているので、その活用は更に一層行政の効率化、市民の側からみれば利便性の向上に資するものと思う。
その一方で、折角デジタル化のスキームを作り、相当の予算を投入しながらも、実際にはそうしたシステムが活用されぬままに終わっているケースもある。
これは、コロナ関係ではないが、生活保護業務における情報提供ネットワークシステムに関し、会計検査院が厚労省に対して行った処置要求においては、多額の国庫補助金を投じて関係行政機関の間で必要な情報交換を行い得る体制を整備したにもかかわらず、実際にはこのシステムが多くの都道府県において全く活用されていなかったことが指摘されている。
こうしたシステムが活用されないことは、単にシステム整備に投じられた公費が無駄になっているというにとどまらず、デジタル化のメリットが認識されず、そのことがまたデジタル化の遅れの原因となるという悪循環に繋がっているように思う。
なお、会計検査院が国会からの要請を受けて検査を行うこともある。
私が委員をしていた当時の例として、いわゆる森友学園問題につき2017年参議院からの要請を受け、同学園に対する国有地の売却が国庫に損害を与えるものであったか否かにつき調査を行い、その結果を国会に報告したことがあった。
この件については、刑事告訴も行われ、同学園の理事長夫妻に対して有罪判決が下されるなどしている。しかし、刑事手続は、専ら個人の刑事責任の有無について行われるものであり、一旦捜査が開始されると、社会の関心もそちらの方面に流され、行政として改めるべき点についての議論がともすればなおざりにされるきらいがないとは言えない。
これに対し、会計検査院は、国有地売却の際に約8億円の値引きの理由とされた地中のゴミの量の推計について一部の行政文書が廃棄されているためそれが正当であると認めるに足りる根拠を確認できなかったなどとした上で、売却に関係した財務省と国交省に対しては文書管理の改善を求めるなどの所見を明らかにし、今後こうした事態を生じさせないようにするための提言をしている。
財政健全化を考えるよすが
そのため、税金等の歳入ではそれだけの支出を到底賄えないことから、国債発行という借入れに頼った予算編成が続いた。その結果、国債発行残高は著しく膨張し、今や我が国は先進国の中で最悪の財政状況に陥っている。そして、その返済負担は少子高齢化で労働人口が著しく減少する次の世代に先送りされ、財政の持続可能性について懸念を抱かせるものである。しかも、膨大な国債発行残高は、金利の変動によって我が国の財政を危殆に追い込むリスクをはらんでいる。したがって、財政の持続可能性は、少子高齢化と並んで、我が国が抱える最も深刻で構造的な問題であると言わなければならない。
財務省も財政健全化のために様々な取組みを重ねているが、時にそれがあたかも国民を軽視して省益のために行われているような非難を浴びることがある。
他国を見ると、検討のベースとなる数字が政治的な考慮によって左右されないように、政治から独立した財政推計機関が見通しを示す制度が設けられている国がある。そして、我が国においても同様の制度を採用すべきであるとの意見もある。
そうした制度論については、今後国会を含む各方面における議論を待つこととしたいが、現状においては、そのような役割を果たしうる独立性のある国家機関は会計検査院しかない。
会計検査院に注目してほしい