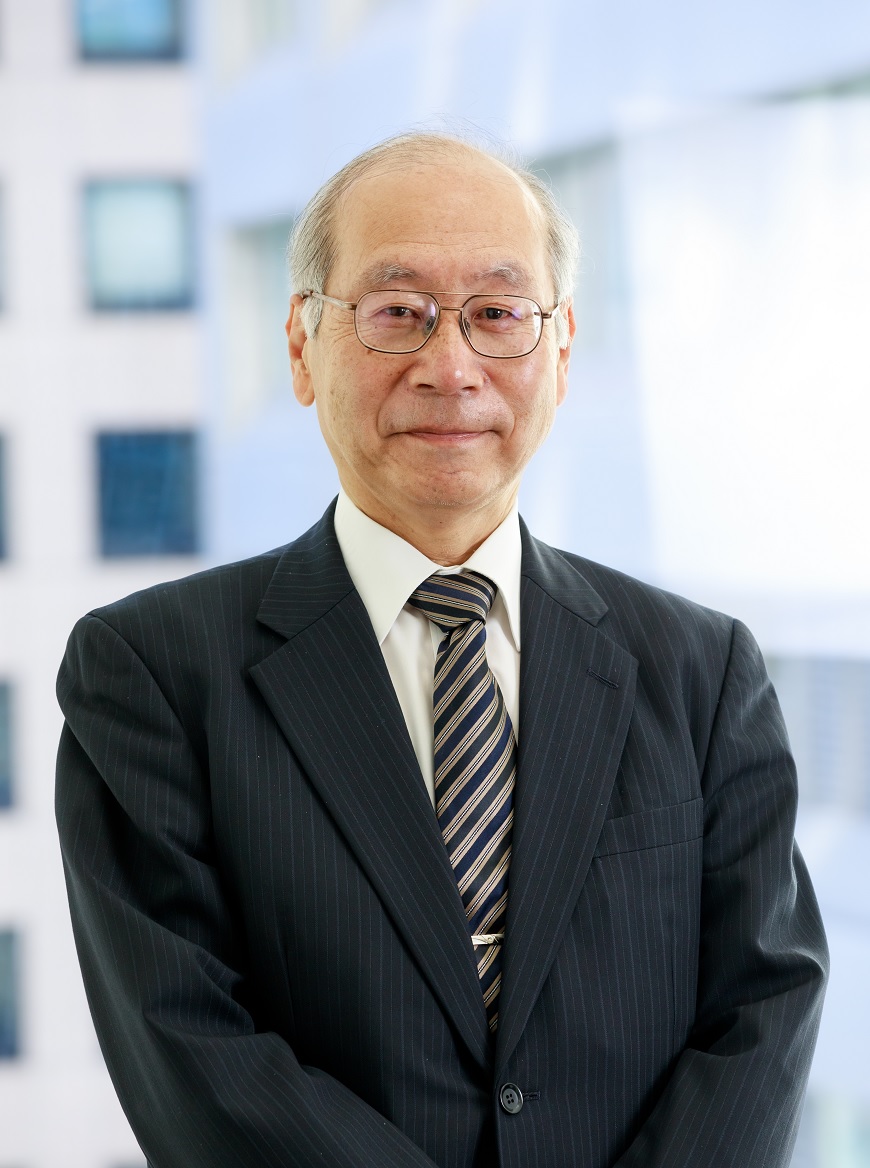[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#11 日本版司法取引」:大野恒太郎弁護士(顧問)
日本版司法取引
―引き込みの危険への対応―
本稿では、我が国に導入された司法取引制度(導入の経緯は#10「司法取引の導入」参照)がどのようなものであるのか、また、懸念される「引き込みの危険」への備えは十分かなどについて概観することにしたい。
司法取引の上に特に「日本版」の語を加えたのは、この制度が日本独自のものであり、諸外国のものとは大きく異なる点があるからである。
捜査協力型
第一に挙げなければならない点は、導入された司法取引は、「他人の刑事事件の捜査に協力する」という型のものに限られるということである。したがって、英米で認められているような「自分の事件について罪を認める」という型の取引(自己負罪型または自白型)は含まれない。
日本が司法取引を「他人の刑事事件の捜査に協力する」というタイプに限定したのは、そうした事件に対する捜査に協力を得る点に制度導入の必要性が最も高く、国民の理解も得やすいと考えられたからである。
これに対し、英米では、自分だけが関わる事件であっても、取引が可能であり、罪を認めれば処分を軽くするという自己負罪型の制度も広く活用されている。
先般報道により注目を集めたプロ野球大谷翔平選手のM通訳は、大谷選手の資金を使い込んだ事件につき、米検察当局と司法取引を行った由である。これは自己負罪型の司法取引で、それにより自分に対する処分の軽減を図ろうとするものであったと思われる。
こうした自己負罪型司法取引を認める理由は、主として刑事司法の効率的運営を図ることにあると理解されている。また、罪を認めれば、そのことを改悛の情を示すものであると評価し、その分責任の軽減を認めるという考え方もあり得るであろう。
しかし、日本では、今回自己負罪型の司法取引は採用されなかった。
その理由は、「罪を犯したのであれば、それを正直に認めるべきである。まず否認しておいて、軽い処分の約束と引き換えに初めて自白するというのはごね得を認めることに通じる。」というような考え方が国民の間になお根強いと思われたことに配慮したものである。
我が国において司法取引が想定される最も典型的な事件は、前回お話ししたように共犯事件である。共犯者の中で、地位の下の者の捜査協力を得ることによって、主犯による指示を含め事件の全貌を明らかにし、主犯の刑事責任を追及しようというのが、その基本的な趣旨である。
もっとも、共犯事件というのは、下の者にとって、他人つまり主犯の事件であるとともに、自分の事件でもある。ここで、他人である主犯の事件について供述するということは、同時に自分の事件について自白することでもあるといういわば両面性を有する。そして、共犯事件については、他人つまり主犯の事件の捜査に協力するという側面をとらえて、司法取引の可能な事件に分類されるのである。
対象犯罪
次に、日本版司法取引においては、その対象犯罪が、組織的に犯されることの多い財政経済犯罪と薬物銃器犯罪に限定されている。
その理由は、これらの犯罪につき制度活用の必要性が特に高く、かつ、制度利用に対する国民の理解を得やすいと考えられたからである。
財政経済犯罪は、企業犯罪とされるものと概ね一致し、具体的には、例えば、脱税、金商法違反(インサイダー取引、虚偽有価証券報告書提出、相場操縦等)、独禁法違反(価格カルテル等)、不正競争防止法違反(外国公務員贈賄、産業スパイ等)等の外、刑法に規定されているものとして、贈収賄・詐欺・横領・背任・文書偽造等が含まれる。
これに対し、例えば、殺人・傷害等の身体犯や強盗罪等は対象犯罪ではない。また、財産犯であっても、窃盗罪等は対象犯罪に含まれない。
さらに、政治資金規正法違反や公職選挙法違反は、組織的に犯されることが多く、しばしば刑事責任が秘書等に押し付けられ、上位の立場にある議員等が不当に罪を免れているのではないかとの疑念を持たれることがあるが、財政経済犯罪等の範疇には含まれないので、現行法の下では対象犯罪ではない。
司法取引の内容
司法取引は、事件関係者側つまり被疑者側と検察官側のそれぞれに一定の行為を義務付けている。
まず、事件関係者側に義務付けられる協力行為としては、取調べにおいて主犯からの指示も含め事実関係を正直に供述すること、それを主犯の裁判においても証言すること、証拠物の提出等がある。証拠物としては、会社の内部書類、メール等の電子データ、録音データなどが典型的なものであろう。
それならば、検察側には何が義務付けられるのか。
事件関係者側の協力行為の見返りに検察側が約束する刑事処分上有利な取り扱いとしては、不起訴や求刑の軽減、略式命令請求のような簡略な手続をとること等がある。その処分がどの程度軽くなるのかは、事件の重大性、捜査協力行為の内容等様々な要素で異なってくる。
不起訴の場合は別にして、求刑の軽減の場合、事件関係者の側にとって、求刑が司法取引をしなかった場合に比べて本当に減らされているのかどうかは必ずしも明らかではない。これは、量刑ガイドラインが明示されている英米とは事情を異にする点である。
そうした状況にかんがみ、検察側としては、事件関係者の捜査協力を得るため、本人やその弁護人に対して具体的に軽減の程度を説明するものと思われる。それでも、事件関係者の側の納得が得られない場合には、司法取引は成立しない。
ところで、事件関係者の側にとって取り分け切実な関心は、逮捕されるのかというような身柄の取扱いであろう。それでは、捜査協力をすれば、逮捕しないとか、検察官が保釈に賛成するというような身柄の取扱いは合意の内容に含まれるのか。
法務当局の見解では、身柄拘束は事件の処分そのものではないという理由で、合意の内容には含まれないとされている。
しかし、理論上これが合意に含まれないとしても、捜査協力を約束し、予定される処分について合意がなされれば、現実には逃亡や証拠隠滅のおそれはなくなるであろう。したがって、司法取引を行うことにより、実際には多くの場合身柄を拘束される事態を避けることができると思われる。
司法取引の手順
まず、その申し込みは、検察側、事件関係者の側のいずれからも可能であり、申し込みを受けて協議が行われる。協議においては、弁護士の関与が不可欠とされている。
協議の過程で、検察側は事件関係者から提供される予定の証拠について事実確認を行う。例えば、弁護人同席の下で関係者本人から供述を聴取して、必要な裏付け捜査を行うことなどがこれに当たる。それにより、その供述内容が真実なのか、司法取引に値するものかどうかが判断される。
こうした協議において検察側を説得して、どの程度処分を軽くさせられるかは、弁護人の力量によるところが大きいであろう。
検察側と事件関係者側との間で合意が成立すれば、その内容を書面で確定する。
合意が成立して書面が作成された後は、合意に基づき、取調べで真実を述べることや証拠物提出、主犯の裁判における証言等の協力行為が行われ、他方で、協力者に対する処分が免除され、あるいは軽減されることになる。
もっとも、司法取引の申し込みを受けて協議が行われたとしても、必ず合意に至るとは限らない。例えば、検察側が事実確認の結果そのような協力行為では司法取引を行うだけの価値がないと考えた場合や、事件関係者の側として提示された処分では納得できない場合等がこれに当たる。
協議が行われたものの合意が成立しなかった場合には、協議の過程で事実確認のために行われた供述は、法律上、その後当人に対しても主犯に対しても基本的に証拠として使えないこととされている。そうでなければ、協議の際に、事件関係者側において協力行為の中身を明らかにすることを躊躇し、円滑に司法取引を進めることができなくなるからである。
裁判所との関係
日本版司法取引は、司法取引という通称にもかかわらず、裁判所は取引の当事者にはならない。
そもそも、今回の制度が、司法取引と広く呼ばれているのは、参考とされた英米における制度が司法取引と呼び慣わされてきたからである。もっとも、英米における司法取引で最も多く用いられているのは、日本では認められていない前述の自己負罪型である。そして、英米では、取引の結果裁判で有罪の答弁が行われると、裁判所は原則としてそれに拘束され、証拠調を経ることなく、有罪を前提とした量刑手続に入ることになる。こうした英米における制度は答弁取引Plea Bargainingと呼ばれ、それが司法取引とも訳されたのである。このような英米流の答弁取引に対しては、我が国の刑事司法が拠って立つ実体的真実主義の原則とは相容れないとの批判が強い(コラム#10参照)。
これに対し、日本版司法取引は、捜査協力型に限られ、またその合意内容は取引の当事者ではない裁判所を拘束するものではない。
そもそも我が国においては、被告人が冒頭手続において起訴事実を全面的に認めたとしても証拠調が省略されることはなく、裁判所はあくまでも証拠調の結果に基づいて事実を認定することとされている。
そうすると、そのような日本の制度の下において、事件関係者が検察官との間で司法取引を行ったとしても、裁判所がそれとは異なる処分を行い得ることとなり、司法取引は当てにならないのではないかという疑問を生じる。
こうした観点から、不起訴や求刑について検討してみよう。
まず、不起訴であるが、裁判所は基本的に検察官が不起訴にした事件を裁くことはできない。
しかし、検察審査会が不起訴処分に対する審査の結果、起訴相当あるいは不起訴不当を議決することはあり得、その場合には、司法取引(合意)は失効することとされている(刑訴法350条の11)。もっとも、再捜査の結果、起訴されるケースや、いわゆる強制起訴に至るケースは実際上稀であると思われる。
次に、求刑についても、裁判所が検察官の求刑を超えた量刑の判決を下すことは、実務上稀であろう。
そして、仮にそのような判決が出されれば、司法取引の当事者である被告人は司法取引(合意)から離脱することができると定められている(同350条の10第1項)。また、検察官としても司法取引を踏まえその量刑が重過ぎるとして上訴することが考えられる。
いずれにしても、こうした裁判所の関与の程度にかんがみると、司法取引という用語は、正確ではないばかりか、むしろ誤解を招く余地がある。しかも、取引の語は、厳格であるべき司法には相応しくないいささかダーティーな語感を伴わないでもない。
今回設けられた制度は、正式には、法文の記載に則って「協議合意制度」と呼ぶこととされている。
それにもかかわらず、私が本稿等で敢えて「司法取引」の語を用いているのは、そうした用語が既に社会的に一般化していることを前提に、それがどういうものなのかを説明しようと考えたからである。
引き込みの危険対策
ここで、司法取引制度に対して寄せられる懸念について検討したい。
司法取引は事実を曲げ罪なき者に濡れ衣を着せるおそれはないのか。言い換えれば、「犯罪者が自分に有利な処分を得たいために、虚偽の供述をして他人を主犯に仕立て、引き込む恐れがあるのではないか。」という問題である。これは、「引き込みの危険」として立法段階で最も議論された点であり、実際に司法取引が用いられた事件においてもしばしば争われている。
この点に関連し、従来、判例では、有利な取扱いを約束することによって得られた自白は、その任意性に疑いがあることを理由に、証拠とされないこととされていた(最高裁1966(昭和41)年7月1日判決参照)。
この事件は、約束によって自白をした本人を被告人とするもので、しかも、検察側がその約束に反して起訴をしたという事件であり、捜査協力型の司法取引に直ちに当てはまるものではない。
しかし、この判例がおよそ約束による自白には虚偽が入り込む恐れがあることを含意していると解釈すれば、司法取引による証言についても同様の懸念を生じ得る。
そこで、今回の制度では、虚偽が入り込むことのないよう、司法取引の手続や要件を明確に法律で定め、そうした懸念を払しょくする手当がなされている。
まず、司法取引にはその被疑者の弁護人が関与しなければならないとされている。弁護人の関与により、被疑者が心理的圧迫によって虚偽供述をすることを防ごうとするものである。
ここで、弁護人とは、司法取引をする事件関係者の弁護人であって、司法取引によって得られた証拠で訴追されることになる主犯の弁護人ではない。けれども、司法取引をする事件関係者の弁護人であっても、その者が虚偽供述をすれば以下に述べるように虚偽供述罪等で処罰されるおそれがあることや、弁護士の職業倫理も踏まえ、そのようなことのないように注意することを期待し得る。
次に、検察官としても、取引をするに当たっては、得られる供述について、それが真実であるか、裏付け証拠があるかどうかを協議の過程で確認する。そして、裏付けが得られず、主犯の犯罪の立証ができないような場合には、司法取引には応じないものと思われる。
これに加え、検察は、引き込みによる冤罪が発生しないよう、司法取引の運用を当面各検察官や地検任せとせず、高検や最高検の了解を求めているとのことである。したがって、少なくとも制度が定着するまでは、極めて慎重な組織的チェックが行われる見通しである。
さらに、司法取引に基づく証言等の証拠調が行われる主犯の裁判においては、検察官に合意内容書面の証拠請求が義務付けられており、司法取引の事実は主犯の側や裁判所に明らかにされる。したがって、取引に基づいてなされる証言は、取引の経過を含め、その信用性について、引き込みの危険がないのか、反対尋問等を通じて慎重に吟味されることになる。
最後に、司法取引の合意に違反してなされた虚偽供述や虚偽証拠の提出は、5年以下の懲役に当たる独立の犯罪とされた。これまで、捜査機関に対する虚偽供述は直ちに証拠偽造罪等に該当しないとされ、かりにそれが同罪に当たる場合であっても、その法定刑は懲役3年以下であるから、司法取引の合意に反して行われた虚偽供述等に対してはかなり重い刑罰が規定されたことになる。
したがって、いかに軽い処分を得たくても、虚偽の供述をすれば、かえって重い処罰が付け加わることになるので、そうした行為への抑止効果があると考えられる。
これらの方策により、引き込みの危険を防止するために十分な制度的手当がなされているのである。