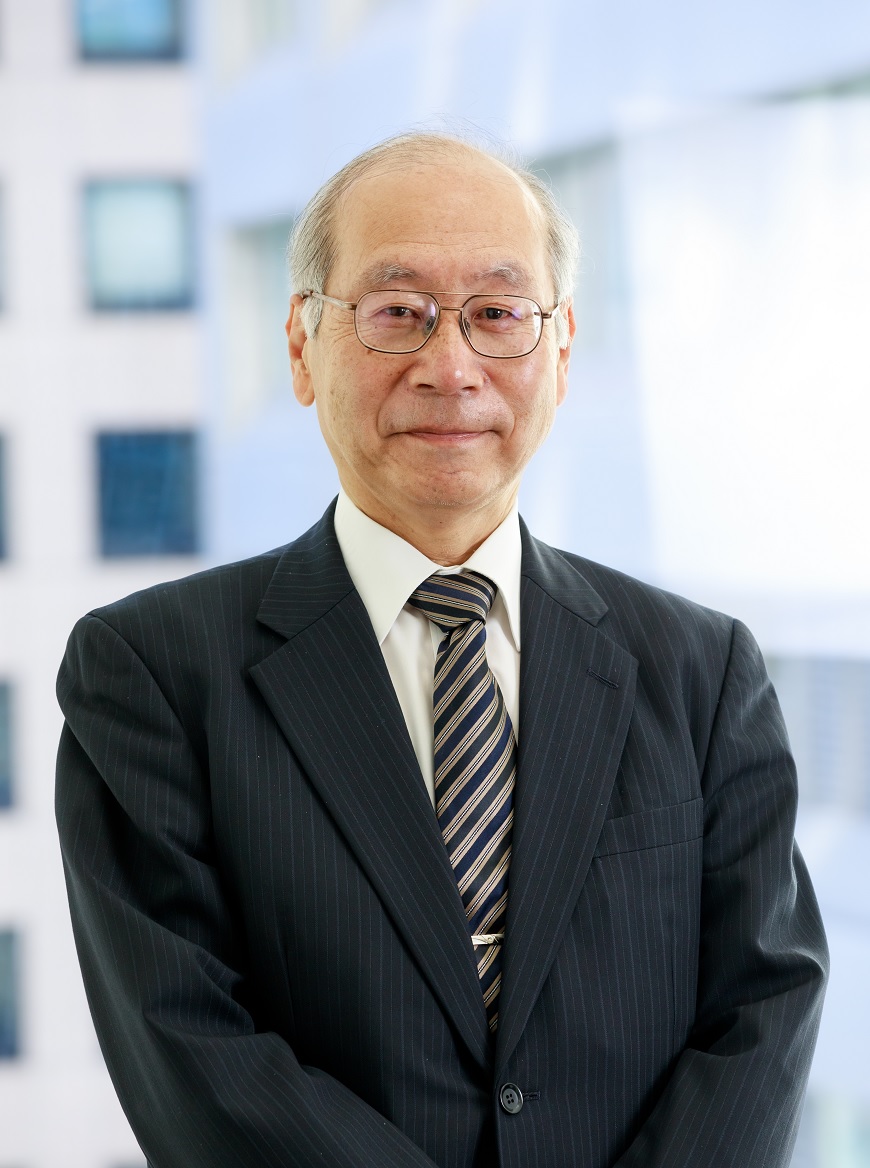[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#07 司法制度改革の立役者」:大野恒太郎弁護士(顧問)
司法制度改革の立役者
―山崎潮さんの思い出―
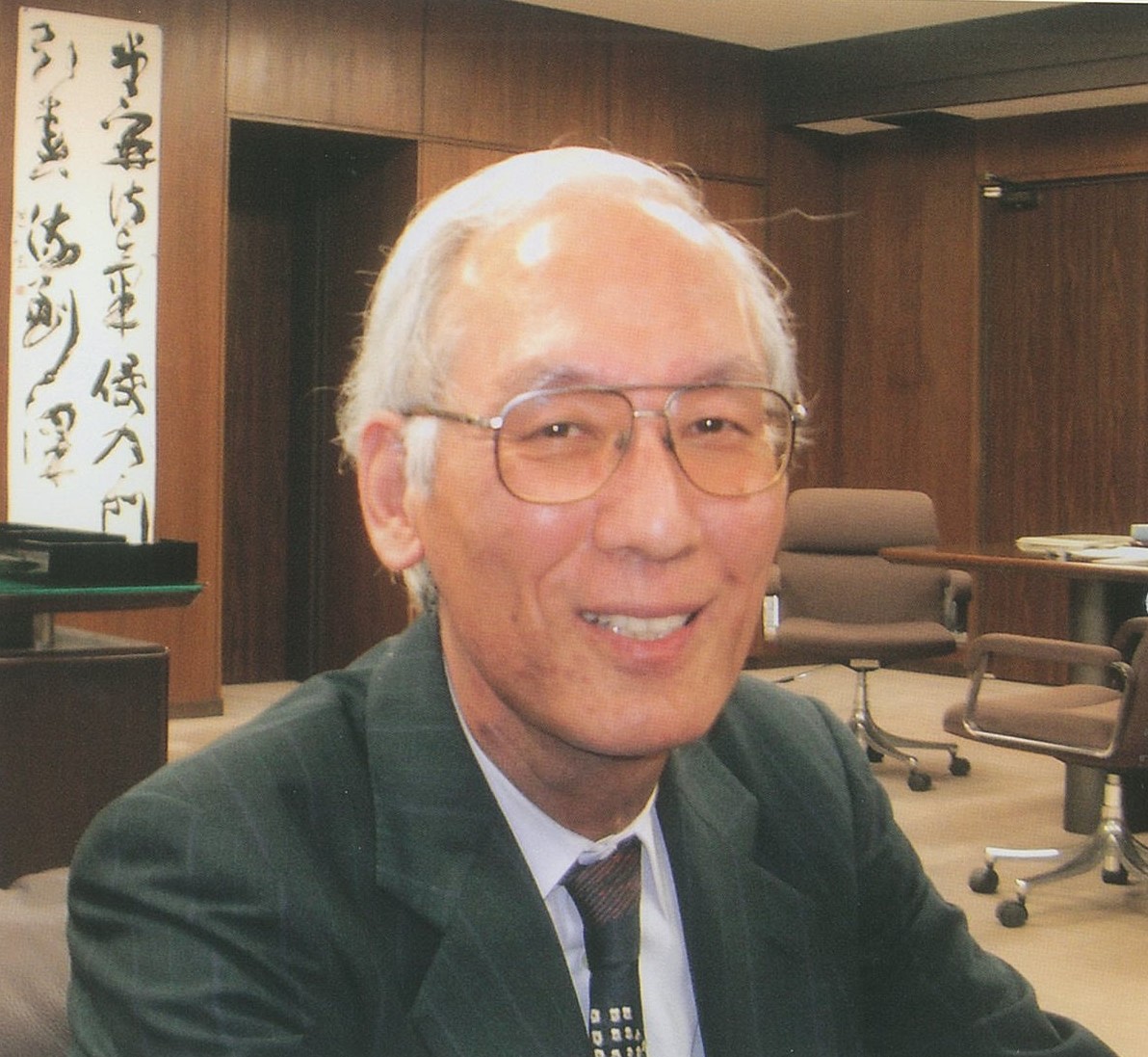
在りし日の山崎さん
(平成19年4月6日「山崎潮さんを偲ぶ会」冊子から)
司法制度改革から20年が経過した。この改革は、戦後半世紀余り大きな変革もないまま推移してきた我が国の司法制度をその利用者である国民の視点に立って抜本的に改めるものであった。それにより、裁判員制度、法科大学院制度、日本司法支援センター(法テラス)の創設をはじめ、司法全般にわたる改革が行われた。
山崎潮さんは、内閣司法制度改革推進本部(以下、推進本部ということがある。)事務局長として、司法制度改革の実現に獅子奮迅の活躍をし、推進本部担当分だけでも17本の関係法律を成立させるという歴史的な業績を上げたのであるが、その1年半後に亡くなった。
私は事務局次長として直接山崎さんの指導を受け、その超人的な活躍を目の当たりにし、我が国司法にこのように立派な人物がいたことを誇らしく思う。
そこで、山崎さんがこの大改革にいかに大きな貢献をしたのか、またいかに魅力あふれる人物であったかを是非皆さんにお伝えしたいと思い、本稿を記すものである(文中敬称等略)。
司法制度改革の経緯と山崎さんの事務局長就任
山崎さんは、1970年に任官した裁判官であり(司法修習22期)、84年に法務省に異動し、数々の重要な民事関係立法を担当するなどした上、法務省民事局長に在任していた2001年、内閣司法制度改革推進本部の事務局長に任命された。
ところで、どのような法制度であっても、社会情勢の変化に対応するため、適時適切に立法によって必要な手直しを行わなければならないことは言うまでもない。
しかしながら、司法関係の法案については、1964年の臨時司法制度調査会意見書の提言が日弁連の強い反対により実現されなかった後、1970年には参議院法務委員会において「今後司法制度の改正に当たっては法曹三者の意見を一致させて実施するよう努めなければならない。」との付帯決議がなされ、司法制度の改正は法曹三者協議という枠組みで行われることとされた。そのため、法曹人口の増加をはじめ様々な懸案については、社会経済的な重要性にもかかわらず、三者の合意が得られなかったことから、立法的な対応がなされないまま長期間が経過していた。
その結果、「二割司法」などと揶揄されたように、我が国の経済社会における司法のプレゼンスは低く、利用者である国民のニーズに対して十分に応えているとは到底言えない状況にあった。
ところが、我が国の経済社会がバブル崩壊等で行き詰まりを見せると、行政主導の事前規制調整型から民間の活力がより発揮されるよう事後監視救済型に移行する必要があるとの声が高まり、1990年代に行政改革等が行われた。そうした中、司法についても、社会のセーフティネットとしてその機能を強化する必要があるとの主張が各方面からなされるようになった。
そのような流れを受け、1999年内閣に司法制度改革審議会が設置された。この審議会は、司法制度改革は司法の利用者である国民の視点から議論されるべきであるとの考え方に立ち、法曹ではない委員が大多数を占めるものであった。そして、2001年公表されたその意見書において、裁判員制度や法科大学院の創設をはじめとする司法制度のドラスティックな改革が提言されたのである。
政府は、この意見書を受け、それを最大限尊重した司法制度改革を実現すべく、内閣に小泉純一郎総理を本部長とする司法制度改革推進本部を設置し、その事務局長として、山崎さんに白羽の矢を立てた。
司法制度改革審議会意見書は、司法利用者の視点から作成されたことから、それまでの司法実務からは大きく踏み出すものであった。したがって、例えば、相当数の弁護士が法曹人口増に反対し、裁判所や検察には裁判員制度に反発をする者も少なくなかった。つまり、それぞれ異なった点についてではあったが、法曹界においては、司法制度改革に対して半信半疑あるいは冷ややかな見方が根強かった。
しかも、審議会において意見がまとまらなかった点(例えば、裁判員の人数。本コラム#02参照)はその対立がそのまま立案段階に先送りされており、そこを解決しなければ法案作成に漕ぎつけることはできなかったのである。
こうした状況の下で、改革の実務責任者である推進本部事務局長のポストに就くことは、火中の栗を拾うようなもので、あまりにも困難やリスクが大きく、大方の者であれば尻込みをしたのではないかと思われる。
しかし、山崎さんは、これを敢然と引き受けた。2001年12月のことである。それは、山崎さんの類い稀な、前向きで肚の座った生き方によるものであると思う。
山崎さんは、就任当時の心境について、2004年11月衆議院法務委員会における最後の答弁の機会に、「司法制度改革審議会の意見書を読んで、こんなすごいことを何で3年間でできるんだと、目がかすむ思いでした。司法のあらゆる分野にわたり、国民生活に大きな影響を与えるものが多々含まれ、制度というより、文化を変えるようなものもあったからです。こんなに大切なことを本当にできるかな、しかしやらざるを得ない。」と述懐している。
山崎さんが、我が国の司法の歴史の中でもほとんど前例のない大きな課題にその責任者として直面した際に感じたプレッシャーと、それにひるまず立ち向かっていこうとする元大学陸上選手らしい心意気が伝わってくるように思う。
山崎さんの仕事ぶりと人となり
私は、法務検察出身の事務局次長として、弁護士出身と財務省出身である他の二人の事務局次長と共に、山崎さんの下で働いた。
山崎さんは長く法務省の民事局等で民事立法の業務に従事されていたが、それまで私とは直接の接点はなかった。
私は、最初に、山崎さんの国会関係挨拶回りにお供した。その際、山崎さんは、「懲役3年に行ってきます。」と言うことがあった。これは、推進本部の設置期間が司法制度改革推進法によって3年と定められていたことを前提とした発言であった。
また、何人かの国会議員に対しては、「夫婦別姓の時は敵でしたが、司法改革では味方です。」というような挨拶もしていた。この挨拶は、1996年法務省民事局が法制審議会の答申を受けて選択的夫婦別姓の立法を目指しながら、議員筋の反対により法案を提出できなかった経緯を踏まえたものである。
私は、のっけから山崎さんの型にはまらない言動と人をグッと惹き付ける人間的迫力に魅了された。
推進本部事務局は、法曹三者のみならず、各省庁や民間からの出身者を含む最大時60名を超える事務局員から成っていた。山崎さんは、意見書に盛り込まれた改革を何としてでもやり遂げるという強い使命感と強力なリーダーシップにより、寄せ集めの部隊を見事に統率して立案作業を推進した。
その際、特に私達法曹出身者に対しては、国民の視点から司法の在り方全体を改革するという司法制度改革の趣旨に則り、「司法は俎板の上の鯉なのだから、それぞれの出身母体にとらわれることなく、司法制度改革審議会意見書の提言を実現するよう力を合わせよう。」と呼びかけた。
先程も述べた通り、当時の情勢の下において、これは決して容易なことではなかった。
山崎さんのお供をして裁判所を回った際に、幹部裁判官の中には、これまで自分たちが我が国の司法を営々として築き上げてきたのに、部外者による的外れな意見書を真に受けて改悪しようというのかと言わんばかりの否定的な反応を示す人もいた。
私自身も、検察幹部の懇談会に出席した際に、先輩幹部から、「意見書の内容にはとても賛成できない。推進本部事務局次長としての君の役割は、司法制度改革を骨抜きにすることだ。」などと言われたことがある。
さらに、司法制度改革のうち、法曹人口増加や外国法弁護士の位置付け、他の士業との関係等については、特に弁護士会の中で反対の意見が強かった。したがって、そうした状況の下でこれらの案件を担当した弁護士出身の事務局員の苦労も並大抵のものではなかったであろう。
山崎さんは、常に段取りの重要性を強調した。そうでなければ、推進本部顧問会議や11にも上る検討会を運営する一方で、法曹三者をはじめとする関係機関、政党等との調整をしながら立案を行うという事務局の膨大で複雑な業務は進まない。手順を間違えたために関係方面に反発されてしまったのでは、法案の内容がどのように良くても、それを成立させることなど期待できないのである。
もっとも、実際には、想定したように作業は運ばず、綱渡りの連続であった。法科大学院法の時は、法案が間に合わず次官会議を1日2回も開いてもらったことがあり、「こんな禁じ手は二度と使えない。」などと言い合った。
ところが、その後、立法が輻輳すると、ますます何でもありの様相を呈するようになり、裁判員法の時に至っては、自民党裁判員小委員会、与党調整、自民党総務会のすべてが紛糾し、これらの関門を突破したのはそれぞれ期限ギリギリのタイミングであった。最後に司法修習生の修習資金を貸与制に改める裁判所法の一部改正が成立したのは、推進本部解散後の臨時国会最終日であった。
山崎さんは、事務局員に対しては、「どうせやらなきゃならない仕事なら、明るく楽しくやろう。」を合言葉にしていた。お酒はほとんど飲まなかったが、末端の係員にも親しく声を掛けた。時として部下を叱ることがあっても、表裏がなく竹を割ったようなカラリとした性格故、嫌味や後に引きずるようなところがなかった。
そして、「昔は体育会系だった。」と言いながらも、ご自分の揮毫を表装した掛け軸を局長室にかけ(冒頭写真参照)、麻雀や競馬等の賭け事には絶対の自信を持っていた。私達事務局員は、時にそうした山崎さんを冷やかしながら、その明るく豊かな人柄に魅了されていた。
司法以外の分野出身の事務局員から、「山崎局長が裁判官だというのは本当なんですか。」と真顔で尋ねられたこともある。実は山崎さん本人もこの点を相当気にしており、折に触れてご自分が裁判所出身であることを強調していた。しかし、その開けっぴろげで人間味あふれる人柄は、世間一般が裁判官に対して有する謹厳なイメージとはかなり異なるというのが、大方の意見であったように思う。
しかし、私達事務局員が山崎さんを尊敬したのは、何よりも、山崎さんが常に自ら先頭に立ち、困難から決して逃げなかったからである。
山崎さんは、顧問会議や検討会への出席や関係機関、政党等との調整に加え、法案の国会審議に際しては、膨大な量の答弁を終始一手に引き受けた。午前中は衆議院で、ある法案の答弁をすれば、午後は参議院で全く別の法案の答弁をする日もあった。推進本部最終年である2004年の国会における推進本部担当法案に対する政府質疑の時間は、衆参法務委を合計すると116時間を超えている。山崎さんの答弁は、普段と同様、常に歯切れ良く、自分の言葉で分かりやすく話し、決して答弁案を棒読みにするようなことはなかった。
それならば答弁案が不要かというとそうではなく、質問数が立て込むなどして答弁案の作成が遅れていることに腹を立てると、「こうなったら答弁案通り読む。もう知らんぞ。」と𠮟ることもあった。部下として「是非そうしてください。」と答えるわけにもいかず、困ってしまったことを思い出す。
山崎さんが国会審議においてもまさに八面六臂の働きをされたからこそ、司法制度改革推進本部が解散する直前、衆議院法務委において、司法制度改革を担当したことに対する所感や今後の改革の在り方についての所見を述べるよう求められたのである。そして、山崎さんは、数分間にわたって先に引用したような発言、というよりも実質的には演説を行い、与野党の議員からその労をねぎらう盛大な拍手を受けた。
これは、政府参考人に対しては極めて異例のことであり、立場の違いを超え、山崎さんがいかに尊敬され、その貢献がいかに高く評価されたかを物語るものである。
司法制度改革の成果
冒頭にも記載した通り、推進本部事務局は、結局、3年間で合計17本の法律を成立させた。その中には、国会審議の便宜上提出法案の数を圧縮するため、一括法形式を採り、一つの法案の中に実質的には複数の法改正を包摂するものも含まれていた。
主要なものを列挙するならば、裁判員法、これと密接な関係を有し、公判前整理手続や被疑者に対する国選弁護制度を創設するなどした刑訴法等改正、法科大学院関係法、司法アクセスを強化するため日本司法支援センター(法テラス)を創設した総合法律支援法、裁判迅速化法、行政訴訟において国民の権利利益のより実効的な救済を可能にした行政事件訴訟法改正、知的財産権をめぐる紛争の解決を促進してその保護を図った知財高裁設置法等、裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)、新仲裁法、個別労働関係事件の簡易迅速な紛争解決を図った労働審判法等がある。これらは、いずれも司法制度改革審議会の意見書の中で提言されたものであり、それぞれの分野において画期的な意義を有し、実務的に大きな影響を有する立法であった。
もとより個々の改革については様々な評価が成り立ち得る。しかし、司法制度改革は、それまで専ら司法の担い手である法曹の観点から議論され、事毎に対立していわばデッドロックに乗り上げた状態で停滞していた司法制度を改め、国民本位の視点に立った立法によって積極的に対応する時代を開くものであった。そうした意味において、司法にとっては、明治における近代的法制の導入、第二次世界大戦後における新憲法体制への転換に続く歴史的な意義を有する改革であったと言えるであろう。
このように重要な法律が多数短期間のうちに成立させることができた理由は、長い間大きな動きのなかった日本の司法をこの機会に思い切って改革しなければならないことが、各界各層の共通認識になっていたという事実があるように思う。すなわち、司法をその利用者である国民にとって「より身近で、速くて頼りがいのある」ものにする司法制度改革の理念については、大方の意見が一致したのである。
また、司法制度改革は、意見書の提言を受けて我が国の法制度・司法制度全体をカバーする、いわば改革のパッケージとして行われたところに大きな特徴がある。
個々の案件ごとには機関や団体によって強い反対が表明されており、賛否が入り組んでいた。しかし、これらをパッケージにすることによって、抵抗を乗り越えて改革を前に進めようという力学ないしモメンタムが働き、それぞれが「俎板の上の鯉」としてその痛みを分かち合わなければならないという気運も醸成されたように思う。
こうした司法制度改革の枠組を外し、個別の制度を別々に採り上げる方法によったのであれば、短期間にこれだけ多岐にわたる法案をまとめ、成立させることは、到底できなかったであろう。
さらに、法曹三者は、それまで司法制度を三者の間のみで議論をし、それぞれの立場にこだわって、ともすれば意見の相違を強調する方向に流れる嫌いがあったことは否定できない。
しかし、法曹三者は、司法の利用者である国民の側から見れば、司法サービスのサプライヤーとして同じ立場に立たされている。その意味で、国民の視点から行われた司法制度改革において、三者はいずれも「俎板の上の鯉」であり、国民からの批判ないし注文を受ける立場にあることに気付かされたのである。
そして、司法制度改革が契機となり、その後、法曹三者の間では、健全な緊張感を伴いながらも、建設的な協働が行われるようになった。
加えて、推進本部事務局における弁護士出身局員の誠実で献身的な活躍も、政府部内における信頼や評価を高め、その後の弁護士出身の任期付き公務員増加に道を開くものであったと思う。
このように、法曹三者の関係が大幅に改善されたことも、司法制度改革の成果として挙げることができると思う。
こうして、私達事務局員にとっては、山崎さんの下で関係各方面とも力を合わせて司法制度改革に関与したことは、それぞれの職業生活の中で格別な位置を占めることとなった。
推進本部は、設置年限を迎えた2004年12月に解散し、山崎さんは裁判所に復帰し、私も検察に戻った。
山崎さんの突然の死
ここで、山崎さんが亡くなったことを話さなければならない。
本部解散から1年半を経過した2006年5月16日、当時最高検総務部長をしていた私は、千葉地検に出張した夜、千葉市内で、千葉地裁所長をしていた山崎さんと千葉地検検事正の3人で会食をした。
山崎さんは、先程も触れた法務委員会における発言の最後を、ユーモアたっぷりに「法務委の厳しい試練に耐えて、私も成長してまいりました。今後は一法律家としてスローライフを送りたい。」などと述べて締めくくっていた。その言葉通り、山崎さんからは推進本部時代とは打って変わってゆとりのある地裁所長生活について愉快な話を聞くことができた。また、山崎さんは、その時点から3年後に施行される裁判員制度が実際にどのように動いていくのか楽しみであり、司法制度改革に対する歴史的な評価はこれからの運用如何にかかっているなどとも述べていた。
推進本部時代はまさに激動で苦労も多かっただけに、話は尽きなかったが、午後9時ころには、店の前でタクシーに乗り込んだ山崎さんを見送って別れた。
ところが、翌日午前、山崎さんに前夜の御礼をするため千葉地裁に電話をしたところ、地裁事務局長から、山崎さんが亡くなったという衝撃的な話を聞かされたのである。朝、所長官舎に迎えの車が着いたが、山崎さんが出てこないので、運転の方が鍵を開けて中に入ったところ、山崎さんが倒れており、救急車を呼んだが、既に亡くなっていたとのことであった。
前の晩、山崎さんは大変元気であった。もともとあまり酒を飲まない方であったから、その時もほとんどアルコールに口を付けなかった。したがって、私は山崎さんが亡くなったとの報せをにわかに信じることができず、言葉を失った。
後日裁判所側から聞いたところでは、死因は心筋梗塞であり、着衣の状況から倒れたのは帰宅して間もないと判断される由であった。そうであれば、お別れして1時間と経たない時のこととなる。
山崎さんは、スポーツマンで活動的であったが、3年間にわたり司法制度改革の実務サイドの責任者として途方もないストレスの下で激務を重ねたことによって、知らず知らずの間に疲労が蓄積していたのではないかと思う。元推進本部事務局員の中には、「山崎さんは戦死ですね。」という者もおり、私自身もそのような印象を禁じえない。
山崎さんが言い遺したことと司法制度改革の理念
山崎さんは、折に触れ、「仏を作るより、仏に魂を入れることの方が難しい。」として、立法化の後の運用において司法制度改革の真価が問われ、国民本位の改革を実現する際の一番のポイントは、プロである法曹の意識改革であるなどと話していた。
また、前述の最終答弁の中で、「(これだけ大きな改革は)とても一発ではいかないので、やり遂げるためには、走り幅跳びではなくて三段跳びで行こうということを考えたのです。そこで、立法作業ではまず70点取ることを目的にしました。」などとも発言している。これを敷衍するならば、改革は当初の立法だけで直ちに実現できるものではなく、立法、運用、手直しの3段階を経てようやく良いものになるので、運用を見た上で再度の改正を行うことを恐れてはならないとの趣旨である。
司法制度改革における立法は、その時点の様々な制約の中で行われたものであり、決して絶対的な解ではない。山崎さんは、他の誰よりもそのことを熟知していた。そうであればこそ、将来改正を重ねることを躊躇してはならないと強調していたのである。
改革から相当期間が経過したことにより、その後の運用や社会経済の進展に対応して、手直しを要する点も数々浮かび上がってきている。山崎さんが言ったように、これらに対して、必要に応じ立法的な手直しを加えていくべきことは当然である。
私達が決して忘れてならないのは、山崎さんが文字通りその生命を捧げた「国民に身近で、迅速で頼りになる司法」を実現するという司法制度改革の理念であり、これに基づいて改革を継続することである。
追記
本文で言及した司法制度改革一括法の中で、いわゆる外弁法が改正され、外国法事務弁護士と日本弁護士との共同事業が認められた。当事務所は、2005年4月同改正法が施行されると同時に、国内系法律事務所としては初めて外国法共同事業を立ち上げた歴史がある。
また、本文中で推進本部に11の検討会が置かれたことについて述べたが、当事務所顧問の高橋宏志名誉教授は、司法アクセス検討会の座長として、法テラスを創設した総合法律支援法の立案等に尽力された。
なお、司法制度改革の全体像については、拙稿「司法制度改革―裁判員制度を中心に―」日本法律家協会「法の支配」136号50ページ以下を参照されたい。