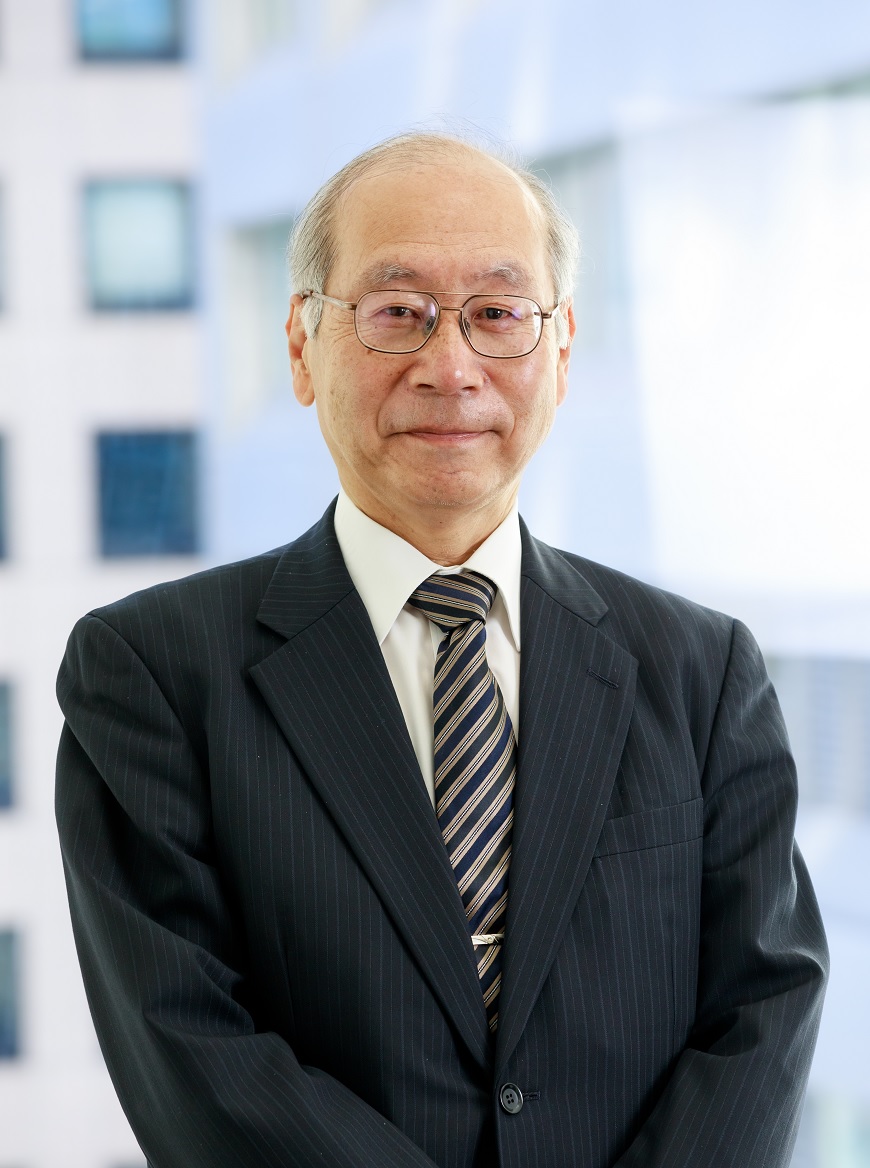[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#08 マダニの恐怖」:大野恒太郎弁護士(顧問)
マダニの恐怖
―山を歩く時にはご用心―

マダニ(兵庫県立人と自然の博物館ブログより)
最近マダニによる被害を報じる報道が目に付く。マダニに咬まれて重篤な症状に陥り、死亡する例も相次いでいるという。その原因は、シカやイノシシ等野生動物の血を吸うマダニが病原体を媒介することにある。
もっとも、多くの人がマダニについて具体的な知識を有しているわけではなく、家屋にも発生するダニと同じようなものだろうなどと誤解をしている場合が少なくない。私達もそうであった。自分達が山でマダニに咬まれるまでは。
本エッセーでは、私と妻がそれぞれ山でマダニにからむ手痛い経験をしたことをお話しする。
私のケース
私は、宇都宮地検に勤務していた年の夏、妻と尾瀬から奥鬼怒に縦走した。2007年に日光国立公園から尾瀬国立公園が分離されたが、私達が歩いたのはそれよりも前のことである。まだ朝日も上らない午前4時尾瀬沼を出発し、延々と連なる尾根歩きの後、天上の楽園のような鬼怒沼を経て奥鬼怒の加仁湯温泉に着いたのは、夕方5時を相当過ぎていた。13時間余り歩き続けたことになる。その間、一人の登山者にも行き会わなかった。
このルートの途中、栃木・福島・群馬三県を分ける地点に黒岩山(標高2163m)という山がある。登山路は山頂を通らず、山腹を巻いている。しかし、この山は栃木百名山にリストアップされており、折角近くまで来たのに登らずに通り過ぎるのは惜しいと考え、私達は、わずかな踏み跡を頼りに、藪を漕いでその山頂を往復した。頂上には小さな表示板があり、高度感があって眺望に恵まれた素晴らしい山であった。しかし、この藪漕ぎが災いをもたらしたのである。
縦走を終えた夜は、加仁湯で、おいしい料理とイワナ骨酒などを楽しんだ上、温泉に浸かり、山歩きの疲れを癒した。
翌朝、宿の車でバス停のある女夫渕温泉まで送ってもらった。
ところが、私は、バスに乗っている最中、左脇腹に違和感を覚えた。シャツをめくって見ると、何と左脇腹に小さな虫らしきものが上半身を没入させており、皮膚上に尻の部分と後ろ足らしきものを突き出しているではないか。あまりにおぞましい姿に、私は驚き、隣に座っていた妻に尻の部分をつまんで引っ張り出すよう頼んだが、うまくいかない。その下半身は取り除いたものの、上半身はそのまま脇腹の皮膚の中に残ってしまった。もっとも、その時点でその虫らしきものが何であるかは分からず、それがそれ以上体内深く入り込むのを阻止できたことをもってひとまず良しとせざるを得なかった。それは、黒岩山の往復で藪漕ぎをした際に食いついた可能性が最も高いと思われたが、前夜温泉に入った時点では全く気付かなかった。
私の体調に異変を生じたのは、翌日昼になってからである。その日も休日で、私は妻と官舎に近い県立博物館に行ったのであるが、強い倦怠感を覚え、妻が展示を見て回っている間、通路の長椅子で横になっていた。37度を超える発熱もあったため、夕食は抜いた。しかし、その時点ではまだ、二日前の強行軍の疲れが残っているのだろうと思っていた。
次の日、妻は東京の自宅に帰り、私は出勤したが、体調は一段と悪化し、悪寒のためほとんど仕事にならない状態に陥ってしまった。こうなると、ただの山の疲れであるとは思えない。思い当たることと言えば、正体不明の虫に食いつかれた左脇腹が赤く腫れ上がっていることであったため、私は宇都宮市内の皮膚科を訪ねた。
医師は、私の話を聞くなり、言下に「それはマダニですね。」と断定した。私の体内に残ったマダニの上半身から拡散した病原体によって惹き起こされた感染症であるという。そして、感染症を治し、重いライム病等を防止するため、5日分の抗生物質を渡されたのである。体内に残ったマダニの上半身はいずれかさぶたとなって自然に剥離するとの説明であった。
当時私は、マダニやライム病について何の知識も持ち合わせていなかった。
そこで、帰宅後、早速インターネットでこれらについて検索してみた。驚いたのは、皮膚に食い入っているマダニの写真である。それは、まさに私が脇腹に見付けた虫らしきものの姿そのものであった。テレビの刑事ドラマなどを見ていると、刑事から犯人の写真を見せられた目撃者が、「この人です!この人が犯人に間違いありません。」などと断言しているシーンがある。これを見た時、私も思わずそのように叫びたくなったことをまざまざと思い出す。

そして、インターネットの記事から、
・マダニは、生物分類上は、クモの仲間である大型のダニであること、
・住宅に生息するイエダニが0.2~0.4ミリ程度でほとんど肉眼では見えない大きさであるのに対し、マダニは、その種類にもよるが、通常3から8ミリ位の大きさで、血を吸うことによって10から20ミリ程度まで大きくなること、
・他の動物から数日間にわたって吸血することにより、体内に様々な病原体を保有していること、
・一旦マダニに食いつかれると容易に引き離せず、マダニの一部が人体に残れば、そこから病原体が広がり、ライム病を始めとする種々の感染症を引き起こすこと
などを知った。
私の症状は、幸い、抗生物質の効果で、その後徐々に改善されていった。抗生物質は、更に5日分を処方してもらい、血液検査の結果、ライム病等に感染していないことも確認した上で、完治を宣言された。
こうして私はマダニの恐ろしさを知った。
そして、それ以降、私も妻も、山に登る時は、マダニに食いつかれないよう長袖長ズボンを着用するとともに、藪漕ぎをした後は着衣や皮膚にマダニが付着していないことを確認するようにしたのである。
しかし、マダニ禍はそれで終わらなかった。
妻のケース
私がマダニの被害に遭ってから8年後の夏休み、私と妻は、北海道の幌尻岳(標高2052m)に登った(この山は日本百名山に含まれる。なお、本コラム#3参照)。
幌尻岳は、日高山脈の奥深いところにあり、メインの登山路は沢沿いでしばしば降雨に伴う増水によって通行ができないことがある。そこで、私達は、そうした懸念のない新冠ダム湖からのルートを取ることとした。前日、車の入れるゲート前にレンタカーを駐車し、そこから距離にして延々17.5キロに及ぶ林道を歩いて、山懐にある新冠ポロシリ山荘という無人小屋に一泊した。
登頂当日は、天候に恵まれ、朝5時、小屋に寝袋や食料を残して出発、途中しばらく笹に覆われた沢筋のルートを進んでから、高度差1000メートルを超える急坂を登り切って9時半山頂に到達した。山頂からは、360度遮るもののない日高の山々の眺望を堪能し、高山植物が咲き乱れる様を楽しみながら七つ沼カールと呼ばれる氷河地形を見下ろす北東の肩を往復した。そして、11時半下山を開始し、15時荷物を置いてある小屋に帰り着いた。その夜は、この小屋にもう一泊して、翌日また長い林道を歩いて帰るつもりであった。
幌尻岳北東の肩から七つ沼を俯瞰
妻のただならぬ悲鳴を聞いたのは、私が小屋の2階に上がって寝場所を確保しようとしていた時のことである。
私が慌てて1階に下りると、妻は外から水を引き込んでいる炊事場に立ちすくんでいた。右ほほにマダニが食いついているのを鏡で発見したという。見ると、確かに、妻の右ほほにマダニが付いている。
妻は、私が奥鬼怒でマダニに咬まれたことを目の当たりにして以来、マダニに対する警戒に怠りはなかった。当日も、笹をくぐる箇所があったことから、マスクをした上、ヤッケのフードをかぶって頭部顔面を保護していた。それにもかかわらず、マダニはマスクの下に潜り込んでいたのである。
私は、マダニを潰すとそこから病原菌が体内に拡散して感染症を惹起することは、自分の経験から十分に理解していた。もっとも、今回マダニがいつ付いたのかは分からず、つまめば簡単に除去できるかもしれない。そう考えて、私は妻の頬からマダニを取り除こうとしてつまんでみた。ところが、マダニの頭部は既に頬の中に入り込んでいたと見え、私がつまんだ下半身はそこで千切れ、上半身を頬内に残す結果となってしまったのである。
そうすると、私の経験に照らしても、いずれ病原体が回って妻が体調を崩すことは必至と思われた。そして、妻が車を止めた場所まで17.5キロに及ぶ林道歩きに耐えられるという保証はない。しかも、私はペーパードライバーで、自動車の運転は専ら妻に任せていたので、妻が運転できないと、山中からの脱出も困難になる。
そうしたことから、私達は、当夜、小屋に泊まるという当初の計画を改め、妻の体調が悪化する前に下山し、少しでも早く病院に行くことを決めた。
それからが大変であった。
夕食作りを中止し、早々に荷物をまとめて小屋を出たのが、夕方の4時である。長い林道を歩いているうちに、日が暮れ、ヘッドランプを点灯して歩くことになった。
そうなると、怖いのはヒグマである。日高山脈はヒグマの生息地として知られ、ヒグマにより被害を受けた話も耳にしていた。そこで、クマよけの鈴を鳴らすだけではなく、普段は使わない笛もピーピーと吹き鳴らしながら歩いた。暗闇の中私達の前をキタキツネがまるで我々を先導するように歩いて行く。ところが、キツネには、鈴や笛の音にまるでひるんだ様子がないのである。キツネにすら効き目がないのであるから、ヒグマを撃退する効果はそれほど期待できなかったが、それでもないよりはマシであろうと思って、必死に笛を吹き続けた。
夜8時、レンタカーを止めた場所に辿り着いた時には、本当にホッとした。当日は朝5時から歩いているので、行動時間は既に15時間に達していた。
しかし、少しでも早く医者に行くことが目的である以上、ここで休む訳にはいかなかった。車を発進させた後も、真っ暗な山中の林道が延々と続き、途中エゾシカやキタキツネが頻繁に道に立ちふさがったり横切ったりしたため、往路よりもずっと時間がかかり、道路が舗装されている人里に出た時には10時半になっていた。
近くの宿泊施設に電話をしてみたが、既に遅い時刻であり、宿泊を断られてしまった。やむなく千歳に直行することとし、折から降り出した雨の中、日高道、道央道を通り、何とか千歳駅前のビジネスホテルに転がり込むことができたのは、深夜零時半である。
小屋で起床したのが3時半であったから、それから21時間、本当に長い一日であった。とりわけ妻は、幌尻岳往復の後、マダニに食われた上、暗闇の中、林道歩きに耐え、長距離にわたる車の運転も担当し、良く頑張ったと思う。
翌朝8時、私達は、開院時間に合わせて近くの病院を訪ねた。担当の若い男性医師はマダニには慣れた様子であり、妻の頬を手際よくメスで切開してマダニの頭部を除去するとともに、抗生物質2週間分を処方してくれた。
私が医師に「マダニを取り除こうとしたのが間違いで、やはりそのままにして病院に来るべきだったのでしょうか。」と尋ねると、「マダニが付いたままだと気持ちが悪いので、取り除こうとするのは仕方がありません。大抵の人がそうします。その上で早く病院に来たのは正解でした。」とのことであった。
また、妻が「マダニに咬まれて死んだというニュースを耳にしますが、私も死んでしまうのでしょうか。」と真顔で問うたのに対しては、「死者が発生しているのは主に西日本で、北海道ではまだ出ていません。」という答えであった。私達が一安心していると、医師は続けて「そうは言っても、何事にも最初ということがありますから。」などと言い足したのである。半分冗談で言ったのだと思うが、それを聞いた私達の表情は引きつっていたはずである。
その日の飛行機で、私達は帰京した。
幸い妻は感染症を発症しなかった。
2日後、私達は今度は四国の山に向けて出発した。
追記
その後、2016年に北海道で男性がマダニに咬まれ、ダニ媒介脳炎を発症して死亡したとの報道に接した。
また、2023年放送のNHKニュースによれば、2022年の1年間に全国で116人、マダニにより重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に感染したとの報告があり、うち12人が死亡した由である。