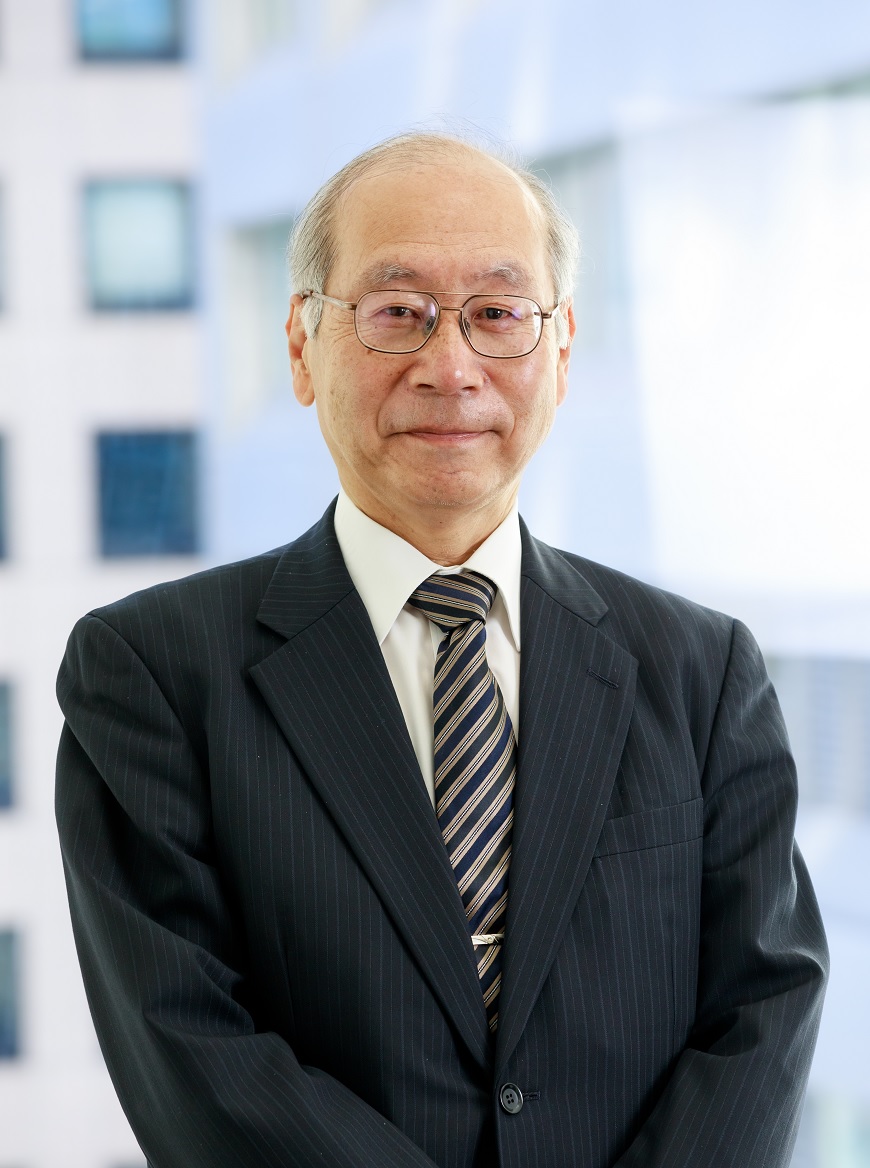[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#14 シャングリラ探しの旅」:大野恒太郎弁護士(顧問)
シャングリラ探しの旅
―小説のモデルとなった桃源郷はどこか―
シャングリラは1933年英国の作家ジェームズ・ヒルトン(1900-1954)が著した小説「失われた地平線」Lost Horizonの舞台となった架空の土地である。これまで、そのモデルとなった地はどこかなどと盛んに議論され、私自身もシャングリラの持つ秘境性に惹かれ、その面影を探し求める旅を重ねた。
1 小説「失われた地平線」
これまで同書を読んでおられない方のために、はじめにそのあらすじを記すことにする。
時は1931年、主人公コンウェイはインド周辺国の英国領事であるが、同地における動乱のため、その部下等3名と共に飛行機で脱出を図る。ところが、飛行機はチベットの山中に不時着、主人公らはラマ僧らに救出され、その僧院へと連れて行かれる。
僧院のある地がシャングリラであった。そこは高峰の山懐に位置し、外の世界とは切り離された豊饒な別天地であり、平和で健康的な暮らしぶりから、ラマ僧らは不老長寿に近い生活を送っていた。しかも、ラマ僧院は、西洋の近代的な設備を備えており、ラマ僧らの中には西洋人も含まれ、英語もかなり通用した。
主人公は、ラマ僧の最長老が18世紀にこの地に至った西洋人宣教師であり、飛行機不時着の件が長老の後継者を確保するために仕組まれたものであることを知る。世界が再び破滅的な戦乱に巻き込まれることを予感していた主人公はシャングリラに住み着くことに心惹かれるが、一日も早い帰国を求める年若い部下の懇願に折れ、ある日密かに部下と共に山を越えてシャングリラを脱出し、衰弱した身体で、中国四川省の重慶に辿り着く。しかし、その後、主人公は消息を絶つ。
本書が発表された当時、欧州は第一次大戦の記憶が鮮明であり、ナチスの台頭等にも直面していた。そのため、戦乱のない平和な世界を求める読者の心情が本書の描くユートピアとしてのシャングリラを一層魅力的なものにしたに違いない。したがって、同書は出版後直ちにベストセラーとなり、これまで繰り返し映画化されている。
もっとも、西洋人の高僧が理想郷を取り仕切り、その後継者としてわざわざ英国人である主人公を誘拐まがいの方法で連れて来たという筋書き等には、当時における西洋人優位の考え方が露骨に表れており、多少の違和感を覚えずにはいられなかった。
なお、小説中シャングリラの場所については、チベット高原北西側の崑崙山脈の近くであるとされているものの、これは主人公らの脱出先が崑崙山脈からはるかに離れた四川省の重慶であることと位置的に符合しない。
また、著者は、本書出版後ニューヨーク・タイムズの取材を受けた際に、本書執筆に当たっては1840年代にフランス人宣教師がチベットを訪れた際の旅行記を参考にしたと述べている由である。
2 パキスタン北西部フンザ

私がシャングリラを意識するようになった最初の契機は、1993年夏のパキスタン北西部フンザ訪問である。
当時私は有力政治家の脱税事件の公判に専従していたのであるが、7月に第1回公判が開かれた後、第2回公判期日がかなり先の9月に指定されたことから、その間に2週間の海外旅行を行った。それは、中国最西部の新彊ウィグル自治区カシュガルから車でパミール高原クンジュラフ峠(4693m)を越えてパキスタンに入り、カラコラム・ハイウェイをインダス峡谷沿いにラワルピンディに抜けるというもので、その途中フンザに立ち寄ったのである。
フンザは、ラカポシ(7788m)、ウルタル(7388m、日本の著名な登山家長谷川恒男氏が1991年に遭難死亡した山)等の高峰に囲まれた小盆地に所在する。その前後の険しい峡谷が乾いた不毛の地で、ほとんど一木一草もなかったのに対し、アンズ等が豊かに茂る緑の別天地であり、まさしく桃源郷と呼ぶにふさわしい土地であった。取り分けかつてこの地に君臨した藩王の居城の背後にウルタル峰の険しい岩壁がのしかかるようにそびえる景観には強烈な印象を受けた。
そして、「失われた地平線」の著者ヒルトンが執筆に先立って同地を訪問したことがあったため、フンザの観光案内においても、しばしばその事実が引用され、フンザこそシャングリラのモデルであるなどと喧伝されていた。しかも、紀元前4世紀には、アレクサンダー大王の率いるマケドニアの軍勢がこの付近にまで進出してきた史実を踏まえ、付近住民はその末裔であるなどと言う説すらまことしやかに唱えられていた。
私はフンザ訪問時にまだ「失われた地平線」を読んでおらず、シャングリラは俗界から隔絶した山中の理想郷であるという程度の理解しか有していなかったため、フンザがシャングリラのモデルであるとする宣伝に格別の疑問を感じなかった。
しかしながら、フンザは、チベットに位置しておらず、宗教的にもイスラム教が支配的であって、地域内にチベット仏教のラマ僧院は存在しない。さらに、中国の重慶との間には、東西に長く伸びるヒマラヤ山脈があるため、ここから陸路重慶に至ることはおよそ物理的に不可能である。したがって、フンザがシャングリラのモデルであるとすることには無理があると言わなければならない。
もっとも、著者ヒルトンがフンザを訪れた際に目にした風景を小説の中に盛り込んだことは十分に考えられる。「失われた地平線」の中に、僧院の背後に聳える高峰について、主人公がスイス・アルプスのグリンデルワルドから見上げたヴェッターホルンのようであると感じた旨の一節があるが、それはまさしく私自身がフンザから首の根が痛くなるような角度でウルタル峰を見上げた際に受けた印象そのものであった。
3 中国四川省シャングリラ
次に私が訪ねたのは、中国四川省西南部のシャングリラ鎮(郡。なお、シャングリラの中国語表記は「香格里拉」)である。それは退官後の2018年秋のことであった。
シャングリラ鎮は標高3000m近い谷合にあり、四川省省都の成都から車で丸2日をかけ、4000mを超える峠をいくつも越えてようやく到達した。この時は、同じ月の中で公私合わせて3回外国に行くという強行日程のため体調を崩しており、耳の調子が悪く、高度によって大きく変化する気圧への対応ができず、道中激しい耳の痛みや難聴に苦しみ続けた。
シャングリラ鎮からは亜丁自然保護区のシャトルバスに乗って標高4160mの洛絨牛場に至り、これを取り囲むようにして聳える央枚勇(ジャンベーヤンあるいはヤンマイヨン、5958m)等6000m級の山々の、この世のものとも思えない美しい景観を堪能した。また、この地域は、四川省内のカンゼ・チベット族自治州に属し、ラマ教寺院が地元の人達の尊崇を集めていた。しかも、ここは「失われた地平線」の主人公が脱出した先である重慶と同じ四川省にあり、位置的にもシャングリラのモデルに相応しい。
その一方で、シャングリラ鎮自体は深い谷間に位置するため、そこからは直接高峰の姿を望むことができない。ラマ僧院の背後に高峰の景観が開ける場所となると、4000mの高地まで登らなければならないが、そこでは農耕が可能であると思われず、「失われた地平線」の舞台としてはやや高所に過ぎるという難点があった。
当時私は、シャングリラ鎮の名称の由来について、観光客集めのためであろうと推測する程度で、改称の時期や経緯、同地と小説との関連について具体的に知らなかった。
その後、インターネット等で調べたところ、同地は、米国人植物学者のジョセフ・ロック(1884-1962)が1920年代に訪れ、前記央枚勇峰を「自分が見た中で最も美しい山」と激賞するなどその探検記をナショナル・ジオグラフィック誌に掲載しており、著者ヒルトンも「失われた地平線」を創作する前にこれに目を通した形跡があるとのことであった。そして、同書の記載と実際のこの地の状況は、山の形状をはじめ符合する点が多々あると認められる旨の指摘がなされている。
なお、著者が本書執筆の際に参照した資料として19世紀のフランス人宣教師の旅行記に触れていながら(2参照)、直前に発行されたナショナル・ジオグラフィック記事に言及しなかったのは、著作権の問題を警戒したからではないかとのうがった見方をする者もいる。
いずれにせよ、四川省シャングリラ鎮については、小説のシャングリラのモデル地であると主張するにつき、一応の理由は立つように思われる。
4 中国雲南省シャングリラ

四川省シャングリラ鎮で素晴らしい景観に接すると、気になるのが、その南側に接する雲南省にあるシャングリラ(香格里拉)市である。ここはもともと中甸という名称の県であったが、2002年にシャングリラと改称し、2014年には市に格上げされたとのことである。四川省のシャングリラが鎮(郡)であるのに対し、県はランクが一つ上であり、改称に際しては中国国務院の承認も得ているというのであるから、言ってみれば格が違う。
四川省シャングリラ鎮と雲南省シャングリラ市は、間に山脈を挟んで300kmほど離れ、1日かけて両者を結ぶ路線バスも運行されるような位置関係にある。3で触れた米国人ロックは、雲南省麗江を拠点に27年間にわたり中国西部の植物や民俗の研究を行っており、当然雲南省の側も詳しく調査している。そして、四川省シャングリラ鎮の近くに央枚勇等の高峰があるのに対し、雲南省シャングリラ市もその周辺部には四川側を凌ぐ雄峰が聳えており、陸路重慶に至ることができるという点においても四川側と遜色がない。
そのようなことから、私は四川省シャングリラに続き、雲南省シャングリラに旅行しようと考えたのであるが、コロナ禍による渡航禁止もあって、それがようやく実現したのは、2024年9月のことであった。
中国のインフラ整備の規模と速度には驚くべきものがあり、往路は雲南省省都の昆明から途中まで新幹線を使い、帰路はシャングリラ市から空路で昆明に戻った。シャングリラ市の市街地は、標高3200mの高原上にある。そして、やや離れた丘の上には巨大なラマ教寺院の松賛林寺が建ち、そこにはあずき色の僧服に身を包んだラマ僧が多数出入りするなどしていた。しかし、私が「失われた地平線」を読んだイメージからはあまりにも開け過ぎており、山が遠過ぎる印象を受けた。少なくともその市街地に関する限り、白銀の高峰が背後にのしかかるように聳えているというシャングリラの景観の片鱗すら窺うことはできなかったのである。
もっとも、ここから車で片道1日を要する市北西部に位置する徳欽のラマ教寺院飛来寺付近(3480m)からは、瀾滄江(メコン川源流、その付近の標高は2000m程度)の深い峡谷を挟んで、横断山脈の梅里雪山(メイリ―シュエシャン、6740m。1991年京大学士山岳会メンバーを中心とする日中合同登山隊が遭難して17名死亡。その後未登のまま登山禁止とされた)の峰々が高く美しく連なっていた。
そして、この旅で私が自分の有するシャングリラのイメージと最も近いと感じたのは、梅里雪山に行く際に渡った瀾滄江の谷に点在する小集落とブドウ畑の景観である。19世紀にフランス人宣教師がこの地にブドウを持ち込み、地元の人達にその栽培とブドウ酒の製造を教えたとのことであった。峨々たる斜面に取り囲まれ、外界からは遠く隔てられた谷間に豊かな緑の空間が開けている様は、まさにそこが別天地であることを実感させるものであった。そのようなことで、ヒルトンもこのような奥地に入り込んだ宣教師の話を伝え聞き、それもまたシャングリラのイメージの中に反映されているのではないかなどと勝手な想像を膨らませたのである。
冒頭でも述べた通り、シャングリラは、著者ヒルトンの創作にかかる架空の土地であり、そこには様々な土地に関する情報や著者の想像が盛り込まれていると思われる。したがって、特定の土地についてそれがシャングリラのモデルであるかどうかを詮索することは、本来あまり意味のある作業ではないであろう。
しかし、シャングリラは、ヒルトンの小説を読んだことのない人をも含め、世界の多くの人にチベットの山中にある秘密の理想郷についての夢を与えたという点においてその影響は大きい。私自身も、その旅に「シャングリラ探し」という一味変わった視点を加え、30年間にわたり大いに楽しませてもらったのである。
(追記1)
フンザの位置するパキスタン北西部は、私が訪問した後、2001年の米国同時多発テロ前後からイスラム原理主義勢力がその影響力を増していると伝えられている。実際に、2011年には、カラコラム・ハイウェイが山間部を抜けたところにあるアボタバードにおいて同所に潜伏していたアルカイダの指導者オサマ・ビン・ラディンが米軍に殺害されるなど、一般人が旅行をする先としては必ずしも安全な先ではなくなっているようである。
また、中国も、日中間の歴史的な経緯や近時における国際間の緊張の高まりにより、その旅行にいささかの懸念を覚える日本人も少なくない。
ヒルトンは、世界の戦乱を予感する中でシャングリラという平和なユートピアを創造したのであるが、「シャングリラ探し」の旅を楽しむことも、平和な世の中であることがその大前提である。昨今武力紛争が拡大する国際情勢を見るにつけ、著者がシャングリラに込めた平和を願う心が改めて切実な思いとして感じられる。
(追記2)
本エッセー脱稿後NHKのBS放送で「中国空旅:シャングリラを探して」という番組を見た。シャングリラ探しをテーマとしつつ、ヒルトンの小説の筋立てに過度にとらわれることなく、四川省と雲南省の山奥の美しい自然景観や平和な集落が紹介されていた。そして、本文4で触れた四川省シャングリラ市の松林賛寺などにも立ち寄りながら、最後には徳欽から瀾滄江対岸の梅里雪山山懐にある雨崩という村に至るという内容であった。
この番組は、いずれかの地をシャングリラとして特定するのではなく、インタビューした村人の言葉を借りて、シャングリラはそこに暮らす人々の心の平穏の中にあるとするものであり、私としても大いに共感するところがあった。