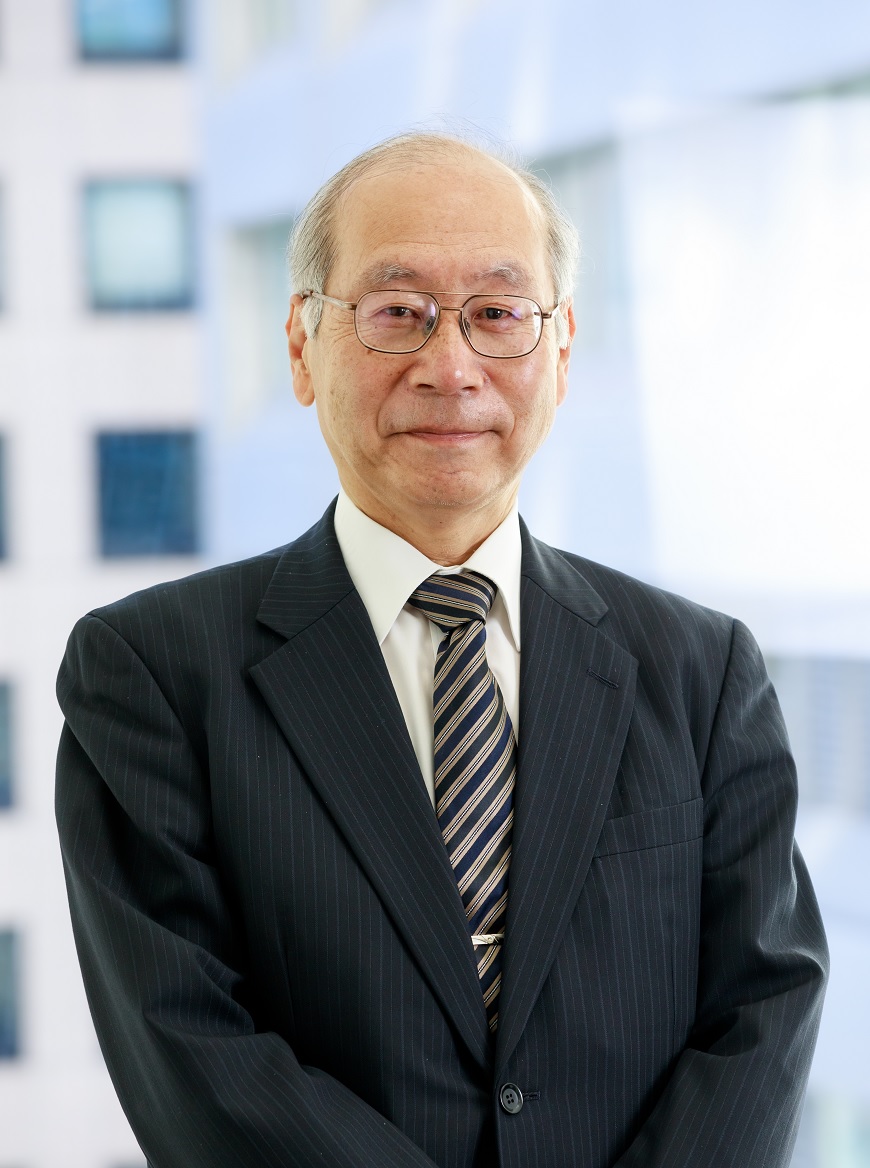[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#12 企業と司法取引」:大野恒太郎弁護士(顧問)
企業と司法取引
―守るべきは会社の将来―
今回は、企業がどのように司法取引制度に向き合っていくべきかについて考えてみることとしたい。
刑事事件と企業
はじめに、その前提として刑事事件が企業にどのような影響を及ぼすかを見てみよう。
企業はその活動をする過程で、様々なトラブルに遭うことは避けられないが、その中でも最も深刻なものが刑事事件である。
刑事事件の疑いを生じ、捜査当局による捜査が開始されると、関係個所の捜索が行われ、多数の資料を差し押さえられ、関係者の身柄の拘束が行われることもある。そして、マスコミの取材や報道が過熱すれば、それへの対応にも追われ、日常業務を遂行することは事実上不可能になる。
その後その事件が起訴された場合には、企業は、裁判への対応等で一層長期間にわたり大きな負担を余儀なくされる。
刑事事件は、時に経営トップの辞任を避けられないものにする。さらには、株価の暴落や関係取引先や社会からの反発を受けて、企業の存続が危ぶまれる事態を招くこともある。
そうした意味において、刑事事件は、企業にとっていわば究極の危機対応を要する事態と位置付けることができるであろう。
したがって、不幸にして刑事事件が発生した場合、あるいはその発生が見込まれる場合には、企業としては、いかにしてそのダメージを最小限にとどめるのかが問われることになる。
ところで、日本の刑法の下では、通常刑罰の対象となるのは、個人である。法人(会社・企業)が刑事処罰の対象となるのは、法律上個人と法人の両方を処罰する両罰規定という特別な規定が置かれている場合に限られる。司法取引対象犯罪のうち、両罰規定を置いているのは、税法、金商法、独禁法、不正競争防止法等であり、刑法は個人処罰のみを規定している。
両罰規定があるケースにおいて、会社に対する有罪判決が下されると、会社は、まず刑事罰として罰金を支払わなければならない。これに付随する不利益として、公共入札からの一定期間にわたる排除、取引停止、各種業法上の許認可欠格事由への該当(建設業、廃棄物処理業、債権回収業等)、社会的評価の低下等がある。
日本の法律に規定されている罰金額は、諸外国に比べると極めて低い。しかし、罰金額そのものよりも、刑事処分を受けたことに伴う社会的経済的損失の方がはるかに深刻なのである。
一方、両罰規定がない場合、例えば刑法犯である贈賄事件のケースなどにおいても、会社の役職員が会社の業務に関連して刑事事件を起こしたということであれば、社会的非難は会社に向けられる。そして、刑事罰が役職員個人にとどまる場合であっても、先程述べた様々な社会経済的不利益の多くは、会社にも及ぶ。
このように刑事事件は企業に甚大な影響を及ぼすものであるので、企業がそうした事態に対応するに当たり、司法取引がどのような意味を持つか、どのように活用すべきかについて、これまで公にされている実例も踏まえて検討してみよう。司法取引の活用は、その立場によって異なるところがあるので、役職員個人としての立場と企業の立場とを分けて論じる。
役職員の立場から見た司法取引の活用
まず、役職員、つまり企業に身を置く個人の立場から考えてみたい。
一番典型的な場合は、例えば、会社の粉飾決算事件(金商法に規定される虚偽有価証券報告書提出罪)でその経理担当者が検察官の取調べを受けるようなケースである。担当者は上司の指示で虚偽の内容の帳簿記載を行っており、真実の数字を記した裏帳簿を隠し持っている。それを認め、裏帳簿を提出すれば、会社の粉飾決算が明らかになるが、実行行為者である自分の刑事責任も追及されることが懸念される。だからといって、このまま否認を続けていると、いずれ身柄を拘束されるおそれがある。担当者はまさに進退両難のジレンマに陥っているのである。
経理担当者としては、こうした場合、弁護人と相談をして、検察官に対して、粉飾を指示した上司あるいは会社の犯罪の捜査に協力するという内容の司法取引を申し込むことが考えられる。そして、上司からの指示も含めて真実の供述をし、裏帳簿を提出することと引き換えに、不起訴処分、したがって事実上身柄も拘束されないという有利な取り扱いを受けることを相当程度期待できるであろう。
こうしたケースが、役職員個人による司法取引の例である。したがって、会社組織の中で上司の指示を受け心ならずも不正に手を染めてしまったような場合でも、事案によっては、司法取引を行って上司や会社の犯罪に対する捜査に協力することにより刑事処罰を免れる道が残されているのである。
このように、司法取引は今後企業役職員個人の刑事事件の弁護活動における有力な選択肢となる。
これまでは、捜査当局に協力しても、その結果有利な処分を得られるかどうかを確実に予測することができなかった。そこで、弁護人としては、捜査段階ではとりあえず検察側になるべく証拠を与えないようにし、それでも起訴された場合には、検察側から開示された証拠の内容を見て裁判で争うかどうかを決めるというように、万事受け身の対応をすることが少なくなかった。そのため、依頼者個人は逮捕され、起訴されるなど取り返しのつかない不利益を余儀なくされていたのである。
しかし、今後は、これまでのように検察側と弁護側が常に対立するという二項対立的な固定観念にはとらわれず、司法取引によっていかに有利な処分を確保するのか、弁護士の手腕が問われることになった。
司法取引第3号として報道されている事件は、まさしくこうした類型に当てはまるものであった。本件は、アパレル会社の社長等が会社の売上金を着服したという業務上横領事件である。検察側と司法取引を行ったのは、社長等に指示されて着服金の出し入れという犯罪の実行行為を行った担当社員であり、不起訴の約束と引換えに、社長らの犯罪に対する捜査に協力したとのことである。
また、第4号事件もこの類型に当てはまる。この事件においては、税理士事務所の職員が、不起訴の約束と引き換えに、自動車販売会社やその顧問税理士らによる銀行に対する詐欺事件の捜査に協力した由である。
会社の立場から見た司法取引の活用
次に、会社の立場から見た場合の司法取引について考えてみよう。
言うまでもなく、司法取引は、両罰規定がある場合には、会社に対する刑事処分の免除・軽減を得る上で有用である。また、両罰規定がない場合であっても、会社として、主犯以外の役職員に対する処分の減免を図るため、これら役職員による司法取引を支援することも考えられる。
しかし、会社にとって最も重要なことは、司法取引が、不祥事を生じた企業が自ら膿を出す自浄作用によって不正と決別する姿勢を明らかにして、その信頼・レピュテーションを回復する足掛かりとなることである。
ここで「真に守るべきは、会社の過去ではなく、その将来である」ことを強調したい。
具体的事例を見てみると、司法取引が用いられた第1号事件は、三菱日立パワーシステムのタイ公務員に対する贈賄事件である。会社は司法取引の結果起訴されず、一部の役職員が起訴され、争った者もいたが、全員有罪判決を受けている。
この事件に対する論評の中には、「本来責任を負うべき会社が免責され、その役職員だけが処罰されるのは、トカゲのしっぽ切りである。」という趣旨のものがあった。
しかし、これは的外れであるように思う。そもそも我が国における法人処罰は、両罰規定によってその役職員個人に対する犯罪と連動するものとされ、法人の処罰根拠は監督責任であること等にかんがみると、法人を主犯ととらえることは難しい。
そして、実際上も、会社としてはコンプライアンスを重視して相当の措置を講じてきたにもかかわらず、一部の役職員が、自分の成績を良くして社内の地位を上げようというような個人的動機から、会社の方針に反して密かに不正に走るというケースも決して稀ではないからである。
また、司法取引第2号の事件は、あまりにも有名なカルロス・ゴーン氏の事件である。日産自体は司法取引の当事者とはならなかったが、その役職員による司法取引を会社として後押ししたと言われている。
ゴーン氏が起訴されたのは、自分の報酬額を偽ったという虚偽有価証券報告書提出罪と、個人的な使途に充てる目的でサウジやオマーンの関係先に対して日産の資金を不正に支出し、日産に損害を与えたという特別背任罪の2罪名であった。そのうち、虚偽有価証券報告書提出罪は、両罰規定があるので、日産は理論上司法取引の当事者となりうる。これに対し、特別背任罪には両罰規定がなく、日産はむしろ被害者の立場に立つ。
しかし、日産が理論上司法取引の主体となりうる虚偽有価証券報告書提出罪についても、司法取引を行った当事者は、役職員個人であって、日産という会社ではなかった。これは、同社代表取締役であるゴーン氏が主導した犯罪である以上、日産の会社としての責任は免れないと考えられたからであろう。そして、現に虚偽有価証券報告書提出罪については、日産も起訴されている。
それにもかかわらず、日産がその役職員による司法取引を支援するなど事実上検察の捜査に協力したとされることの背景には、日産の会社としての判断が働いたものと推察される。すなわち、日産としては、虚偽有価証券報告書提出罪により会社が処罰されることになったとしても、ゴーン氏による一連の犯罪の解明に全面的に協力することによって、社内外に会社として不正とは縁を切る姿勢を明らかにし、会社の再建と信頼回復を図ろうと考えたものと思われる。
内部通報と内部調査
ここで注目すべきは、第1号事件も第2号事件も、司法取引に先立ち会社に内部通報があり社内調査が行われたという点である。
今やどこの会社も内部通報を無視することはできない。これを握りつぶせば、通報者は社外のマスコミや捜査機関に対して、会社には通報を採り上げてもらえなかったと訴えるであろう。そして、内部通報が推奨され、インターネットが発達している現在、こうした情報はいずれ必ず外部に漏れ、瞬時に拡散することを覚悟しなければならない。
そうだとすれば、仮に内部調査の結果相当重大な犯罪の疑いが浮上した場合に、会社としてはどうすべきか。
そうした場合に、司法取引は、企業側が先手を打って検察側に相談して合意をすることにより、企業の受けるダメージを最小限のものにすることを可能にするのである。
従来は、内部調査の結果を捜査機関に持ち込んでも、果たしてどのような処分が行われるのか必ずしも予測できなかった。そのため、これに二の足を踏むことが多かったと思われる。
これに対して、司法取引を行えば、企業側は、刑事処分について確実な見通しを得るとともに、捜査のスケジュールやマスコミへの対応等についても検察側との協議等を通じてそれなりの準備をすることが可能になるのである。
なお、内部調査の結果を受けて司法取引を行うというケースに類似するものとして、不祥事等を契機に旧経営陣が退陣し、新経営陣が事実関係を調査したところ、旧経営陣の行為が刑事事件に該当する疑いが濃厚になったというケースも想定される。
そうした場合、新経営陣としては、株主等ステークホルダーに対して責任の所在を明らかにして、過去を清算し、信頼を回復するために、司法取引を活用することが考えられる。その際には、旧経営陣による犯罪の捜査に協力することと引換えに、旧経営陣の下で不正行為に関わった職員に対する処分の減免を求めることとなろう。
司法取引との関係で企業が留意すべき点
一つ目は、最も責任の重い者の処罰を覚悟すべきことである。
企業として、自ら司法取引を行おうとし、あるいはその役職員の司法取引を後押ししようとする場合、それは他人つまり主犯の刑事事件の捜査に協力することであるから、その事件について自社内で実質的に最も責任の重い者の処罰を覚悟しなければならない。
したがって、社長や担当の役員がその件に関与しており最も責任が重いにもかかわらず、その下の職員に責任を押し付け、役員達が罪を免れるような対応は許されない。検察側としても、司法取引の運用上、社会の理解が得られることを重視するから、そうした司法取引には応じないであろう。
もっとも、その事件が、他の会社や公務員等社外の人にも関係し、社外の人を「他人」とすることができる場合であれば、事情は異なってくると思われる。
次に、検察側を取引に応じさせるためには、「他人の刑事事件の捜査」に有用な信頼性の高い証拠を提出しなければならない。したがって、会社として徹底した内部調査を遂げ、事件に関与した役職員に事実関係を正直に供述させることはもちろん、その供述を裏付けるメール等の物証を確保して提出することが重要である。
そうした「堅い」証拠がないと、主犯が否認した場合には水掛け論に陥るなどとして、検察側が司法取引に難色を示し、合意に至らないことも考えられる。
そして、タイミングも極めて重要である。
例えば、談合のようにその事件が他の会社にも関係するときに、先に他社が司法取引を行った場合、検察にとっては重ねて司法取引を行う利益が失われる。その結果、会社としてはその事件について司法取引をすることが難しくなる。
それは、自社の役職員が会社に先んじて検察と司法取引を行った場合も同様である。そうなると、検察としては敢えてその会社とも司法取引をして刑事責任の減免を約束する必要性がなくなってしまう。
したがって、企業としては、内部通報を受けた場合等には少しでも早く内部調査を進め、その結果に基づき、司法取引についても、これまた迅速果敢な判断と行動が求められるのである。
もっとも、談合事件などにおける司法取引が他の会社に出遅れたとしても、別の事件で司法取引を行うことによって、全体としての処分の軽減を図ることは、なお可能である。
したがって、会社がある事件について調査を進める過程で、他の事件が存在することを発見した場合は、それについて検察側に司法取引を申し入れるということは、十分に考えられる。取り分け元の事件について検察が捜査を進めれば早晩その別事件が発覚する可能性がある場合などには、先手を取ることが肝要である。
ところで、ひとたび会社がらみの刑事事件が発生した場合、会社と役職員間、また役職員相互間に利益相反の問題を生じ、司法取引を行うことについての競争もあり得よう。
したがって、それぞれの権利や利益を確保するためには、会社やその役職員が別々の弁護人を選任する必要がある。
最後に、絶対に行ってはならないことは、証拠隠滅である。
近年のデジタル・フォレンジック技術の進歩により、いったん消去されたメール等のデータも相当程度復元が可能になった。
また、証拠隠滅罪は、司法取引の対象犯罪とされている。したがって、例えば、部下に証拠書類をシュレッダーにかけさせるなどした場合、捜査当局の追及を受けた部下が司法取引に応じ、自分の免責と引換えに上司の指示を明らかにすれば、その上司は重い処罰を免れない。のみならず、企業が組織ぐるみの隠ぺい工作を行ったとして、そのレピュテーションに致命的なダメージを被る。
むしろ企業としては、いったん問題が生じた場合には、無用の疑惑を招かないよう、データの削除や廃棄を禁止する措置をとるべきである。諸外国においては、既にそれが常識となっている。
なお、企業について刑事事件の捜査が開始された場合に、取調べを受けた役職員に対しその内容を事後的に確認することは差支えないが、捜査当局から口裏合わせをしていると誤解されないように注意する必要がある。
司法取引の現状と見通し
司法取引制度は、2018年6月に法律が施行されてから既に6年が経過した。それにもかかわらず、公表された適用例がこれまで僅か5件にとどまるというのは、率直に言って意外であり、期待外れである。
その理由としては、様々な要因があり得るが、裁判所が「引き込みの危険」(#11「日本型司法取引」参照)を警戒するあまり、司法取引の結果得られた証言の信用性を過度に慎重に評価するきらいがあり、これが検察の姿勢に影響している可能性もある。
しかしながら、私はいずれ必ず司法取引が一層活用されることになると考える。
その理由は、何よりも、この制度が事件関係者側と検察側双方の利益になり、かつ公益にも合致している点にある。
そして、独禁法違反の行政手続における課徴金減免(リニエンシー)制度の実績は、そうした見方を裏付けるものであろう。
リニエンシー制度は、カルテル等につき、公取委に進んで事実関係を報告して申請すれば、申請の順序に基づき、課徴金の額が自動的に免除あるいは減額されるという制度である。
2006年にこの制度が導入された当初は、そのように仲間を売るような制度は国民感情に反し、使われることはないだろうと言われていた。
しかし、ふたを開ければ、今やリニエンシー制度を活用することが、当然視されている。公取委が公表している資料を見ると、2024年3月末までの18年間で、申告の件数は累計1573件、しかも、その中には大手企業が軒並み名前を連ねている。
それも当然であって、企業にとっては、この手続を活用することに合理性切実性があるからである。
実務上この関係で重要な先例は、住友電工カルテル事件における株主代表訴訟である。この事件においては他社がリニエンシー申請をしたにもかかわらず、住友電工はこれをせず、公取委から約88億円の課徴金納付命令を受けた。これに対し、一部の株主が、リニエンシーを申請しなかったことは役員の善管注意義務違反に当たり、それにより会社が損害を被ったとして、役員ら個人に対して課徴金額に相当する約88億円の損害賠償請求訴訟を提起した。最終的には2014年に和解で決着したが、役員らは個人で連帯して5億円を超える解決金の支払いを余儀なくされた。
こうした事件は、会社役員にリニエンシーを申請しないことのリスクを痛感させ、ますます会社をしてリニエンシー申請に走らせることとなったのである。
もとより独禁法のリニエンシー制度と司法取引制度との間には多々異なる点がある。
しかし、両者は同様の問題意識に基づくものであることから、司法取引もいずれ活用されることは必至であると考える。
検察は、現在なおこの制度の活用については非常に慎重な姿勢をとっている。しかし、司法取引は、従来型刑事司法の取調べ・供述調書偏重から脱却を遂げる中で、組織的犯罪を摘発訴追するために鍵となる役割を果たす制度である。したがって、いずれその運用が軌道に乗って制度の認知度信頼度が高まれば、加速度的に積極的な姿勢に転じるであろう。
この関係では、先に触れた第4号事件が警察捜査にかかるものであることに注目したい。警察捜査事件においても、司法取引の当事者となるのは刑事処分の権限を有する検察官である。しかし、検察官独自捜査事件に比べはるかに件数の多い警察捜査事件においても司法取引が用いられるようになれば、その一層の活用に道を開くものと思われる。
さらに、最近、大阪地検特捜部が捜査した奈良県御所市の汚職事件が司法取引第5号事件として報道された。これは、同市の市議が建設会社幹部から市発注の工事に関して賄賂を受け取ったというものである。この事件では、建設会社側のコンサル会社社員が司法取引を行い、賄賂工作について証言をしたとされている。
ここで注目すべきは、贈収賄について司法取引が活用されたという点である。賄賂罪は、公務の廉潔性をその保護法益とすることから、収賄側の公務員の処罰に最重点が置かれており、それを実現するためには、今後も特に贈賄側関係者に対して司法取引の積極的適用が図られると思われる。
司法取引制度が企業にもたらすもの
司法取引は、何よりもまず、会社あるいはその役職員に対する処分の免除・軽減を得る上で有用である。
そして、繰り返し述べた通り、企業が自ら膿を出す自浄作用によってコンプライアンスに対する姿勢を明らかにして、信頼・レピュテーションを回復する足掛かりとなり得る制度である。司法取引は、刑事事件が発生したときに、受け身で不適切な対応をして、傷口を広げるような事態に陥らず、より主導的積極的に会社の将来のため「災いを転じて福となす」ことに道を開く。
さらに、刑事司法の範疇を超えたより大きな社会経済的観点から見るならば、司法取引制度は、内部通報制度と同様、企業にとって不正が発覚してその責任を追及される蓋然性を高めるので、不正行為に対する抑止機能を強化するものである。そして、実効的なコンプライアンス体制の構築とも相まって、健全な企業活動を実現し、ひいては社会経済全体の利益の増進にも裨益する。
このように、司法取引制度は、刑事司法の分野だけではなく、社会経済的にも重要な意義を有しているのである。