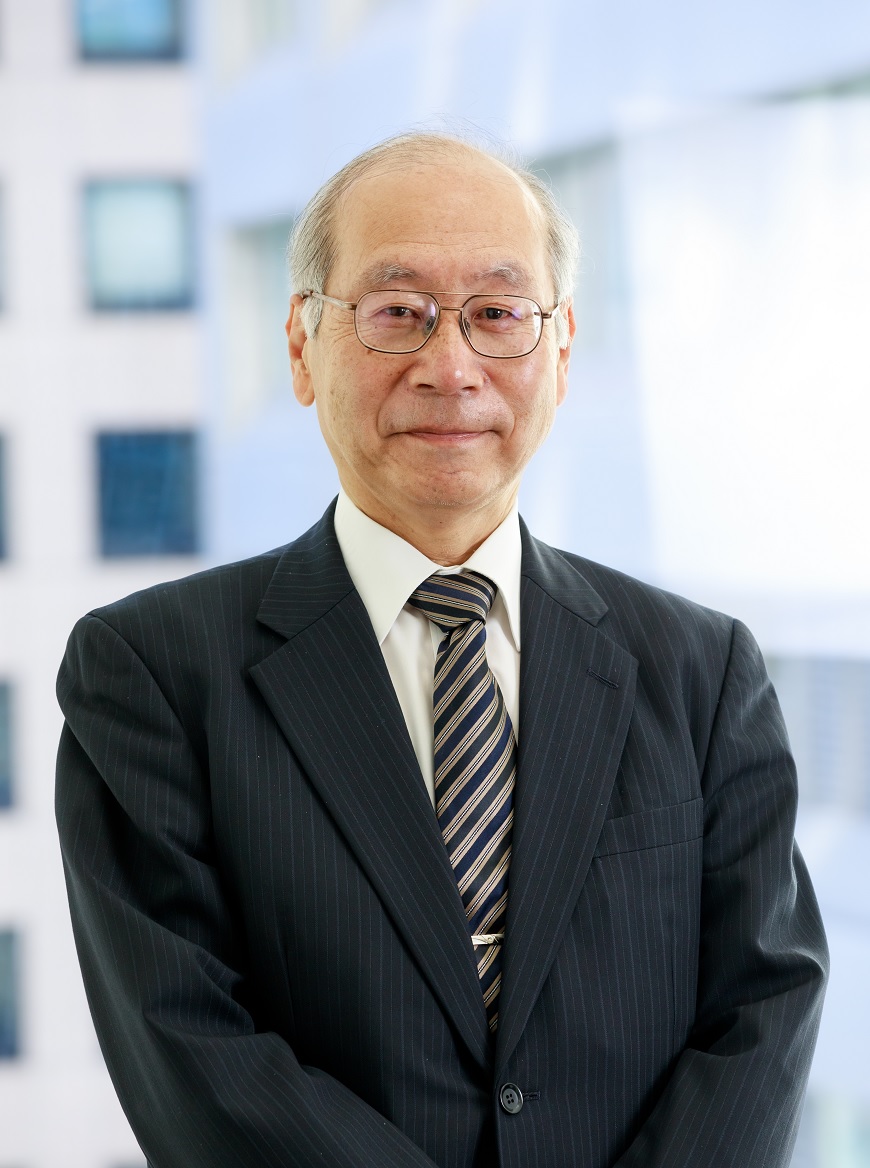[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#10 司法取引の導入」:大野恒太郎弁護士(顧問)
司法取引の導入
―取調べ・供述調書偏重からの脱却―
私は、40年余り検事として勤務したが、その間、我が国の刑事司法は大きく進展した。中でも、刑事手続全体に占める取調べや供述調書の果たす役割は、その時々の検察活動とも密接に関連しながら、劇的に変化した。
本稿では、そうした変化の結果、先年我が国においてもいわゆる司法取引制度が採用されるに至った経緯について触れることにしたい。
なお、この制度は、正式には協議合意制度と呼ぶべきであり、司法取引という用語は、誤解を招く余地もあるなど適切ではないが(詳しくは、#11「日本版司法取引」参照)、社会的には既に広く用いられていることから、本稿でもその語を使用することにする。
従来型刑事司法
我が国で従来司法取引制度が存在しなかったのはなぜか。
端的に言えば、それは従来型の刑事司法の下において必要がなかったからである。
ここで刑事免責制度を例にとって見てみよう。刑事免責は、司法取引とは別個の制度であるが、いずれも自己負罪拒否特権(証言拒絶権)に関係する制度であり、司法取引の結果刑事免責が約束される場合もあるなど、両者は実務上密接に関連している。
私が検事に任官した1976年にはロッキード事件の捜査が行われ、田中角栄元首相らが起訴された。私は当時新任検事としてロッキード社関係者の嘱託尋問調書の翻訳に当たった。この嘱託尋問は、ロッキード社が日本において行った賄賂工作につき、我が国の検察が東京地裁、外交ルートを通じて米国の裁判所にロッキード社関係者の証人尋問を嘱託して行われた。ところが、証言を求められた同社の幹部らが自己負罪拒否特権を発動して証言を拒否したため、日本の検察が検事総長の不起訴宣明等を通じて刑事免責を約束することによって、その証言を得たものである。
英米法上、証言することによって自らが罪に問われるおそれがある場合には、自己負罪拒否特権により、証言を拒むことが認められている。そして、刑事免責は、これを与えることにより同特権をはく奪して証言を強制することができるというものであり、米国においては、特に共犯事件等における事実解明のために不可欠な制度であると位置付けられている。
ところが、日本では、米国等と同じように自己負罪拒否特権が認められているにもかかわらず、長い間刑事免責制度は存在せず、またそれによって直ちに事実解明に不都合を来すこともなかった。これは、結局のところ、当時日本においては、ロッキード社関係者のように自己負罪拒否特権や黙秘権を発動して供述を拒むような事例は稀であり、取調べによって自白を得ることが通例であったからである。
ここで改めて日本の従来の刑事司法(以下「従来型刑事司法」などと呼ぶ。)を他の先進国の制度と対比して見ると、際立った特徴を看取することができる。それは、捜査は被疑者の取調べを中核として綿密に実施され、起訴(公訴)は検察官が有罪の確信が持てる場合に限って極めて慎重に行われ、公判においては、捜査段階で作成された供述調書等を証拠として詳細な事実認定がなされるというものである。これらの特徴から、我が国の従来型刑事司法は、しばしば精密司法などと呼ばれた。
そして、従来型刑事司法は、時に厳しい批判を受けることもあったが、長期間日本に定着し、事件の真相解明や良好な治安の維持に大きな役割を果たしてきたことは否定できない。
例えば、1995年に発生した地下鉄サリン事件をはじめとする未曽有の組織的テロ犯罪であるオウム真理教事件も、結局、従来型刑事司法の枠組みの下で処理された。主犯の麻原彰晃(本名松本智津夫)の関与は、彼の配下である実行犯らの自白や証言がなければ立証できなかったものと思われる。
しかも、我が国においては、刑事司法に対し有罪無罪の判定を超えて被疑者・被告人の動機等の解明も期待する傾向があった。「心の闇が明らかにされるか」などといった新聞記事の常套句にも表れているように、被疑者・被告人に対しては刑事手続の中で包み隠しなく事実を明らかにすることが社会的に求められていたように思う。
また、被疑者・被告人が犯行を自白することは、犯罪者の立ち直りを促進する上でも重要であると考えられた。
こうした従来型刑事司法を最大限に活用したのが地検特捜部である。自白を獲得する力量のある検事は、「割り屋」などと呼ばれ、東京地検特捜部が手掛けたロッキード、リクルート、佐川・金丸、ゼネコン等政財界にかかわる大きな事件の摘発・捜査においては、いずれも「割り屋」とされる検事が大きな役割を果たした。
私自身も、そのような従来型刑事司法に身を置きながら、特捜部等で仕事をしてきた(#1「ある取調べの思い出」参照)。
従来型刑事司法の行き詰まり
ところが、こうした従来型の刑事司法は、21世紀に入り司法制度改革(#7「司法制度改革の立役者」参照)の影響もあって次第に行き詰まりの様相を呈するようになり、それが司法取引導入に繋がっていくのである。
まず、従来型刑事司法を成り立たせてきた自白獲得の点である。
国民の意識変化や、司法制度改革で弁護体制が強化され弁護活動が活発化したことによって、取調べにおいて黙秘権が発動されるケースが増え、自白は次第に得にくくなり、取調べに頼って事件を解明することが難しくなってきた。それどころか、身柄を拘束して取調べを行い自白を得るという手法は、「人質司法」であるなどとしてこれまでにも増して厳しく批判されるようになった。
また、裁判における供述調書重視の運用も、従来型刑事司法の大きな柱であったが、司法制度改革において導入された裁判員制度により、事情が大きく変化した(#9「裁判員制度15年」参照)。裁判員裁判においては、裁判員の方に長大な供述調書を読んでもらうことはおよそ期待できない。そこで、裁判員が「見て聞いて分かる」ような法廷での供述が重視されるようになった。そして、その影響は、次第に裁判員裁判以外の一般の裁判にも及んでいったのである。
しかも、この時期、いわゆる冤罪事件が立て続けに発覚した。
著名な例を挙げるならば、足利事件の再審がある。この事件は、1991年に発生した幼女殺人事件であるが、捜査が行われた当時、現場に残された体液のDNA型は、被告人のDNA型と同一と判定されていた。そして、被告人の捜査段階における自白に基づいて作成された調書も有罪判決の根拠とされ、被告人は無期懲役に処せられていたのである。
ところが、その後の技術の進歩でDNA型鑑定の精度が飛躍的に上がったことにより、実はそれが別の型であることが明らかになった。そのことは取りも直さず、被告人の自白調書の内容が事実に反することを意味するものであった。
こうした事件により、捜査段階において作成された供述調書の信用性が低下し、裁判所も供述調書をこれまでのように広く証拠として採用しないようになった。
そして、決定的だったのが、2010年大阪地検特捜部が捜査・起訴した厚生労働省村木厚子氏に対する事件の無罪判決である。この事件には様々な問題があったが、その中でも、村木氏の関与に関する厚労省関係者の多数の調書が検事の誘導によるものであるとしてことごとくその信用性を否定されたことは、従来型刑事司法がかねて内包していた問題性を白日の下に晒すものであった。
この事件をきっかけにかつてない検察批判が巻き起こり、特捜部解体論すら主張された。私は、この時期、法務省の刑事局長や事務次官を務めており、検察批判の矢面に立つことになった。そうした中で、検察改革・刑事司法改革が行われたのである。
2016年刑事訴訟法改正と司法取引の導入
改革は、2016年の刑事訴訟法改正に結実した。
この改正の趣旨を一言で言えば、従来型刑事司法における取調べや供述調書への過度の依存からの脱却を図ったことである。
まず、村木氏の無罪事件等を受け、強圧的誘導的な取調べがなされないようにするため、裁判員裁判対象事件や検察官独自捜査事件において身柄を拘束された被疑者に対する取調べの録音録画が義務付けられた。
その一方で、取調べに過度に依存しなくても犯罪事実を解明できるよう、証拠収集手段の多様化が図られた。具体的には、司法取引・刑事免責の導入、通信傍受の拡大・要件緩和等である。司法取引をはじめとするこれらの捜査手法は、諸外国では、事件関係者が自白せず、取調べによっては事件を解明できないことを前提に、早くから活用されてきたものであった。
こうして、日本は、取調べや供述調書に依存してきた従来型の手法が行き詰まったことにより、ようやく他の先進国並みに、取調べ以外の証拠獲得方法を充実させて事実関係を解明し、訴追を行うという制度への構造的歴史的な転換が実現したのである。
2016年の刑事訴訟法改正によって導入された制度の中でも、実務的に特に大きな意義を有するのは、司法取引である。
我が国において導入された司法取引は、刑事責任を問われ得る立場にある事件関係者と検察側とが協議を行い、事件関係者が検察側の捜査に協力することの見返りに、検察側はその人に対して刑事処分の免除や軽減を約束するという制度である。
もっとも、このような司法取引制度は、決して抵抗なく受け入れられたものではない。
そもそも日本の刑事司法は、真実の解明を旨とする実体的真実主義に立脚している(刑訴法1条参照)。そうした刑事訴訟の基本的な考え方からからすれば、英米流の司法取引において、その結果行われる有罪の答弁に裁判所が拘束され、時に実体的な真実から離れた犯罪事実が認定される可能性があることに対して強い警戒感違和感があった。
しかし、今回導入された日本版司法取引は、別稿(#11「日本版司法取引」)で述べる通り、英米流の有罪答弁に結び付いた制度とは異なり、他人の犯罪に対する捜査協力型のものであって、裁判所を拘束したり、証拠調を省略するものではなく、実体的真実主義と矛盾するものではない。
また、制度導入の議論の際に、検察の先輩をはじめとする従来型刑事司法を担った人達からも、厳しい批判があった。つまり「犯罪者と取引するとは何事か。取調べで真実の自白が得られないのは、今の検事の力量が落ちているからだ。司法取引は健全な国民感情に反する。」などというのである。
しかし、先程述べたような環境の変化を考えると、最早こうした精神論で乗り切れるような事態ではなくなっている。新しい時代の下でなお取調べ・供述調書に依存したこれまでの刑事司法を維持しようとしても、真実を解明できず、犯罪に有効に対処できない事態に陥る。だからと言って、従来の手法で何としても事実を解明しようとすれば、無理な取調べが行われ、冤罪を生み出すことにもなりかねないのである。
司法取引の必要性
社会正義の観点から考えると、最も重要なことは、重大な犯罪の全容を解明することであり、組織的犯罪においてはその主犯を処罰することである。さもなければ、社会の安心安全は保たれず、一般市民の法や司法に対する信頼が損なわれることになるであろう。
しかしながら、企業犯罪を含む組織的な事件においては、主犯はしばしば自分よりも地位の下の者に指示して直接の犯罪行為を行わせ、自分はその背後に隠れて姿を現さない。そのため、処罰は犯罪を実行した下の者にとどまって、主犯は罪を免れる場合が少なくない。これでは正義公平の感情に反し、犯罪を抑止する効果にも欠ける。
ところで、主犯の責任を問うためには、実行行為者である下の者が主犯からの指示を証言するなど、主犯と犯罪とを結びつける証拠を得ることが必要である。
しかし、下の者から主犯の指示に関する証言を得ることは決して容易ではない。そもそも、下の者は、地位が上の主犯の報復や影響力を恐れている。
それと同時に、下の者が主犯からの指示も含め、犯罪の全貌を明らかにすれば、自分もまた処罰されることになるという事情も無視できない。正直に事実を明らかにすると自分の刑事責任を問われるおそれがある場合に、捜査に協力して真実を供述することを期待するのは実際のところ難しいのである。
こうした人間性の本質にかんがみ、事件を解明するために必要なインセンティブとして司法取引が導入された。つまり、司法取引は、事件の真相を明らかにして最も責任の重い主犯や背後の黒幕・巨悪を処罰するため、それよりも地位が下で役割の軽い共犯者の処分を免除したり軽くしたりすることによってその協力を得やすくしようというものである。このように、司法取引は、公益の観点から十分な必要性・合理性を有する。そうであればこそ、こうした制度は、日本以外の先進国においては、その内容に違いはあっても採用され、活用されてきたのである。
もとより客観証拠が残されていない事件も少なくないことなどから、取調べが依然として重要な捜査手段であることに変わりはない。しかし、取調べ以外の有効な捜査手法を導入することは、取調べや供述調書に対する依存度を相対的に低下させ、裁判所に対してより信用性の高い証拠を提供してその適正な判断を求めることを可能にする。
なお、この法改正については、一部に「捜査側の焼け太りである。」として批判する向きもあったが、それは当たらない。
確かにえん罪を防止するということだけを目的とするのであれば、不当な取調べが行われないよう取調べを可視化し、起訴の判断を一層慎重に行えば良く、それで足りるという考え方があるかもしれない。
しかしながら、現状においても事実解明や訴追が困難化している中で、捜査に対するコントロールを強化するだけでは、重大な犯罪の嫌疑があっても摘発訴追して司法の判断を求めることができず、巨悪を野放しにする結果になりかねない。政治関連の事件や大規模経済事件の告発が検察に持ち込まれるなど、その解明が刑事司法に求められている状況は従来と変わりがない。そして、取調べが録音録画されている下では、下の者は、将来録音録画が再生され、取調べにおけるやりとりが上の者の目に触れることを慮ると、上の者からの指示を正直に明らかにすることをますます躊躇してしまう。そうなると、取調べによって組織の上位者等に迫る「突き上げ捜査」を行うことが実際上著しく困難になる。
したがって、本来刑事司法において裁かれるべき事件を有効に摘発して訴追し、国民の刑事司法に対する期待と信頼に応えるためには、専ら取調べに依存しないでも済むような証拠収集の手段を導入することが必要であると言わなければならない。
司法取引はそのような趣旨の下に導入されたものである。
追記
ロッキード社関係者による嘱託尋問調書は、最高裁大法廷1995(平成7)年2月22日判決により、刑事免責が我が国の法制上認められていないことを理由に証拠能力が否定されたが、他の証拠により関係被告人の有罪判決は維持された。同最高裁判決は、「我が国の憲法が、(刑事免責のような)制度の導入を否定しているものとまでは解されない。」とした上で、「(刑事免責制度)を採用するのであれば、その対象範囲、手続用件、効果等を明文をもって規定すべきものと解される。」などと述べている。2016年刑事訴訟法改正によって導入された刑事免責や司法取引は、こうした判例の趣旨を踏まえた法制度である。