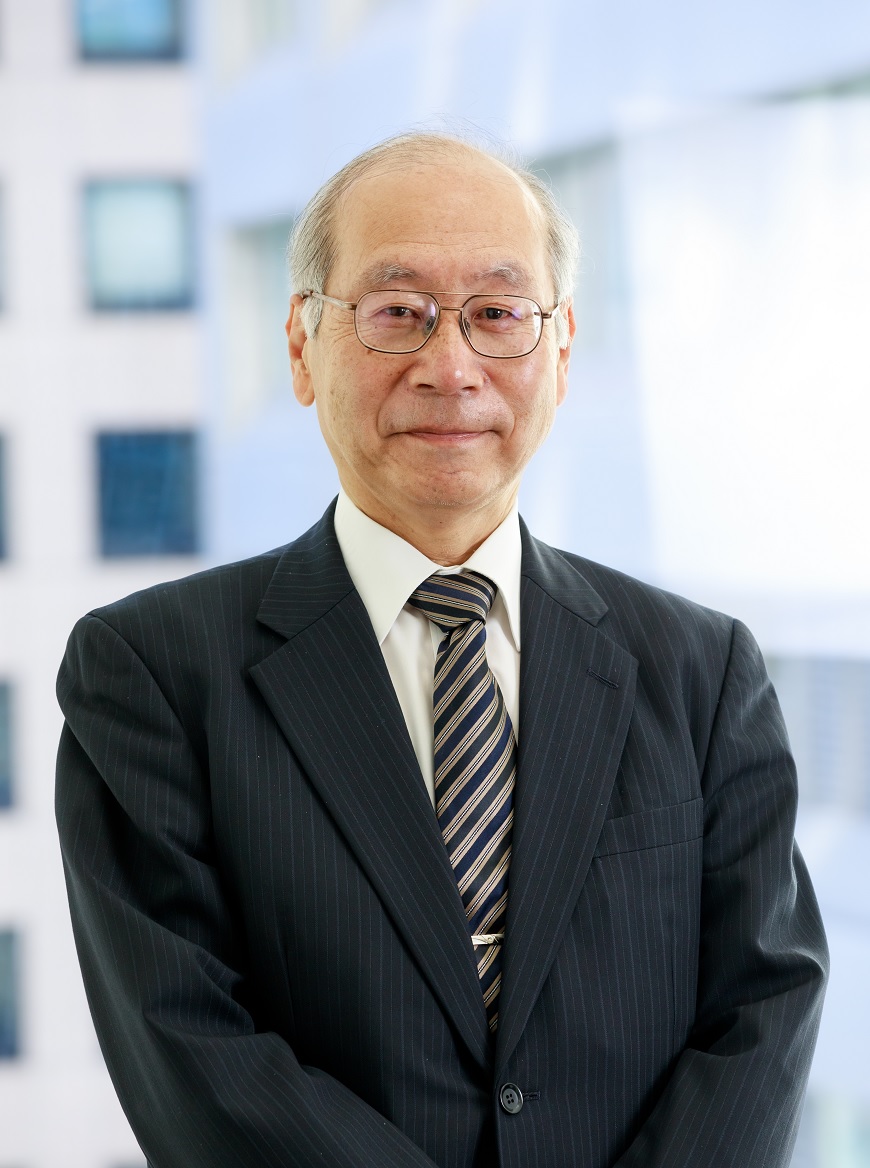[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#09 裁判員制度15年」:大野恒太郎弁護士(顧問)
裁判員制度15年
―その評価と課題、展望―
裁判員制度が2009年5月に施行されてから、15年が経過した。
そこで、今回は、その15年間を振り返り、これまでの運用を評価するとともに、当面する課題や将来の展望について考えてみることとしたい。
裁判員制度15年の評価、司法はどう変わったか
私は、内閣司法制度改革推進本部において裁判員法の立案に関与したが(なお、本コラム#2「裁判員の人数」、#7「司法制度改革の立役者」参照)、その際、裁判員制度に対して実務家を含む各方面から様々な懸念や不安が表明された。例えば、一体国民の協力が得られるのか、専門家でない裁判員に主張や証拠を理解してもらえないのではないか、裁判の結果が極端にブレるようなことにならないか、などというものである。
しかし、実際の運用は、こうした疑問や不安を見事に解消するものだった。実施以来15年、裁判員制度は安定的に運用され、国民の間に定着したように思う。
それならば、司法はどう変わったのか。
まず、裁判員制度の導入により「国民の感覚を裁判の内容に反映させる」という点に関してはどうか。
そもそも刑事裁判における事実認定や量刑については、立場によって異なる見方がなされることが少なくない。そこに一般市民の方が裁判員として参加し、検察側弁護側双方の意見に耳を傾けた上で判断することは、判決に対する納得性信頼性を高めるものと期待された。
そして、実際に、例えば、性犯罪の量刑は、裁判員裁判の結果それまでよりも明らかに重い方向にシフトした。これはプロの裁判官のみによる刑事裁判を通じて形成されてきたいわゆる量刑相場が、一般市民の参加によって一般人の感覚に近い方向に修正されたものである。こうした方向性は、その後の刑法改正による性犯罪の重罰化とも軌を一にしている。
裁判員裁判によってもたらされたこのような変化は、裁判に対する国民の納得を高めることに繋がり、そうした点において刑事裁判をより良いものにしていると評価し得るであろう。
また、裁判員裁判は、刑事裁判手続の在り方を劇的に改めた。
それまでの刑事裁判においては、捜査段階で作成された供述調書が立証上中心的な役割を果たしてきた。公判の日程も、その都度公判調書や証言の速記録作成を待つこともあって、間隔を置いて設定され、裁判に長期間を要することが少なくなかった。
これに対し、裁判員裁判においては、裁判員が「見て、聞いて分かる」ように、法廷における証人尋問等が重視されるようになり、公判が活性化した。
そして、裁判員の参加を可能にするため、起訴後裁判員が選任される前に公判前整理手続が設けられ、ここで争点を整理してそれに応じた公判の審理日程を立てることにより、公判に要する期間が短縮され、裁判の迅速化が図られた。
それでは、裁判員制度の導入によって、国民と司法との距離が近くなったか。
裁判員制度は、司法に対する国民の理解を深めることにより、これまで三権の中では一般の国民から最も縁遠かった司法を国民にとって身近で頼りがいのあるものとすることを意図したものであった。
この点に関し、少なくとも司法の側に大きな意識の変化があったことは明らかである。司法は、従来自らの専門性にこだわってそこに閉じこもり、市民の側に対してその理解を得るため丁寧な説明をしようとする姿勢に欠ける嫌いがあり、そのため「高嶺の花」などと揶揄されることもあった。しかし、裁判員制度の導入は、司法の側に市民の理解を得なければならないという気運を一挙に高め、法曹三者がそれぞれにあるいは相互に連携しながら、学校等に出向いて行う出前授業をはじめとする様々なチャネルで、積極的に市民の側に接近するようになった。
一方、市民の側においても、裁判員裁判の実施は司法が実は市民社会を支えるものであり決して他人事ではないことに気付く契機となった。そして、司法制度改革を受けて、学校教育に法教育が取り入れられたことも、司法に対する市民の認識や関心を高める効果を生じているものと思われる。
もとより特に市民の側の意識改革は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、息の長い取組が求められると思われるのであるが、市民と司法との関係においても裁判員制度導入の効果は徐々に上がりつつあると言うことができるであろう。
このように、裁判員制度は、これまで概ね成功裏に運用されてきたと評価し得るが、その一方で、様々な課題が浮かび上がっている。
そこで、以下に、裁判員制度を運用する上で課題とされる点のいくつかについて考えてみることとしたい。
辞退者の割合について
辞退者の割合は、6割を超えて高止まりしている。
そのように辞退率が高止まりしていても、幸いこれまで裁判員の選任に支障をきたすような状況にはなっていない。また、実際に選任された裁判員の性別、年齢、職業等の構成も、その母体である有権者の構成と大きく食い違うものにはなっていないと認識している。
したがって、現状において、辞退が、裁判員制度の運用に悪影響を及ぼしているとは言えないであろう。
そして、辞退が申し立てられた場合に、裁判所が辞退事由を厳格に解釈して辞退を認めず強引に裁判員として選任しても、実際のところ、そうした人に裁判員に求められる役割を十分に果たしてもらうことをそれほど期待できないと思われる。
しかし、広く一般市民に参加してもらうという制度の趣旨にかんがみれば、辞退率がこれ以上高まらないようにし、できればそれを低下させることが望ましい。
これまでの分析によれば、辞退率が高止まりしている要因としては、高齢化や雇用情勢の変化、国民の関心の低下、裁判の長期化等が挙げられている。
したがって、これらを踏まえ、例えば、企業における裁判員休暇制度の導入促進等、裁判員を務めやすくする環境整備が図られる必要があろう。
国民の関心を高める方策や裁判の長期化の是正については、それぞれ別に論じる。
国民の関心について
国民の関心について、各種世論調査によると、裁判員を務めることに対しては、7割位の人が「やりたくない」「できればやりたくない」と答えており、辞退率の高さの背景には、そうした国民意識があるとも考えられる。
しかし、私は、真面目で責任感の強い市民の方が裁判員として他人の運命を左右するような立場に立つことについて心理的負担を感じ、「できればやりたくない」と思うのは、ある意味自然な感情であり、そのこと自体を責めることはできず、それを大きく変えることも難しいと思う。
したがって、できれば避けたいと思っている方にも、いったん選ばれたからには公の役割として引き受け、裁判員の役割を果たそうと考えてもらえるようにすることが肝要である。
その一方で、裁判所の調査結果によれば、実際に裁判員を務められた方のうち97%程の方が「やりがいがあった」「やってよかった」という肯定的な感想を持っているとのことである。
そこで、そうした裁判員経験者の体験ややりがいを広く社会で共有することは、一般の方の関心や参加意識を高め、ひいては辞退率を低下させる上で極めて重要であると考える。
裁判の長期化について
審理期間が長期化すれば、裁判員候補者にとってはそれだけ仕事の関係等における支障が増大するであろうから、辞退率を高める要因となることは自明である。そして、裁判の迅速化が裁判員制度導入の重要な成果の一つとして位置付けられていることからすれば、裁判員裁判の長期化は、そうした成果を否定することにも繋がりかねない。
ところが、最近の数字によると、裁判員が関与する第1回公判から判決までの実審理期間が約15日(開廷回数は5回強)、公判前整理手続期間(その開始日から終了日まで)が平均11か月超となっており、いずれも制度発足当時に比べてかなり長期化している。取り分け公判前整理手続については、一部には3年を超えるような事件も出ている。
公判前整理手続は裁判員選任前のものであるから、裁判員の負担に直結するものではない。しかし、公判の開始が遅れれば、その分関係者の記憶が薄れ、被告人の身柄拘束が長期化するなどの問題を生じる。裁判員裁判において、従来の刑事裁判に比して審理期間を短縮したとしても、そこに至る公判前整理手続が著しく長期化したのでは、起訴から判決までの裁判期間を全体として見た時に、裁判迅速化の要請に反すると言わざるを得ない。したがって、公判前整理手続の迅速化は急務である。
公判前整理手続の長期化に関しては、弁護側は検察側の証拠開示の遅れに主因があると主張する。これに対し、検察側は、証拠開示については任意開示を含め積極的に対応しているとした上で、弁護人が検察側請求証拠の開示を受け、被告人の言い分を聞いて早期にその主張を明らかにしなければならないのに、類型証拠開示請求を繰り返すなどして、弁護側主張の明示が遅れていることを指摘するなど、双方の見解は鋭く対立している。
ここでは、専門的技術的な議論に立ち入ることは避け、手続を主宰する裁判所、当事者である検察官、弁護人のそれぞれが公判前整理手続について定めた刑訴法の規定に則り、その迅速化に向け協力して努力すべきであると述べるにとどめる。
市民の意見を反映させる点について
ここではじめに確認しておきたいことは、裁判員制度は、市民である陪審員が裁判官を交えずに有罪無罪を判断する陪審制度とは異なり、市民である裁判員とプロの裁判官の協働によって事実認定及び量刑の両面にわたってより良い裁判を実現しようとすることを本旨とする点である。
そして、裁判員制度が裁判官と裁判員の協働を基本とするものであるからこそ、その運用が安定し、内容的にも大方の納得の得られる判決が出されているものと思われる。
ところで、市民である裁判員が臆せずその意見や感覚を表明しなければ、市民とプロの協働の実を上げることはできない。したがって、プロである裁判官が裁判員に対し丁寧な説明を行い、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど配慮すべきことは当然である。
協働の趣旨からすれば、裁判官もまた、その専門的な知識や経験に基づいて自らの意見を述べるべき立場にあるが、だからと言ってその見解を裁判員に押し付けるようなことがあってはならないことは言うまでもない。
裁判員裁判の評議の運用においては、こうした点について細心の注意が払われているものと理解している。最近の統計では、評議(中間評議を含まない。)には1件当たり平均して14時間余りが充てられている。そして、前述の通り、裁判員経験者の約97%の方がその体験について肯定的評価をしており、評議についても大きな不満は見受けられない。これらは、実際に裁判員の意見を丁寧に聞く運用が行われ、それが判決に結実していることを反映するものであろう。
もっとも、刑事裁判は公平性も重要であり、その意味で、裁判官が量刑の分布を裁判員に示すことは必要であり、それをもって裁判官による誘導であると評価すべきではない。
そして、先に述べた通り、性犯罪に対する量刑は裁判員裁判によって明らかに重くなった。そのことは、裁判員が決してプロの裁判官の意見を追認するだけのお飾りでないことを示す何よりもの証左である。
この点に関連して、裁判官と裁判員の協働を実現する上で、裁判官と裁判員の数を3名対6名としたことは結果として適切であったと思う。
裁判員法の立案の際における最大の争点は、裁判官と裁判員の人数をどうするかであり、様々な議論を経て、裁判官3名、裁判員6名の構成を基本とすることで決着した(詳しくは、コラム#2「裁判員の人数」参照)。
この構成は、年齢も経歴も個性も異なる3名の裁判官が様々なバックグラウンドを持つ6名の裁判員とコミュニケーションをとるもので、人数的に見て、裁判員にとって比較的発言がしやすく、多角的なやりとりが行われることにより、議論を深めて協働の実を上げるのに適していると思われる。
なお、この関係で、控訴審の在り方についても一言する。
裁判員が加わって出された一審の判決を、裁判官のみから成る高裁が自分達であれば採るであろう結論とは異なるというだけの理由で破棄するようなことになれば、裁判員裁判の存在意義が失われる。
しかし、それとは逆に、裁判員裁判の判決に対しては上訴を認めないという制度では、世の中の納得が得られないであろう。また、裁判員裁判の判決は絶対で、これに対しては、何ら制度的なチェックが働かないということになれば、裁判員の中には一層重い心理的負担を感じる方も出てくると思われる。
これまで、高裁は、裁判員裁判の判決が経験則等に照らしておよそ受け入れられないような場合に限って破棄するという謙抑的な姿勢をとっている。個々の判決の結論は別として、そうした基本的な方針は妥当だと思う。
守秘義務について
私は、現行の守秘義務の規定は維持されるべきだと考える。
裁判員制度について一般の方と話をすると、多くの方は、自分の意見が後になって表に出て、事件関係者の恨みを買ったり世間から非難されたりするのが不安だと言う。それに対しては、評議の内容については守秘義務があるので、そのような心配はないと説明すると、一様に安心してもらえる。
インターネットが普及している現在、一たび評議の内容がネットに掲載され、これをめぐって様々な言説が飛び交って炎上するような事態を招けば、裁判の公正さに疑問を抱かせ、裁判員となることに対する不安感を一挙に高め、裁判員制度の運営を危うくすることにもなりかねない。
したがって、守秘義務は、裁判の公正さを保ち、評議において裁判員が自由に意見を表明することを制度的に担保するものとして必要である。
そして、裁判員法は、評議の秘密について、評議の経過、各人の意見、その数を指すものと定めている。これは、評議室でのやり取りを守秘義務の対象とするものであって、最も簡明であり、分かりやすい。
これに対し、評議の内容に関する守秘義務を特定の裁判員等に結び付くものに限定し、そうでないものについては、評議の内容であっても守秘義務の対象から外すとする案などが提唱されているが、賛成できない。そのような案では、却って秘密の範囲があいまいになり、守秘義務違反をめぐってトラブルを生じるおそれがあり、裁判員が判断に迷って不安を抱くことにもなりかねないからである。
裁判員経験者がその経験ややりがいを発信することは、先程も述べた通り、一般市民の裁判員制度に対する理解を深め、辞退率の低下を図る上でも重要である。
しかし、そのような裁判員の経験共有は、秘密とされる評議の内容等に触れなくても十分に可能である。守秘義務については、裁判員を務めたこと自体も秘密にしなければならないとの誤解も一部にある由であるが、公開の法廷で見聞したことや自らの感想を述べることには、何の問題もない。現に判決後の記者会見等において裁判員を務めた方から有意義な体験談が開陳されているところである。
以上、裁判員制度をめぐる課題のいくつかについて私見を述べた。
それでは、最後に、今後の司法の在り方を考える際に、裁判員制度をどのように位置付けるかについて考えてみたい。
市民から信頼される司法へ
長く司法の世界に身を置いてきた者として、司法に対する市民の信頼の基本は、それが公正公平であり、自分達を不正から守ってくれる、ということにあると思う。したがって、犯罪者が処罰されずに横行しているようなことでは、善良な市民の安心安全や生活を守ることができず、司法や法に対する信頼は維持できない。
同時に、刑事裁判は適正な手続に従って行われなければならず、冤罪を生むようなことがあってならないことも当然である。
激動する社会情勢の下で刑事司法がそうした役割を果たすためには、その制度を絶えず見直していく必要がある。
裁判員制度は、日本の刑事司法が、従来の取調べや供述調書に過度に依存したものから、新しい時代にふさわしいものに脱皮していく大きな流れの出発点になった。
今日では広く行われている取調べの録音録画も、最初は、裁判員事件において自白の任意性を立証するために導入されたものであった。
また、裁判員裁判において捜査段階で作成された供述調書の役割が相対的に低下したことは、他の事件にも波及していった。そして、冤罪事件等を直接の契機として、取調べや供述調書に過度に頼らなくても事実が解明できるように、いわゆる司法取引や通信傍受等多様な証拠収集手段を用いる方向へと大きく舵が切られた。これらは、諸外国では日常的に活用されている手法である。
こうして裁判員制度の導入は新時代の刑事司法に通じる扉を開くことになったのである。
最後に一言させていただきたい。
市民の方が裁判員に選任される確率は、現在の制度や事件数を前提に大まかな計算をすると、1年あたり1万5000人に1人程度が選任されるという計算になる。そして、仮に20歳から70歳までの50年間で考えれば、生涯で裁判員を務める可能性は、300人に1人位ということになる。そうすると、裁判員に選任されたとしても、それはまず一生に一度のことであろうと思われる。
読者の方には、その一生に一度の機会に、是非裁判員として司法に力を貸していただきたいと切にお願いする。
追記
私は、本年6月2日のNHK日曜討論「裁判員制度15周年―これからの司法は―」に出演する機会を得た。この討論は、私を含め5人で行われ、課題への対応については多少意見を異にする点があったものの、いずれも裁判員制度については肯定的な評価をしており、これを廃止すべきであるとする者はいなかった。
もっとも、討論の生番組であるという性質上、司会者の私に対する発問や時間の制限もあり、席上必ずしも意を尽くした発言をすることができなかった。そこで、本稿において、討論会で採り上げられた論点に関する私の見解を改めて明らかにすることにしたものである。
本エッセーにおける論点の配列は、概ね当該番組における討論の順序にならっている。