[コラム] A&Sスタートアップ法務の羅針盤 #09 「心がけ」だけでは、パワーハラスメントはなくならない
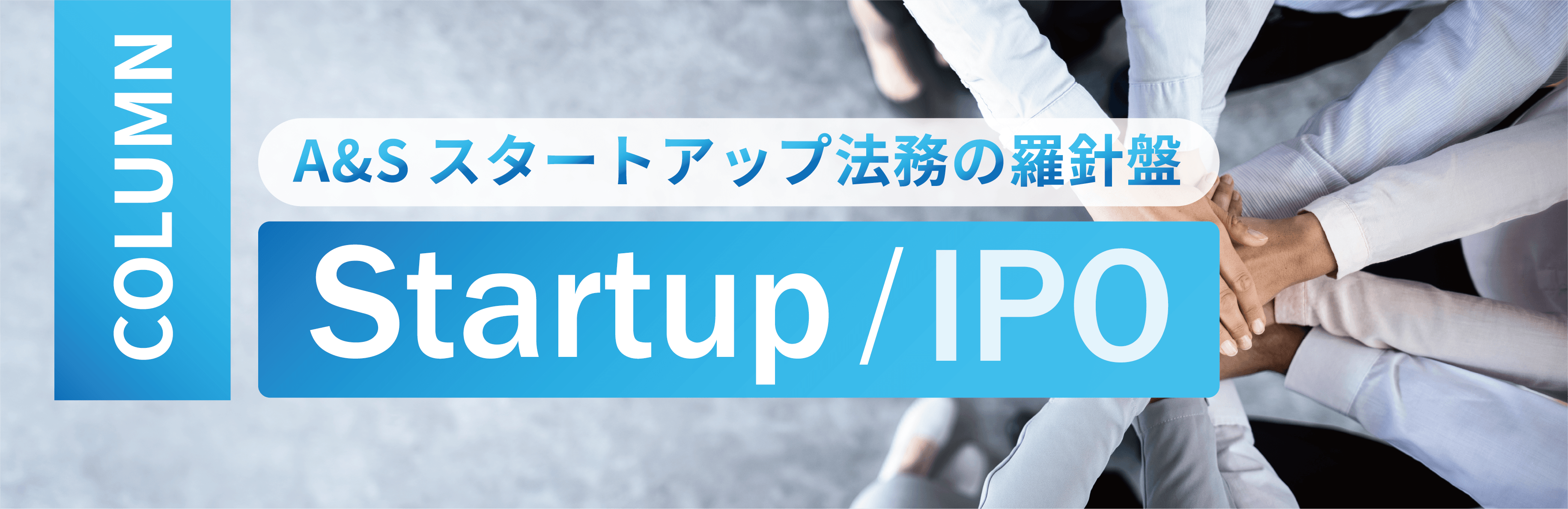
「心がけ」だけでは、パワーハラスメントはなくならない
A&Sスタートアップ法務の羅針盤 #09
2024.3.18
執筆者: 磯部慎吾弁護士(パートナー)
1 パワーハラスメントは、職場からさまざまなものを失わせる
事業者のみなさまは既にご存知だと思いますが、労働施策総合推進法という法律により、パワーハラスメントを防止するための措置を講じる義務が課されています。すでに、パワーハラスメント防止に向けた研修の実施や、ハラスメント相談窓口の整備などの対応をされていると思います。
では、なぜパワーハラスメントを防止しなければならないのでしょうか。
ぱっと思いつく弊害としては、被害に遭った社員が離職する・メンタルヘルスを損なう、ひいては損害賠償請求されるといったリスクがありますが、これにとどまりません。
例えば、被害に遭った社員だけでなく、その様子を見聞きしていた社員についても、ストレスによりパフォーマンスの低下を招くことが知られています。また、上司等からの叱責を恐れて、社員が新しいアイディアの提案や、業務上求められるチャレンジを意図的に回避するようになります。こうした職場の深刻な機能低下をもたらすほか、人材流出も進みますし、新たによい人材を獲得することも難しくなります。今後は、「ビジネスと人権」の文脈で、サプライチェーンから外されるおそれすらあります。
また、改ざん・隠ぺいといった不祥事を起こした企業では、背景にパワーハラスメントが存在するケースが多く見られ、企業のレピュテーションを失う原因にもなっているのが実情です。
2 このような職場は、既に危険水域だなと感じてください
あなたが経営する企業の営業部門は、部長1人・課長2人と、いわゆる正社員、有期契約社員、派遣社員などの部下社員約20名からなるチームです。
半年前に、営業部門の人員増大に伴い、課長1人体制から2人体制に拡充しました。
部長のAは、おとなしい性格ですが、営業計画・予算策定・人員配置といったマネジメント能力が高く、安心して営業部門を任せられます。
課長のBは、総務部門や経営企画部門で活躍した後、1年前に経理部門から異動しました。会社全体を見通す視野を持っており、営業部門の社員からも一目置かれています。
今回新しく昇任した課長のCは、いわゆる努力型で営業成績も抜群で、ぐいぐいとした突破力もあるタイプであるところ、部下からは「厳しい…」という声が挙がっているようです。ただ、B課長から見ても「少し実力が足りない」と評価されている社員のようなので、あなたは、叱責される社員の方に問題があると見ています。
あなたが気になっているのは、最近3か月で、C課長の部下から2人の退職者が出たほか、B課長にメンタルに不調をきたしてしまったことです。
退職者2人は、いずれも契約を逃したことや目標未達だったことについて、C課長に厳しく追及されたと訴えていたようです。ただ、近くで見ていたA部長によると、理路整然と指摘していただけで怒鳴ってはおらず、敢えて止める必要も感じなかったとのことでした。
他方、B課長は、穏やかな性格が災いしたのか、営業部門の古株である3人の部下から、日々かなり強い言葉で反抗的な態度に出られていたらしく、これがきつくて参ってしまったようです。
会社として、どうすべきだったのでしょうか。
3 パワーハラスメントの3要件
パワーハラスメントについては、労働施策総合推進法や、厚生労働省の指針で定義されています。具体的には、
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③その雇用する労働者の就業環境が害されるもの
をいいます。
①の「優越的地位」という言葉からは、「上司が部下に」という場合を想定しがちですが、それだけに限定されません。業務上必要な知識を多く持っているとか、集団を形成しているといった場合も含まれます。そのため、事例のように古株の「部下」3人が、他部門から新しく来た「上司」であるB課長に対する言動についても、この①の要件を満たすことがあります。
②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」は、ケースごとの総合判断になります。業務の目的や、行われた言動の態様や手段などを個別具体的に検討して、そもそも不必要な言動ではなかったか・不適当な言動ではなかったのか・やりすぎで不相当な言動ではなかったかといった観点で判断をします。
では、③の「就業環境が害される」については、社員の能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど見過ごせない程度の支障が生じることいいます。大事なのは、③に該当するかの判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」が基準とされることです。ですから、部下が精神的にタフで文句を言わない場合であっても、必ずしもセーフとはなりません。
4 パワーハラスメントの6類型
こうした①②③の要件を満たせばパワーハラスメントとされますが、その具体的な態様は、ケースによって様々です。そこで、ここではイメージを持ちやすいように、厚生労働省がまとめた6つの類型を紹介いたします。なお、いずれも、①職場において行われる優越的な関係を背景として行われていることを前提としています。
1つめは、「身体的な攻撃」です。これは、殴る蹴るなどしたり、けがを負わせたりすることで、暴行罪・傷害罪といった犯罪に当たります。
2つめは、「精神的な攻撃」です。酷い例ですと、脅迫・名誉毀損・侮辱など、やはり犯罪に当たります。また、必ずしも犯罪に当たらないレベルのもの、たとえば、必要以上に長時間にわたって叱責を繰り返す、「本当に大学を卒業したのか」「係長をしているのに、こんな基礎的なことも知らないのか」「寝言は寝て言え」など人格否定をする、他の大勢の社員の前で威圧的な叱責を行うなどの言動も、「精神的な攻撃」に該当することがあります。なお、怒鳴ったかどうかは、必ずしも決定的な要素ではありません。
3つめは、「人間関係からの切り離し」です。たとえば、ある社員1人を部署全体で無視して孤立させるといったものが典型例です。
4つめは、「過大な要求」です。例えば、業務に習熟していない社員に到底こなしきれない業務を与えた上で達成できないからと叱責するといった言動が挙げられます。
5つめは、「過小な要求」です。こちらは、気に入らない社員の心を折るために、敢えて仕事を与えず放置することが典型例です。
最後に6つめは、「個の侵害」です。これは、社員のプライバシーに属することに過度に立ち入ることです。たとえば、単なる個人的な興味に基づいて社員の交際歴や休日の過ごし方などについて根掘り葉掘り尋ねる、社員のSNSをチェックして「友達申請」を送り付ける、社員の病歴・不妊治療などの機微な個人情報を本人の同意なく暴露するなどの行為が挙げられます。
5 言った側に悪気がなくても、パワーハラスメントを否定する理由にはなりません
今回の事例ですと、C課長は、「こんな仕事をしているようではダメだ」と感じた社員に対して、「こいつのために、ひいては会社のために」という思いで敢えて厳しく指導をしています。ヒアリングでも「自分の言動に非があるなどとは、全く思っていなかった。」と答えるはずです。
しかしながら、こうした思いが動機になっていたとしても、それを理由にパワーハラスメントであることが否定されることはありません。
なぜかと言いますと、パワーハラスメントは、詰まるところ①②の要件を満たす客観的に就業環境を害する行為だからです。そのため、該当するかどうかも、「平均的な労働者の感じ方」を基準に客観的に判断されます。
6 規程を整備しても研修を重ねても、パワーハラスメントはなくなりません
いくら就業規則などの社内規程の整備をしても、いくら社内研修を繰り返しても、それだけでは、なかなかパワーハラスメントがなくならないと言われています。
原因はいくつも考えられます。例えば、C課長のようなタイプの上司は、実は非常に多くいらっしゃるのですが、ご自身にパワーハラスメントだと気付いてもらうことは、期待できません。そのため、上司であるA部長や同輩であるB課長が注意する必要があります。ただ、「正当な指導だ。」と反論するC課長にどこまで注意できるのかは、かなり疑問です。また、抜群の営業成績を残しているC課長が上司にいい顔を見せるタイプだった場合には、叱責された部下の方に非があるとみなされがちです。結果、C課長への注意が、どうしても中途半端になってしまいます。
また、A部長のように傍観するタイプの上司がいると、部下達が「C課長の行為は、会社に承認されている」と受け止めることが多く、就労環境の悪化を促進させてしまいます。
規程や制度の整備、研修による教育はもちろん大事です。しかし、これに加えて「研修の知識を持っていても、自分がパワーハラスメントを起こしている、あるいは促進していると自覚することができない社員が、決して珍しくないレベルで実在する」という現実を直視した対策を講じる必要があります。
具体的には、ステークホルダー目線で「仕事相手として・就職先として、パワハラ体質の会社を選ぶか?」「わが社のMVVに反しないか?」などの原点に立ち返った上で、パワーハラスメントに対する会社の姿勢を鮮明にすることが必要です。
また、各社員が、パワーハラスメントを見付けたときに、相談・通報するのは当然のこととして、更に「見付けた社員の職位に応じて具体的にどのようなアクションをすべきか」というレベルまで具体的に落とし込んだ対応策を周知し、社員が安心してそのアクションに取り組めるような運用を構築することが望ましいと考えられます。
以上
