[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#17 投資分野における人権(1)」:入江克典弁護士(パートナー)
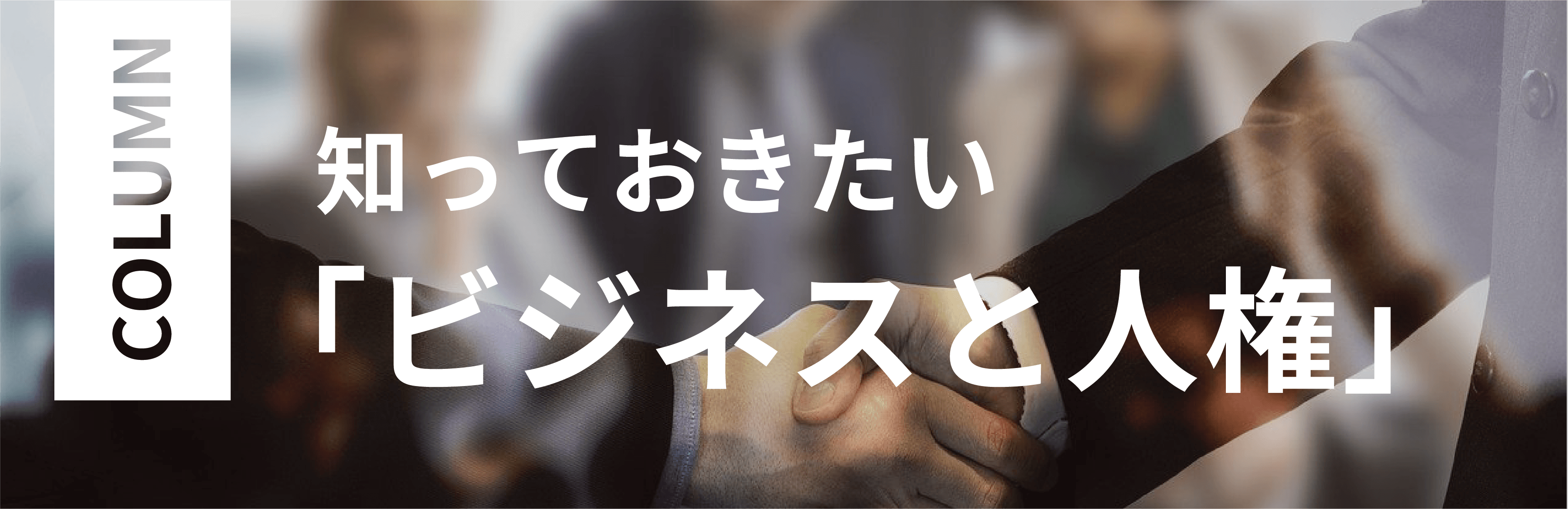
投資分野における人権(1)
知っておきたい「ビジネスと人権」 #17
2025.6.24
これまで数回の連載で、「ビジネスと人権」の問題を業種・業界に特有のファクターや人権リスクに分類し、「製造業」と「建設業」における人権問題を解説しました。今回と次回は、「投資業」における人権問題について解説します。投資先企業の消費者や労働者との間に直接的な関係がない機関投資家は、投資先企業の人権問題に対してどのような責任を負うのでしょうか。詳細は、OECD(経済協力開発機構)が策定した「機関投資家の責任ある企業行動」(2017 年)、PRI(責任投資原則)が策定した「投資家が人権を尊重するべき理由およびその方法」(2020 年)、ILO(国際労働機関)とPRI が策定した「機関投資家向け『ビジネスと人権』ガイド」(2024 年)などにまとめられていますのでご参照ください。
昨今のニュース報道からも明らかなとおり、企業が人権問題にいかに対応するかがビジネスの存続を左右しますが、投資家は、人権の視点から企業の行動を変える大きな力を持っています。特に、一企業である機関投資家は、人権要素を考慮した投資戦略やスチューワードシップ活動(対話などを通じた影響力の行使により投資先企業の価値を高める取り組み:次回に詳述します)を通じて、投資先企業に対し、人権問題への対処に対する働きかけを行い、企業体質や体制の変更を促し、透明性のある情報開示を求め、企業価値を最大化するよう後押しすることができます。
投資家による人権尊重の取り組みの促進は、これまであまり積極的ではありませんでした。投資分析・判断に用いるESG(環境・社会・企業統治)指標において、環境や気候変動に関する「E」への関心が集中し(例えば、温暖化抑制に向けた取り組みの奨励)、人権を含む「S」は相対的に注目されていませんでした。たしかに、「S」に関するリスクファクターは定量的に測定しにくい側面があるといえます。
◇企業価値の毀損を回避
しかし、人権対応の失敗が事業に対して重大な影響を与え、企業価値を毀損(きそん)することは明らかです。最も顕著なものは、NPO によって劣悪な労働環境や商品の安全性に対する懸念などの人権問題が告発され、SNS 上での炎上を通じて消費者が不買運動を起こし、売り上げが低下するケースです。また、人権対応を誤った結果、労働者がストライキを起こしたり人材が流出したりすることで業務が停滞し、ひいては事業の撤退を余儀なくされるケースもあります。さらに、法的には、人権侵害の発生により、輸出先の国の法令によって製品の輸入が禁止されたり、国や自治体等が実施する入札に参加できなくなったり、訴訟を提起されたり、行政罰を科されたりすることもあります。加えて、人権侵害対応の稚拙さにより、瞬時にして株価が下落します。時価総額数百億円が消失する例もあり、企業価値の損失は甚大です。また、長年かけて築き上げたブランドイメージが毀損され、消費者に対する販売力が低下し、労働者に対する就労先としての魅力が低下します。
投資家は、以上のような投資先企業における人権リスクを通じた事業の損失や企業価値の毀損を回避するため、そのようなリスクの予防や軽減のための措置を働きかける責任を負っています。投資家は、「E」の要素と同様に、強制労働、不平等の解消、プライバシーといった人権を含む「S」の要素を投資判断の中核に据え、投資先企業の社内プロセスの改善といった外観のみならず、労働者、消費者、地域社会のための実質的な改善を促進し、持続的な企業価値の向上につなげる役割を担っています。
次回は、投資家が投資先企業の行動を変えるための具体的な方法について述べます。
※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2025年6月4日号より転載
