[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#14 製造業におけるサプライチェーン(2)」:入江克典弁護士(パートナー)
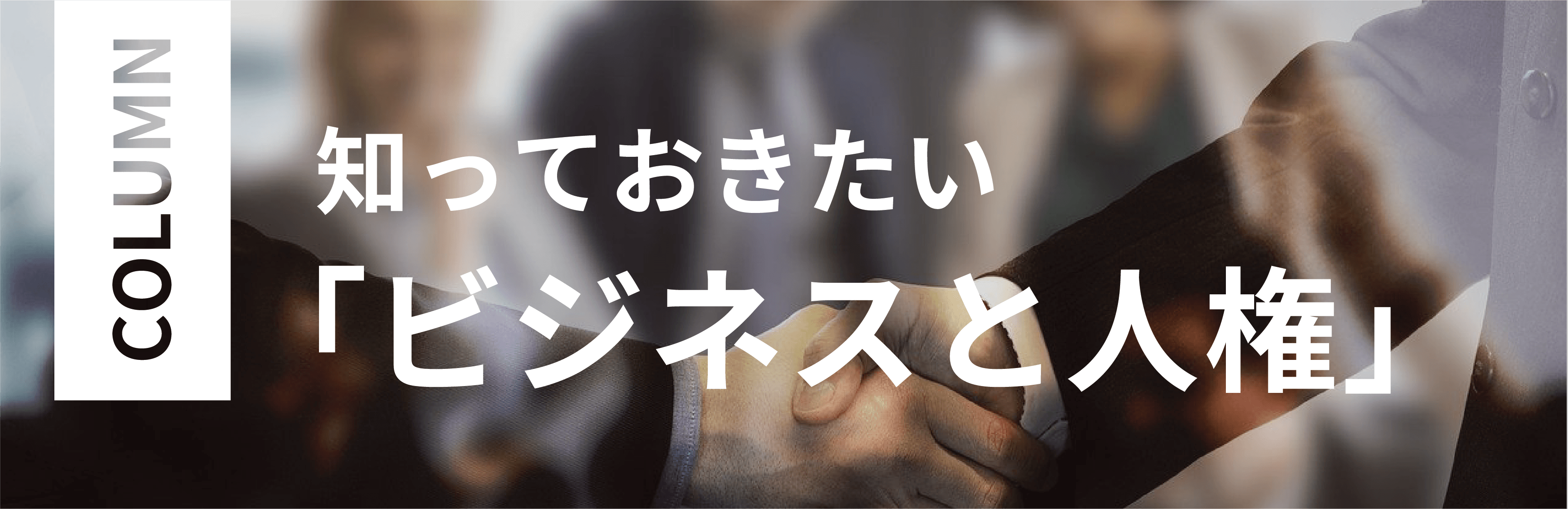
製造業におけるサプライチェーン(2)
知っておきたい「ビジネスと人権」 #14
2025.3.24
2025.3.24
前回は、製造業サプライチェーンにおける人権リスクを概観しました。これを踏まえて今回は、特定された人権問題に対して企業が取るべき対処について概説します。このように、人権に対する悪影響を特定・評価し、対処するプロセスが国連指導原則に基づく人権デューデリジェンス(DD)です。
本稿では特に、サプライチェーンというビジネスモデルに着目して述べていきます。
本稿では特に、サプライチェーンというビジネスモデルに着目して述べていきます。
サプライチェーンにおける人権リスクの構造的な要因は、透明性の欠如です。その透明性は、製品品目の数とそれに伴うサプライヤーの数、自社とサプライヤーの関係性(継続性、契約期間など)、下請け業者の選定の可否とその選定プロセス、リードタイムの長短、製品サイクルの頻度、地域的な多様性といった事情により左右されます。したがって、企業はサプライヤーに発注前に、またはすでに発注済みであればその後に、ステークホルダー(利害関係者)への関与を通じてサプライヤー(上流を含む)をよく知るとともに、その優先順位に従い、人権に対する悪影響の防止・緩和の観点からサプライヤーを査定することが重要になります。
例えば、サプライヤーが人権侵害防止のための方針を策定し、研修等を実施し、従業員に対する周知がなされているか、安全な労働環境が整えられているか、製品の製造過程で従業員の身体に対する危険性がないか、下請け事業者を選定しているか、現場レベルでの苦情処理の仕組みが構築されているか、リスク特定のための継続的モニタリングが可能かなどを評価することが考えられます。
サプライヤーに対する影響力の行使
そして企業は、人権侵害が明らかになればサプライヤーに対して影響力を行使して、その害悪を防止・緩和することが必要となります。自社と直接の契約を持つサプライヤーやそのサプライヤーと関係する下請け事業者に関してであれば、注文を増減させたり、契約期間を調整したり、契約解消を視野に入れたりといった方法で、契約関係の中で害悪に対する措置を求めることができます。契約関係がない場合は、是正のための計画策定や技術提供という形で支援を行うほか、サプライチェーンの中での上流サプライチェーンに対するDD を促したり、人権状況を追跡調査できるための体制を確立したりすることも考えられます。また、グローバルまたは地域レベルのセクター全体で連携して影響力の行使に取り組むことで、個別のサプライヤーのみならずより規模の大きなサプライヤーに影響力を及ぼすことも考えられます。バングラデシュでは、2013年の「ラナプラザ事件」発生の後、衣料品製造業界における労働衛生環境に対する政府の監視の目が行き届かない中、グローバルブランドの協力体制によって下請け製造業者に対する監視体制を構築しました。そして人権DD では、サプライヤーに対して措置を求めた後も、その措置が人権リスクに対してどの程度効果を出したのかを追跡し、そして結果を公表することが一連のプロセスとして求められています。
次回は、建設業における移民労働者の人権問題について概説する予定です。
※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2025年3月5日号より転載
