[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#12 東南アジアにおける人権政策の展開」:入江克典弁護士(パートナー)
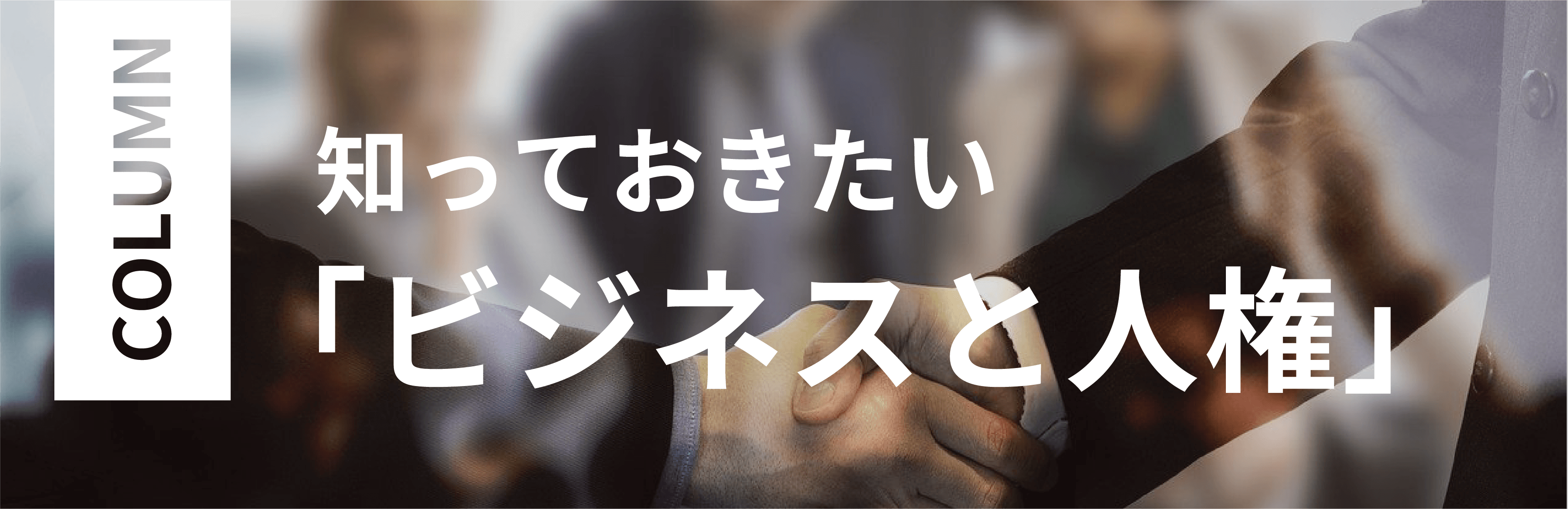
東南アジアにおける人権政策の展開
本稿では、前回までの欧米での規制の解説に続き、日系企業の進出が多いアジアの状況について触れたいと思います。
グローバル企業による人権侵害が世界的に広く認識されたのは、東南アジア・南アジアからでした。1990年代、ベトナムやインドネシアなどで、ナイキ社の仕入れ先による児童労働や劣悪な環境下での強制労働が明らかになりました。世界的な不買キャンペーンの下、同社の評判と株価は下落しました。2013年、バングラデシュで、グローバルアパレル企業の製造を受託していた縫製工場のビル(ラナプラザ)が崩壊し、工場の従業員1100人以上が死亡する事故が起きました。この衝撃がアパレル業界をはじめ多くの業界団体でサプライチェーンにおける人権対応を加速させるきっかけとなりました。2021年、ミャンマーで国軍クーデターによる軍事政権が誕生しました。軍閥企業との関わりなどを通じて人権侵害に加担することがないようにする責任が各企業に対して強く求められています。2022年に国際労働機関(ILO)が公表した統計(Global Estimates of Modern Slavery:Forced Labour and Forced Marriage)によれば、アジア太平洋地域における強制労働の数は、世界全体の半数を超えています。
以上のように企業活動で人権侵害が発生するリスクが依然極めて高い東南アジアでも、「ビジネスと人権」に関する政策が拡大しています。タイ、ベトナム、インドネシアでは、それぞれ国別行動計画(NAP)が策定されました。マレーシアでも、本稿執筆時点(2024年11月)で、NAP策定が目前に迫っています。NAP策定を受けまたはNAPを策定していない国でも、個別の法制度(例えば、労働法制や上場企業に対するサステナビリティ義務報告制度)においてビジネスに際しての人権保護のための仕組みづくりが進んでいます。本稿執筆時点でいずれの国も、人権デューデリジェンス(DD)義務化に踏み込んだ法規制にまでは至っていませんが、欧州諸国との国際取引が活発である中、前回紹介した欧州連合(EU)の「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」の発効により、東南アジアでも法制化に向けて加速する可能性があります。
タイ
2019年10月にアジアで初めてNAPを策定したタイは、2023年に改訂版が公表されています。人権DDの義務化にまでは至っていないものの、タイ国家人権委員会が「人権DDハンドブック」を策定・公表したり、タイ証券取引所が策定した「現代奴隷リスクに対するガイドライン」により、現代奴隷のリスク特定やその対処を支援したりといった取り組みが進められています。
ベトナム
ベトナムは、2023年7月に首相決定(第843/QD-TTg号)によりNAPを公表しました。(1) 投資、(2) 労働、(3) 脆弱な集団の権利保護、(4) 環境、(5) 消費者の権利保護の5つを優先項目として掲げており、これらの分野での既存の政策・法令の改訂・改正や新法の制定が見込まれています。
インドネシア
インドネシアは、2023年9月に大統領規則(第60号)を通じてNAP(国家戦略)を公表しました。インドネシアが経済協力開発機構(OECD)の加盟交渉を進める中でNAPの継続的な実施が重要になるとみられています。インドネシアNAPは、今後これを具体化する実施規則の導入を想定しており、企業関係者向けの人権、環境等に対するリスク評価モジュール(インドネシア語でPRISMA)の活用などを通じて、人権DD実施義務が制度化される可能性があります。
以上のとおり、東南アジアでもビジネスと人権関連の政策が始動し、法制化に向けて動きだしています。2020年のNAP策定の後、いち早く人権DD実施のためのガイドラインを策定した日本政府は、東南アジア各国に多くの日系企業が進出している状況を踏まえ、NAPが画餅に帰すことのないように各国と連携していくことが求められます。また、東南アジア各国で事業を行う日系企業は、法制化の動向を注視するとともに、人権保護のための体制づくりを着実に進めていくことが重要です。
※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2024年12月4日号より転載
