[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#6 人権侵害に対する救済手続き-企業による人権対応 (3) -」:入江克典弁護士(オブ・カウンセル)
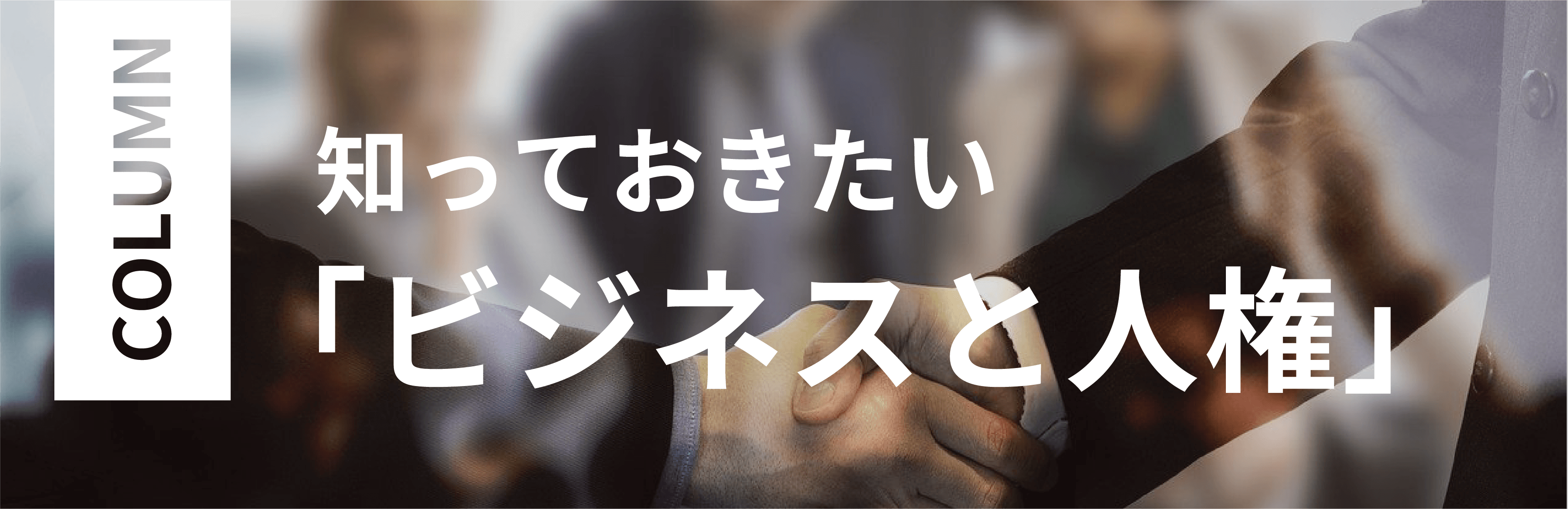
人権侵害に対する救済手続き-企業による人権対応 (3) -
知っておきたい「ビジネスと人権」 #06
2024.7.3
今回は、「ビジネスと人権に関する指導原則」で企業に求められる3つ目の責任である人権侵害に対する救済手続きについて、日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」などに基づき、ポイントを示します。
苦情処理メカニズムの設置
前回、人権デューデリジェンス(DD)の解説の中で、人権への影響を防止し、軽減する措置を取るに際しては、(1) 自社が人権への負の影響を引き起こし、または助長している場合(例:自社製品に起因する利用者の健康被害)と、(2) 自社の事業、製品、サービスなどが負の影響に直接関連している場合(例:サプライチェーンにおける児童労働)の2つに分けて説明しました。(1) の場合は、影響を生じさせる活動を停止し、直ちに対処し、そのための計画を立てること、(2) の場合は、取引関係を継続する中で(直ちに取引を停止せず)、影響力を行使しながら、改善を促すことが求められます。
人権侵害に対する救済についても、上記 (1) の場合は、被害を受けた者に対する救済の実施または救済の実施への協力が求められます。例えば、被害者に対する謝罪、原状回復、金銭的または非金銭的な補償を行い、再発防止プロセスの構築・表明を行うことが考えられます。他方、上記 (2) の場合は、救済の実施までは求められていないものの、人権への影響を防止し軽減するための行動を取るべきだとされます。例えば、サプライヤーの従業員から自社に入ったサプライヤーに関する苦情等に関し、サプライヤーに対して改善の要請を行うことが考えられます。
企業は、上記 (1) の場合の救済を早期に実現するために、人権救済のための苦情や紛争の処理に関する手続き(苦情処理メカニズム)を自ら設置するか、または、業界団体など第三者機関や国家が提供する救済手続きに参加する必要があります。例えば、企業において国内外のサプライヤーの従業員も使用できるホットラインを設置すること、外国人従業員が自国の言語で相談できる窓口を設置すること、企業内に苦情処理委員会を設置することなどが考えられます。第三者機関が設置する苦情処理メカニズムとして、例えば、JaCER(一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構)や責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム(一般社団法人 JP-MIRAI)が提供する苦情処理・相談窓口があります。国家による救済としては、裁判所による裁判、厚生労働省の個別労働紛争解決制度、OECD多国籍企業行動指針に基づき外務省・厚生労働省・経済産業省の3者で構成する連絡窓口(National Contact Point)、法務局における人権相談および調査救済手続き、外国人技能実習機構における母国語相談などがあります。
救済手続きに必要な8要件
企業が自ら苦情処理メカニズムを設置するに際しては、(1) 正当性(苦情処理が公正になされ、信頼を得ているか)、(2) 利用可能性(幅広く手続きが周知され、そのアクセスに支障がないか)、(3) 予測可能性(手続きの内容が明確か)、(4) 公平性(苦情申立人に対する情報や専門知識の提供等がされ、手続きに対する合理的なアクセスが確保されているか)、(5) 透明性(手続きの経過や実効性について苦情申立人に対する情報提供等がされているか)、(6) 権利適合性(手続きとそれによる救済が国際的に認められた人権の考え方に適合しているか)、(7) 持続的な学習源(手続きにおいて将来の教訓を得ることができるか)、(8) 対話に基づくこと(苦情処理においてステークホルダーとの対話に焦点が当てられているか)、という8つの要件を満たすことが求められます。リソースが不足している中小企業においては、まずは上記の第三者機関による仕組みを活用しながら救済手続きを提供していく方が現実的かもしれません。
以上のとおり、今回は、企業の責任としての人権侵害に対する救済について説明しました。適切な救済の種類や組み合わせは人権侵害の性質や範囲によって異なりますので、企業は、侵害を受けたステークホルダーの観点から適切な救済を提供する必要があります。
※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2024年6月5日号より転載
