[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#5 人権デューデリジェンスの実施-企業による人権対応 (2) -」:入江克典弁護士(オブ・カウンセル)
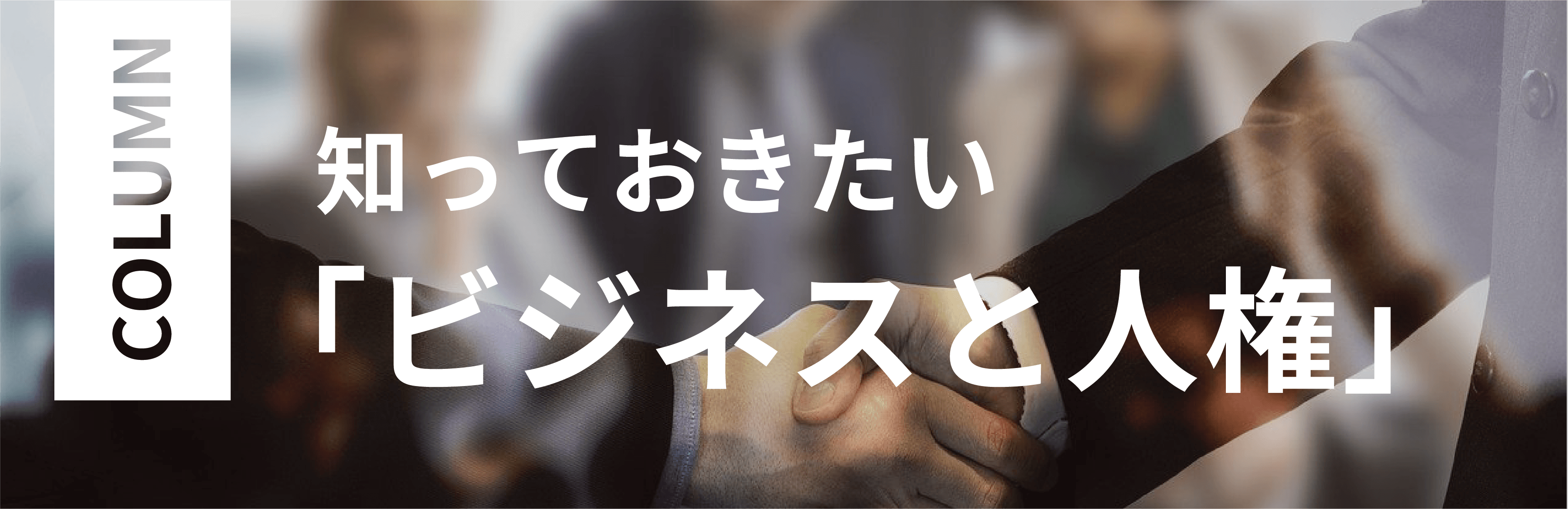
人権デューデリジェンスの実施-企業による人権対応 (2) -
知っておきたい「ビジネスと人権」 #05
2024.6.19
今回は、「ビジネスと人権に関する指導原則」で企業に求められる2つ目の責任である「人権デューデリジェンス(DD)」について述べたいと思います。日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や経済産業者が公表した「実務参照資料」などに基づき、企業が実施すべき人権DDの基本的な4つのステップを概説し、ポイントを示します。
人権リスクを特定し影響を評価
企業はまず、(1) 自社やサプライヤーにおいて人権リスクが重大な領域や人権侵害の発生過程を特定し、その影響と企業の関わりを評価し、対応の優先順位を付けることが必要です。全ての人権リスクに対して濃淡を付けずに対応するのは、企業にとって負担が大きく、逆にリスクが見落とされる可能性があります。よって、人権リスクが深刻な対象から優先して進めることが重要です。また、リスクの特定や評価には、労働者(労働組合)、消費者、NGO、使用者団体といったステークホルダーの意向に耳を傾けて尊重していく対応が求められます。特に、脆弱な立場にいる可能性があるステークホルダー(例えば、外国人、女性、障害者)の声にはより一層の配慮が必要でしょう。このような人権リスクの特定や評価には、「実務参照資料」に付属されている「作業シート」が有用です。
次に、(2) 設定した優先順位に従って、人権侵害を防止し、軽減する措置を取ることが必要です。取るべき措置は2つの場合に分けて考えます。まず、(1)自社が人権侵害を引き起こし、または助長している場合(例えば、自社が取引先に販売した製品を取引先が他の化学物質と併用したことによって水質の汚染が生じ、周辺住民の生活や健康に影響を及ぼす場合)は、企業はその活動を停止し、またはステークホルダーとの協議を経ながら停止するための計画をすみやかに策定する必要があります。他方、(2)自社の事業、製品、サービスなどが人権侵害に直接関連している場合(例えば、サプライヤーの工場で児童労働が行われている場合)は、企業は取引関係を継続する中で、影響力を行使しながらその改善を促し、契約上の条項に落とし込むなどの対応を取る必要があります。取引の停止は、これらの対応が功を奏しなかった場合の手段として捉えることが重要です。
説明責任を果たし透明性高める
そして、(3) そのDDが効果的に行われたかを評価し、その結果に基づいて継続的な改善を進めることが必要です。人権DDは、反復継続して行っていく取り組みですので、DDで得られた教訓を今後の事業や人権DDに生かしていくことが重要になります。ステークホルダーとの協議を継続しながら、企業内部や取引先のDDの実施状況を定期的に監視し、事業やDDのプロセスに落とし込むことが必要となります。
最後に、(4) そのDDから得られた成果について開示することが必要です。人権侵害の事実は企業にとって明らかにしたくないことかもしれませんが、その説明責任を果たすとともに、改善策を具体化することによって透明性の高い企業としてその企業価値を高めることにもつながります。
以上のとおり、人権DDの基本的な4つのステップを概説しました。多くの企業、特に人員と予算が十分でない中小企業は、どこから人権DDを着手すべきかの悩みを抱えていると思います。しかし、上述のとおり、全てのリスクやステークホルダーに網羅的に向き合うよりも、リスクに応じて思い切って優先順位を付けたうえで、そこから現れた個々の課題に誠実に取り組んでいくことこそが重要です。そのためには、経営陣が、人権対応をコストとして捉えず、自社の製品やサービスを改善するための不可欠のプロセスとして捉え、全社的な対応を取るべく指揮することが必要でしょう。
次回は、指導原則によって求められる3つ目の責任である「人権侵害に対する救済」について述べます。
※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2024年5月2日号より転載
